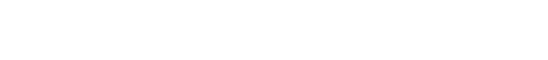2025年10月9日から16日にかけて、山形市において「山形国際ドキュメンタリー映画祭2025」が開催された。26,000人を超える観客、監督・審査員等ゲスト、映画関係者が国内外から山形を訪れ、メイン会場となった中央公民館ホールをはじめ、各会場、ホールは大勢の人々で賑わい、熱気が溢れた。2023年に続き、今回もこの映画祭に参加できたので、その報告をしたい。

(宮嶋俊一撮影)
本映画祭では、メインとも言える「インターナショナル・コンペティション」を始めとして、アジア作品を紹介する「アジア千波万波」や「日本プログラム」、さらには「アメリカン・ダイレクト・シネマ」や「パレスチナ-その土地の記憶」といった特集上映などいくつもの企画があり、それらすべてを本稿で紹介することはできない。よって、取りあげるのはコンペティション部門に出品されたいくつかの作品ということとなる。それら作品の紹介に加えて、上映後の質疑応答やインタビューで関係者から語られた言葉を交えつつ、「ドキュメンタリー映画に描き出された過去と現在」という視点から紹介をしたい。
まず紹介したいのが、ジャンフランコ・ロージ監督作品『Below the Clouds』(イタリア、2025年)である。

作品の舞台は、イタリアのナポリ、ヴェスヴィオ山の麓である。本作に映し出されるのは、当地での現在の人々の暮らしや出来事であるのだが、映像がモノクロであることや遺跡発掘の様子が紹介されることによって、描き出されているのが遠い昔のことであるかのような印象を受ける。
本作には、ストーリーらしきストーリーはなく、その地での出来事が次々に映し出される。明け方に発生した地震の揺れが市民の眠りを覚ます。消防署には不安を抱えた市民から電話の声が届く。その声に、署員は丁寧に対応するが、中には夫のDVを訴える電話もかかってくる。
あるいは、博物館の地下の保管庫の様子。その鉄栅が開かれ、館員が中に入っていくと、懐中電灯がそこに置かれた遺物を照らし出す。また、別の地下には盗掘団のトンネルが張り巡らされており、そこを消防隊員たちが探索する。さらには、東京大学のチームがポンペイの遺跡で発掘にあたっている様子も紹介される。突然登場する日本語での会話に驚かされる。
火山の様子が映し出されることで、そうした出来事のすべてが、街の背後にあるヴェスヴィオ火山の麓の街で起こっていることなのだと意識させられる。遺跡や遺物が映されることによって、過去の記憶が呼び起こされる一方、港では、貨物船の船倉でシリア人の若者が、小麦の荷揚げに奮闘している。ここで映像は、まさに現在と結びついてくるのである。
同じように古代の遺跡を映し出しているのが、モーレン・ファゼンデイロ監督作品『季節』(ポルトガル、フランス、オーストリア、スペイン、2025年)である。

だが、その描き方は『Below the Clouds』と大きく異なる。舞台は、広々とした野原と草原が拡がるポルトガルのアレンテージョ地方。作品では、第二次大戦期に巨石を発掘したドイツ人考古学者、ライスナー夫妻の手紙が読み上げられる。そして、彼らを引き継いだ現代の考古学者や学生たちが発掘を行う。だが、監督はこの作品を「考古学について」の映画でではなく、「考古学的」映画であると言う。古代の遺跡を取りあげているから「考古学的」というだけでなく、この映画の手法そのものが「考古学的」であると監督は述べていた。
それを象徴するのが、古代の伝説を役者が演じる場面である。黄金の飾りを髪に巻いた古代の少女が出現し、伝説を再現する。これはフィクションである。私は監督に、ドキュメンタリー作品において、このようなフィクショナルな映像を挿入することの意味を問うた。監督によれば、その土地に赴き、その風景を見て、伝説を集め、そして当時その地で人々が何を感じていたのかを想像して、この場面を撮影したと言う。その意味で、本作は「想像的ドキュメンタリー」であると言う。考古学的であるとは、想像力の助けによって、リアルな過去に向き合うことであると私は理解した。
さて、過去の記憶という視点から紹介したいのがイグナシオ・アグエロ監督作品『亡き両親への手紙』(チリ、2025年)である。

冒頭で、アグエロの自宅の窓から見える美しい庭や空が映し出される。それを見ると、私的で叙情的な作品であるとかと思わせるのだが、そうではない。父親と共に工場で働いていたかつての労働組合員マルコス・メディナへのインタビューでは、母や家族の思い出から話が広がり、メディナ自身やその家族、さらにピノチェト独裁政権下での社会の記憶へと内容が拡がっていく。そこで呼び起こされるのは、独裁政権下で虐殺された犠牲者や行方不明者たちである。ノスタルジックな映像で始まったにも関わらず、それはいつしか社会派ドキュメンタリーとしての相貌を見せ始める。
監督によれば、ピノチェト政権の虐殺があった時、彼は21歳であり、大きなショックを受けたとのことだ。彼によれば、民主主義が失われていたピノチェト政権時代を描いた映画はあまりない。だが、自分はそうした問題を取りあげるためにドキュメンタリー映画作家になったわけではない。ドキュメンタリー作家になりたいという強い意志はあまりなく、当初はフィクションを作りたいと思っていたが、あまり考えずに映画を撮っているうちに、ドキュメンタリー作品を作り始めていた、ということである。そうしたこともあって、叙情的な映像(それらはこの作品のために撮影したものではなく、撮りたいから撮ったものだそうだ)と社会史的な内容を結んだ作品となっているのだろう。
なお、上映後の質疑応答で監督は面白いことを話していた。映画を見ながら眠ってしまった人がいたかもしれないが、映画に刺激されて眠るのは良いことである。なぜなら、映画を見ながら夢を見て、それが見ている映画と融合し、新しい作品が生まれるからであり、それは素晴らしいことだ、と。「季節」の監督であったファゼンデイロもやはり、これとは違った角度からドキュメンタリー作品における想像力について肯定的に語っていた。歴史学者は歴史を実証的に再現することを目指すが、映像作品はそれ(だけ)を目指すわけではない。夢想的創造力ということを考えさせられた。
記憶ということで、最後にもう1作品紹介したい、それは香港の長洲島にある食堂を舞台にしたフランキー・シン監督作品『日泰食堂』(台湾、香港、フランス、2024年)である。

本作は2019年の映像から始まるが、当時の香港では反政府デモが熱を帯びていた。その後、COVID-19があり、そして現在に至っている。そうした香港の「変化」の中を生きる市井の人々の様子を本作は描き出している。
舞台となっているのは「日泰食堂」。監督のシン氏もまた、この食堂に入り浸っていたと言う。お酒を覚えたのも、この「日泰食堂」だったそうだ。作品に描き出される店主の丈(ジョン)老人や常連客の肥美(フェイメイ)はとても魅力的で、世代を超えた彼らの交流がこの作品の持ち味である。フェイメイは干物のイカ焼きなどを売りながら家族や仲間とビールを飲んだり、煙草をふかしたり、賭け麻雀やトランプに興じている。描かれるのはごくごく普通の若者の暮らしであるが、テレビに映し出されるのは民主化を要求する反政府デモ隊の様子である。テレビニュースの映像からは、2019年頃の香港の熱気が伝わってくる。徐々にデモの参加者は増え、それに応じて警察もまた暴力的に振る舞うようになる。そしてデモ隊もまた、過激さを増していく。肥美はそのデモに参加し、丈老人は離島のテレビでデモ隊の様子を見つめている。食堂の人々を描きながら、そこに当時の香港のリアルが描き出される。
次に訪れるのがCOVID-19である。マスク生活が広がり、観光客は激減する。食堂を訪れる人たちは減少し、デモもまた勢いを失っていく。
プログラムに記された「監督のことば」によれば、「本作は、よくありがちな香港の物語ではない。私が描きたかったのは静かで温かく、漁村の精神にあふれた側面だ。心地よく、地に足が着いた日常生活が営まれている場所を描きたかった」とのことであり、そのねらいは十分達せられたと感じたが、やはりそこに生きる人々の眼を通じて描き出された香港のあり様が印象深かった。
上映後の質疑応答では、登場人物たちの今についての質問が出た。シン監督によれば、みな作品に描かれた世界とは異なる状況を生きているとのことである。ある人は、結婚して子どもを産み、またある人は移民した。島で仕事を続けている人もいる。店主の丈老人は手術をして、今ではイカが焼けなくなってしまったと言う。
ここに描かれているのは、シン監督にとっての在りし日の故郷である。だが、それと同時に、この作品からは香港の未来に向けた希望を感じることが出来た。
まだまだ紹介したい作品はあるが、紙幅の都合もあり、ここまでとしたい。こうして作品を紹介しながら、それぞれの作品の魅力のごく一部しか伝えられないことにもどかしさを覚えてしまう。だが、ドキュメンタリー映画が劇場で公開される機会は限られている。よって、最新のドキュメンタリー映画に関する情報を提供することにも、それなりの意味があるだろう。こうした報告がドキュメンタリー映画に触れるきっかけとなれば、喜ばしいことである。
宮嶋俊一(北海道大学大学院文学研究院教授)
注)立て看板以外の写真はすべて山形国際ドキュメンタリー映画祭提供。タイトル横のアイキャッチ画像はフランキー・シン監督作品『日泰食堂』(台湾、香港、フランス、2024年)