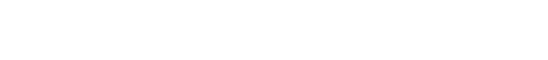2023年10月5日から12日にかけて、山形市内で「山形国際ドキュメンタリー映画祭2023」が開催された。2年に一度開催されてきた映画祭であるが、前回、2021年はオンライン開催となったため、対面での開会は4年ぶりとなる。本稿は、その参加報告である。
とはいえ、大規模な国際映画祭であり、そのすべてを網羅的に報告することは不可能である。そこで、インターナショナル・コンペティション部門(以下、「コンペ部門」と略記)で上映された作品を中心として、報告者なりの視点から今回の映画祭を振り返ってみたい。

三作品を対比する
コンペ部門には、テーマも手法も撮影地も様々な15作品がノミネートされた。その中で、手法的に興味深いと感じたのは、エキエム・バルビエ、ギレム・コース、カンタン・レルグアルク監督「ニッツ・アイランド」(フランス/2023)である。舞台となるのは仮想現実(VR)であるオンラインゲーム『DayZ』。それゆえ、スクリーンには、ずっとゲーム画面が映し出されることとなる。ゲーム配信を見ているような気分になる。映画製作のクルーはこのVR世界へと「潜入」し、そこで様々な人物に出会う。

ゲーム参加者はVR内での名前やキャラクターを持っているが、プレイ中にときおり「現実」が紛れ込む。(「現実」世界で)側にいる子どもが転んで泣き出してしまって席を離れたり、「現実」での職業について語り出したり。他方、VRならではの無法地帯も出現し、そこでは何の抵抗もなく殺人が行われたりもする。参加者の中には、現実が何なのかわからなくなってきたと呟く者も現れてくる。ゲームのやりすぎでリアルとVRの区別がつかなくなる、という言説は、今や古典的とも言える。だが、その「区別がつかなくなってしまいそうになる状況」を「リアル」に描き出し、観客にもその感覚を味合わせてくれるという意味で、本作は斬新である。
この作品と対照的であると思えたのがヴィタリー・マンスキー、イェウヘン・ティタレンコ監督「東部戦線」(ラトビア、ウクライナ、チェコ、アメリカ/2023)である。イェウヘン・ティタレンコ氏は、友人たちとともにボランティアの救護隊員としてウクライナ東部戦線に赴く。本作は、その時の様子を記録したものだ。

ウクライナの戦場の映像は、テレビのニュースやドキュメンタリー番組などでも目にすることが多い。かつてであれば、誰もが赴くことのできない戦場の映像はそれだけで貴重であった。だが、情報技術の発達により、今日では兵士たちが装着したウェアラブルカメラで撮影された戦場の映像ですら、テレビで放映されている。そうしたことを考えると、不可視の戦場映像などもう存在しないのではとすら思ってしまう。だが、本作を見て、そうではないことに気づかされる。あまりにもリアルな戦場の様子がスクリーンに映し出される。重傷を負った兵士を救急車両で移送する、その車内の緊迫感は筆舌に尽くしがたい。目の前の負傷者の命がみるみると失われていく、その様子が生々しく描き出される。あるいは、走行中、目の前を走る救急車両が地雷を踏んで爆発してしまい、乗っていた人々の肉片が、人間としての跡形もなく粉々に飛び散ってしまう。
もちろん、そのような悲惨な映像ばかりではない。野辺でくつろぎながら、仲間と戦争について語り合う様子は、のどかですらある。しかし、そのようなのどかな映像が映し出されるからこそ、最前線の映像は逆にますます厳しいものに感じられる。オンラインゲームのVRの世界で繰り広げられる「生と死」の世界と、ウクライナの戦場の最前線で繰り広げられる「生と死」の世界。いずれも同じドキュメンタリー映画の世界でありながら、対照的なリアリティがそこにある。
さて、ウクライナの映像という意味で、「東部戦線」と対照的であったのがマキシム・メルニク監督「三人の女たち」(ドイツ/2022)である。舞台は、ウクライナ、カルパチア山脈の麓にあるストゥジツヤ村。女性たちが多く暮らすこの村で、監督は大学院の修了制作のための作品作りを開始する。そして、そこに暮らす三人の女性たちが主たる登場人物となる。ひとりは、牛の飼育をする農家のハンナ、もうひとりは生物学者として節足動物の研究に勤しむネーリャ、三人目が郵便局員のマリーヤ。最初は撮影を厳しく拒んだハンナをはじめとして、撮影クルーと村人たちの交流が深まっていく様子がハートフルに描き出される。

これまでも、ドキュメンタリー映画の制作者はあくまで観察者にとどまるべきなのか、それとも作品に介入すべきなのか、といった議論は存在したが、本作では時間が経つにつれて制作者が積極的に前面に出て、村人と交流していく。そのほのぼのとした様子は、観ている者を温かい気持ちにさせる。
上映後の制作者との質疑応答の中で、最近では戦争にかり出される男性も増え、その結果としてますます村人の女性比率は高まったという話があった。田舎の村とは言え、やはり戦争の影響が皆無というわけにはいかない。だが、「三人の女たち」は、それだけではないウクライナの世界を私たちに見せてくれる作品であった。「ウクライナ」というと「戦争」という先入観で見てしまいがちであり、それは仕方ないことである。「東部戦線」はまさにそのような先入観に合致した作品であった。だが、それとは対照的とも言える世界がウクライナにも存在していることを本作は教えてくれた。
ドキュメンタリーの技法
今回のコンペ作品を見ていて感じたことのひとつは、ドキュメンタリー作品と言いいながらも、さまざまな「技法」を駆使した作品が多い、ということである。上述の「ニッツ・アイランド」のようにゲーム世界を舞台にする、というのもそのひとつであろう。イグナシオ・アグエロ監督「ある映画のための覚書」(チリ、フランス/2022)は、ドキュメンタリーでありながら、演者が物語を進める役回りを果たす。舞台は19世紀のチリ、先住民族マプチェの土地、アラウカニア。そこに鉄道建設の技師としてギュスターヴ・ヴェルニオリーが赴任する。かつてそこで起こった出来事を再現するために、彼の日記をもとにして、彼を演じる俳優がその足跡を辿るのである。もちろん、ドキュメンタリー映画において、過去をいかにして描くのか、というのは大きな問題だ。本作においても、そのための写真や証言が数多く登場する。だが、本作では、それに加えて、一種のストーリーテラーとして演者を登場させているのである。

上演後のティーチインで、アグエロ監督は、ドキュメンタリー映画の自由さを強調していた。素材を自由に使えるし、脚本に縛られることもない。その意味で、ドキュメンタリーはフィクションよりも自由だ、と彼は語った。そもそも、ドキュメンタリー映画の父と言われるロバート・フラハティの作品にも、ある意味「演技」が含まれていたのである。そう考えれば、ドキュメンタリーに演者が登場するということは、あえて特筆すべきことではないのかもしれない。
また、テオ・モントーヤ監督「アンヘル69」(コロンビア、ルーマニア、フランス、ドイツ/2022)では、作品の中でもう一つの映画制作の話が進んでいく。監督は、同世代のクイア・コミュニティの友人たちと、B級映画制作を企画する。その作品に出演を希望する応募者たちのインタビューの映像が次々と紹介されていく。そのひとり、その作品の主人公となるはずだった「Anhell69」というアカウント名を持つ友人が、薬物の過剰摂取で命を失う。彼だけではない。自殺やオーバードーズで多くの仲間たちが失われていく。結果的に、「Anhell69」は、仲間たちと一緒に作ることができなかった映画が作品内作品として紹介されると同時に、本作の全体がドラックや暴力、自殺といった問題に対する怒りを表明したドキュメンタリー映画として成立している。

上映後のロビー・トークで、監督はマジカルな力によってこの作品ができあがったと語っていた。またパンフレットの「監督のことば」には、「『アンヘル69』とはわれわれの思い出、われわれの記憶、死を前にしたわれわれの生を不滅化するものであり、おそらくは次世代や後の政権への警告でもあるのだろう」と記されている。フィクションと「事実」が重層的に交錯する中で、リアルな怒りや悲しみが浮かび上がってくる作品であった。
フィクションと「事実」という点で言うなら、ダミアン・マニヴェル監督「あの島」(フランス/2023)も興味深い作品である。舞台は「あの島」と呼ばれる島。主人公のローザは、翌日、島からモントリオールへと旅立つことになっている。そして、この島で同じ時を過ごした仲間たちとの最後のお別れパーティーが開かれる。そこに描かれる楽しさや寂しさ、そして恋愛感情……。だが、別の日、別の場で行われた、その場を演じるためのリハーサルの様子が映し出される。リハーサル?演技指導?あの島での出来事はすべてフィクションであったのか?だが、それにしては、リアルで、生々しい、赤裸々な感情の表出がそこにはあった。

この作品を見ながら「恋愛リアリティショー」を見ている気分になった。そこには一定の演出があり、ストーリーらしきものもある。しかし、「あの島」で、あの瞬間に生じたリアルが映像には映し出されている。それはフィクションであるとも「事実」であるとも言いがたい。本作もやはりドキュメンタリーとは何かを問い直す作品であると言える。
過去からの継承と革新
最後に、報告者がドキュメンタリー映画らしいと感じた作品をふたつ、紹介したい。まず、ダニエル・アイゼンバーグ監督「不安定な対象 2」(アメリカ/2022)である。この作品では、三つの工場・工房が紹介される。ひとつめは、ドイツ、ドゥーダシュタットにあるオットーボック社の義肢製造工場、二つめは南フランス、ミヨーにあるメゾン・ファーブルの高級革手袋縫製アトリエ、そして三つめはトルコ、イスタンブールとデュズジェにあるレアルコム社のジーンズ工場である。

義肢の製造では、大量生産で部品が作られていくものの、最終的には一人ひとりの障害にあわせた製品が作成されていく。高級革手袋縫製アトリエにおいては、何人もの職人が自分の技を生かす場としてそれぞれの工程を担いつつ、一つひとつの手袋が制作されていく様子が描き出される。そして最後は、多くの職人たち・労働者たちが工場で大量のジーンズを制作する様子が描かれる。
プログラムには「三つの工場での製造工程を『持続的観察』の手法によって徹底的に記録する実験的ドキュメンタリー」と記されているが、私にはむしろ既視感があった。定点観測・ノーナレーションと言えば、フレデリック・ワイズマンの作品が思い浮かぶ。本作にも、ワイズマン的なテイストが感じられたからである。だが、そこで描き出されるのは「労働」という概念であるとも言える。労働者がさまざまに身体を動かしてモノを生産している映像を見ながら、「労働」という(抽象的な)概念について身体的な理解を喚起するという点において、本作は新しいとも言えるだろう。
社会へと目を向ける作品が多かった中、イレーネ・M・ボレゴ監督「訪問、秘密の庭」(スペイン、ポルトガル/2022)は、そのタイトルが暗示するように、私的な作品である。監督は、叔母を撮影の対象に据える。彼女の叔母、イサベル・サンタロはスペインの有名な画家であり、前衛芸術に参画した女性たちの最初の世代に属するとされるが、1980年代以降、芸術の表舞台からは姿を消す。仲間との付き合いが疎遠になったばかりでなく、彼女は家族との付き合いも断っている。そんな孤高の元芸術家である叔母の姿を監督は追い、彼女がなぜ芸術の世界を離れ、孤高に生きようとするのか、その謎を探っていく。極私的な秘密を探っていく、という意味では、河瀬直美の作品を思い起こした。だが、本作の制作を通じて、ボレゴ監督は叔母であり芸術家であるイサベル・サンタロを自分と同じ芸術家として理解していくことになる。それは私的な「秘密」の探求でありながらも、そこで探られ、見出されていく芸術や人生というものに、ある種の普遍性が感じられるのである。

おわりに
本稿で紹介できたのは、映画祭のごく一部に過ぎない。コンペ部門以外にも、「アジア千波万波」や「日本プログラム」では興味深い作品がいくつも上映されていた。また、「野田真吉特集:モノと生の祝祭」は、多くの観客を集めていた。
最後に、久しぶりの対面実施に参加し、気がついたことを指摘しておきたい。それは、街中で聴かれる数々の「映画評」である。入場を待つ行列や休憩時間のロビーなどで、「どの作品がよかったか?」という評があちらこちらで囁かれる。そして、その囁きに促されるように、人々がスクリーンへと足を運ぶ。そして、そこから次の囁きが生まれ、そうした囁きが映画祭における作品の評価ともなっていく。これが、本映画祭(に限らないかもしれないが、とりわけ本映画祭)の特徴であった。オンライン開催では、このような「口コミ」が存在する場がなかった。街全体が映画館となってしまったかのようなこの感覚を久しぶりに味わえたことを心から喜びたい。
宮嶋俊一(北海道大学大学院文学研究院教授)
注)立て看板以外の写真はすべて山形国際ドキュメンタリー映画祭提供。タイトル横のアイキャッチ画像は章梦奇(ジャン・モンチー)監督「自画像:47KM 2020」(中国/2023)。