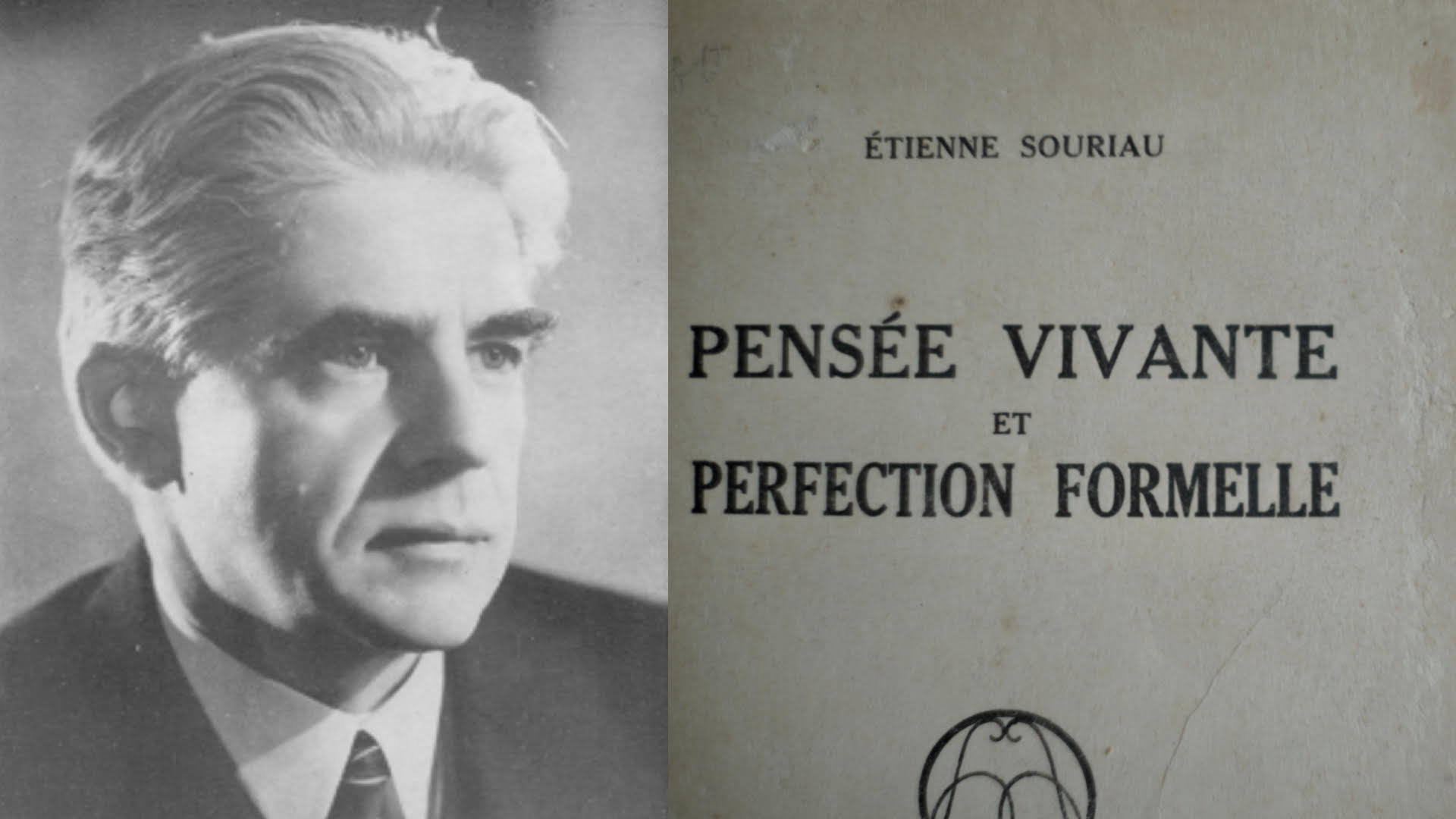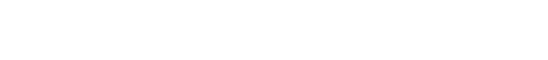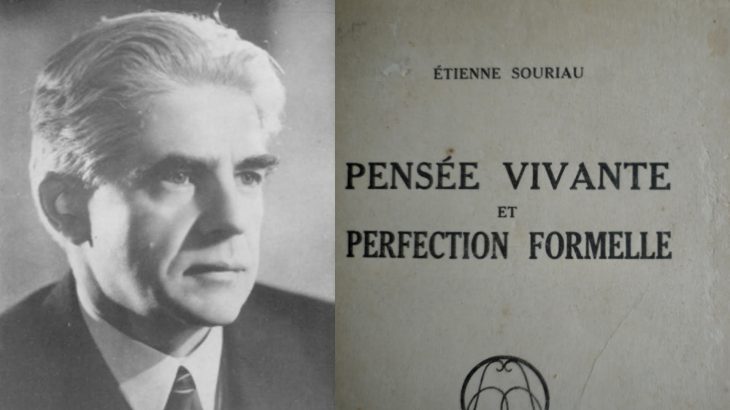はじめに
2022年4月、ダヴィッド・ラプジャード(堀千晶訳)『ちいさな生存の美学』(月曜社)が、ともすればそれこそひっそりと出版された。原著者[i]ラプジャード(David Lapoujade,1964-)は、「ウィリアムズ・ジェイムズを中心としたプラグマティズム研究、および精緻なドゥルーズ研究をおこなうフランスの哲学者」[ii]である。
「ドゥルーズ最良の継承者が忘れられた美学者スーリオを呼び戻しながら、新たな生と実存の様式を創建する」と謳う帯文のとおり、本書は一つの「エティエンヌ・スーリオ論であり」、「小著ながらスーリオとラプジャードのエッセンスが詰まった書物である」と訳者の堀は「解説」[iii]で紹介する。
「忘れられた美学者」というにわかには歓迎できない呼称には、前提がある。スーリオ(Étienne Souriau, 1892-1979)は、20世紀フランスの哲学者/美学者であり、そのアカデミック・キャリアーに比して、哲学、美学史上への直接的な影響は乏しく、孤高のひと、というたたずまいであった[iv]。
堀も指摘するように、2009年に変化がおとずれる。1943年のスーリオの著作『さまざまなエグジスタンス・モード』[v]が再刊された。のみならず、スタンジェール(Isabelle Stangers,1949-)とラトゥール(Bruno Latour,1947-2022)の序文が付された。その冒頭「忘れられた哲学者の忘れられた書物」[vi]をもじって、帯文のフレイズは案出されている。
ラトゥールは、「多元モードであることplurimodalité」[vii]にまつわるスーリオの試みが、自身がおこなってきた実存モードの探求を先どりしていたゆえに驚嘆したと言う[viii]。アクターネットワーク理論で名を馳せたラトゥールによる評価は学問史上の再評価となり、2010年代には、ブリュッセル自由大学の紀要[ix]、フランス美学会誌[x]で特集が組まれた。
ラプジャードの論考も、そうした流れの中にある[xi]。訳書に付された堀による充実した解説は、ラプジャードが見たスーリオを起点に、両者の思考の親しさをあざやかに照らし出している。それに対して本論は、ラプジャードのスーリオ解釈の妥当性を見きわめることも含め、スーリオとラプジャードとのコントラストを描きたい。
1 スーリオ――したたかな改革者
ⅰ.権利の要求
今道友信(1922-2012年)は、著書『美について』(1973年)[xii]に、スーリオがなぜ美学を志したのか、本人から思い出話をきかせてもらった、と記している。スーリオは今道を「自宅の書斎」に招き、「しみじみと別れの一夕を過ごし」つつ、「まだだれにもあまり話したことはないが」と前置きしつつ、こう言ったそうだ。
私は卒業の口述試験のときに、デュルケーム、ブレイエ、などの多くの教授たちから、君は美学をするという噂だが、そんなものは哲学かね、と聞かれた。そのとき私は躊躇しながら、年来考えていたことを答えた。人間の精神の最高の客観的所産は、科学と芸術であると思う。しかし、それらの所産は、いずれも自己自身についての反省を持っていない。哲学はソクラテスの昔以来、人間の自己自身に関する反省である。私は人間精神の最高の所産を反省することによって、人間の可能性に関する最高の反省ができると思う。したがって、従来は科学の反省としての新カント派の哲学しかなかったから、今、自分は芸術を自己反省することによって人間精神の内的な反省を可能にしたいと思う。――(略)――ここに哲学としての美学、また芸術の真の哲学的思索ということが問題として可能になるのではないかと思う、と。
今道友信『美について』 p.168
いならぶ教授陣の失笑と、若き美学者の情熱のたぎりがきこえてきそうなエピソードである。ラプジャードが言うように、もしスーリオが「ちいさな生存の美学」を志向したのだとすれば、スーリオ自身は、まずなによりも「芸術」、あるいは「芸術の哲学」すなわち「美学」、を志向する自らの思考という弱者の権利を要求したと言える。
ただしこのたくらみは、「大学外で人気をえていたベルグソン」[xiii]への対抗意識を孕んでいた。というのもスーリオは自らの思考を、アカデミックな「哲学」のどまんなかにうち建てんとしたからだ。この点で、スーリオが「偽りの豊穣さ」[xiv]を忌避したとするラプジャードの見解は、スーリオの出発点での方向づけをきっちりと押さえている。
つまりスーリオは、「生vie」、そして「芸術art」のすがたは、その「深みprofondeur」、すなわち、とらえられなさの内にあるのだとする考えを、魅惑的と認めつつも、「逃げfuite」だと断罪しさえした[xv]。はたして、美学なんぞが哲学かね、と失笑をくらった若き美学者自身は、逃げなかった。
美学はフォルムの学である。フォルムはものの本質であり、人間のあらゆる認識に介在する。たほうで芸術は、フォルムをあつかうエキスパートだ。だから哲学は人間を知るために、美学を擁して芸術を知るべきだ。「フォルム」を媒介にして哲学と芸術を結びつけることでスーリオは、美学に、まっとうな一哲学という、まさにかたちを与えた。
はたしてスーリオは、フランス美学会、国際美学会などを通して、実質上芸術の学たる美学、の制度化を果たす。既存の権威(権力)構造をひっくり返さずに、その内側で、弱者の権利を要求していく。その点でスーリオは、革命家révolutionnaireではなく、改革者réformateurであったと言える。
ⅱ.不遇と復権
ただし、改革者はそのじつ、革命家よりもしたたかである。スーリオは、美学がさまざまな学問のあいだparmiに遍在するという将来を予測した。生のパラディグマを芸術としつつ、哲学それ自体をも芸術になぞらえつつ、ひそかに、哲学を美学に包摂しようというプログラムを遂行していた。
20世フランスの哲学はしばしば、芸術に学び、ひいては芸術にあこがれた、という意味では、スーリオの方向づけに沿うかたちで展開したとも言える。こうして、哲学と美学とを束ねて時代を牽引するかに見えたスーリオの思索自体はしかし、皮肉にも、哲学においても、美学においても、思想史上の画期をなすにはいたらなかった。
1973年のド・ヴィトリ=モブレイによる、はじめてのスーリオのモノグラフィー『エティエンヌ・スーリオのコスモロジー思考』(1974年)[xvi]もまた、そうした情況をふまえてのものであった。ド・ヴィトリ=モブレイは別稿「孤高の存在論」(1980年)で、スーリオ流のぼやき、にもきこえることばを引いている。
哲学においては、メインストリートの外を歩む者は、特定の世代の最大多数によって、不条理とみなされ、したがって、権威をもたないだけでなく、ほとんど時代遅れとみなされる。じっさいには、メインストリートの外を歩む者が進んでいた場合でも。
スーリオ「芸術と哲学」(1954年) p.15[xvii]
日本では、今道が先のように、たびたび積極的にスーリオを紹介した[xviii]ことはさいわいであったと言える。1980年代に、今道に連なるしかたで谷川渥と橋本典子が論考を残した。谷川は初期スーリオの緻密かつ批判的な分析をおこない[xix]、橋本は、今道編纂の『西洋美学のエッセンス』[xx]で、概説ながらも全体像をまとめてくれている。
ぼく自身は1999年に、それこそ『西洋美学のエッセンス』でスーリオの項を見つけ、卒業論文のテーマに決めた。「芸術とはなにか」を真正面から問う、意外と美学者にはまれなそのスタンスに、素直に共鳴したからだった。主著の和訳もなく、専門研究の蓄積もないので、やり甲斐はあった。
しかし、その後2000年代に進めていったスーリオ研究の過程で、学会発表、論文査読のたびに、諸先輩がたからいただいた(浴びせられた)のは、まさに、スーリオの思索そのものを「そんなもの」あつかいする反応であった。「なんでいまさらスーリオなのか」、「その現代的意義はなにか」、「現代アートに対して有効なのか」などなど。
やがて2010年にぼくは、ド・ヴィトリ=モブレイにつぐモノグラフィを出す。そこでぼくもやはり、スーリオ研究は「どのみち擁護、か救済のかたちをとらざるをえない」[xxi]とぼやいている。スタンジェール/ラトゥールの「忘れられた哲学者」という句もまた、スーリオ(研究)が抱き続けてきたルサンチマンのリフレインとなって響いたわけだ。
が、今度ばかりは事情がちがった。そのリフレインが、ラトゥールという「メインストリート」の住人のお墨つきでもあったからだ。「忘れられた」は反語に転じ、風向きは変わりはじめた。はたして、堀千晶の言う「復権」があいなり、ラプジャードの筆も起こされることになる。
2 ラブジャード――ささやかな革命家[xxii]
ⅰ.アナフォラ vs エピフォラ
こうしたスーリオをとりまく情況と、スーリオの中心概念である「創建instauration」[xxiii]の内容を重ねあわせれば、スーリオの思考が、おのずとフラクタル構造を描くことがわかる。創建は、「創造」のオルタナティヴという位置づけでスーリオが哲学に導入したことばで、うち建てる/建てなおす、という両義性をもつ。
作品をうち建てることは一つの完成を旨とする。ただし、完成は過程を要する。作者の一手が作品を「修正」し、修正された作品に応じてつぎの手が打たれる。つまりうち建てることは、建てなおしの連鎖だ。とすると、作品をうち建てることの全体が、先行する世界の建てなおしでもある。最初の一手は、世界の修正に乗りだすことだからだ。
したがって第一に、創建を論じるスーリオの思考自体が、連鎖し、ある哲学をうち建てる。同時にそれは、ある美学をうち建てることでもある。第二にスーリオは、自らの哲学、美学をうち建てることで、先行する哲学を建てなおし、先行する美学を建てなおしたことにもなる。
だとすれば、フラクタルはさらに拡張する。つまりスーリオ哲学に触れたぼくらが、自らの思考を建てなおしつつうち建てることで、スーリオ哲学の建てなおしを果たすことができる[xxiv]。ラプジャードが本書ではかるのも、そうした思考のうち建て/建てなおしだととらえることができる。
堀も示唆しているとおり、ラプジャードの念頭にあるテーマの一つは、スーリオが一見無関心を通した「現代芸術」に対して、スーリオの論を適用することだった。このテーマは、ぼく自身の課題でもあった。ラプジャードがいかにしてスーリオを「救済」するのか、その手ぎわを見てみよう。
その試みにさいしてラプジャードがスーリオに見出した手がかりはいくつかある。ここでは、結論部で導入される「アナフォラanaphore」をとりあげたい。アナフォラということばは、レトリック用語の一つで、頭語反復を意味する。スーリオはこれを、創建の過程を表現するために使った。
創建の過程は、すでに見たとおり、建てなおしの連鎖である。当の建てなおしの内実をこそスーリオは、アナフォラということばによって指し示す。すなわち建てなおしは、前進promotionしながらも、くりかえしはじめるrecommencementというかたちを描く。スーリオにとって作品はエグジスタンス[xxv]であり、それ自身であることを旨とするからだ。
エグジスタンスたる作品は、たえずそれが同じ作品であるように、たえずつくりなおされなければならない。あるものの完全なフォルム(本質)とは、「自分と同じようなものであるものに戻るフォルム」[xxvi]であるとスーリオは言う。作品は、厳密に言えば、瞬間ごとに存在しはじめなければならないわけだ。
だからこそスーリオは、アナフォラということばをエピフォラepistrophèに対比させている[xxvii]。エピフォラは、レトリック用語では、頭語反復と対称をなす「脚語反復」であり、新プラトン主義、おそらくプロクロス(Proklos, 412-485)の概念で、超越者である一者への回帰、帰還を意味する。
スーリオは、アナフォラを採用することの内で、すくなくとも単純なエピフォラを忌避していることになるだろう。かりに存在がエピフォラのかたちをとれば、個別性を旨とするはずのエグジスタンスたちは、同じ一者に溶解してしまうからだ。そうしたエピフォラの存在論は、たとえば、下記のとおり定式化されるであろう。
aは、Xである。
bは、Xである。
cは、Xである。
dは、…以下同様。
「Xである」という脚語を反復する、存在の詩。ここでは、いかなる個別の存在、すなわちいかなるエグジスタンスa、b、cも、超越者であるX(大文字)に帰着し、そこに包摂されてしまう。それに対してアナフォラの存在論がありえるとすれば、こう記述できるであろう。
xは、Aである。
xは、Bである。
xは、Cである。
xは、…以下同様。
「xは」という頭語を反復する、存在の詩。あるエグジスタンスであるx(小文字)は、ある瞬間にAである(本質Aを備える)が、つぎの瞬間にはBである。そう言うときすでに、Aである瞬間からBである瞬間へは「断続の連続」[xxviii]が成立しており、xはそのつど、x自身へと戻っていることになる。つまりxは、くりかえし存在しはじめるわけだ。
エグジスタンスは、自分自身へ戻ることよってこそ前進するという、逆説の途を行く。その動きに巻きこまれる者が、作者となる。作者は、あるものが端的にそのものであることができるように手を貸す。将来に向かって後悔し、ノスタルジー[xxix]を感じつつ、将来をとり戻すべく、はじまりという終わりへと向かう。
ⅱ.アナフォラ vs カタフォラ
たほうでラプジャードは、アナフォラanaphoreをカタフォラcataphoreと対比させる。このばあい、レトリックというよりは、文法用語という位置づけで、両者には、「前方照応」と「後方照応」という意味をあてがうことができる。ラプジャードはこのペアー概念を、芸術史のコンテクストに織りこもうとする。
スーリオのテーマは、個々の存在(作品)の自律化であった。それは19世紀後半から20世紀前半に進んだ「芸術」の自律化に沿ってもいた。スーリオは、自身のキーワードである「フォルム」は芸術批評用語ではない、と注記している[xxx]。それでも、フォルムに着目する発想は、同時代の芸術論で展開されるフォーマリズムと軌を一にしていた。
それはスーリオが、E.ハンスリック(1825-1904年)をひきあいに出すことからもわかる。スーリオにとって芸術は、いかなる他律的な原理も必要としない。感情カテゴリーや美を芸術の本質規定に用いることを、スーリオは徹底して避けた。ゆえに芸術は、客観宇宙、主観宇宙から独立した「芸術宇宙univers artistique」を構成する[xxxi]。
スーリオにとって芸術が一つの宇宙をなす条件は、当の宇宙に内在する法則の存在である。そうした芸術宇宙のありかたは芸術の一ジャンルである音楽をモデルにしている。ここでの音楽は、十二音階と調性を基軸とする西洋音楽である。たとえば芸術宇宙の素材であるクオリアqualia(純粋な感覚質)は、音階に類比するグラデイションgammeを含む。
そうした前提に立ちスーリオは、たとえばH.マティス(1869-1954年)、P.ピカソ(1881-1973年)、R.ド・ラ・フレネー(1885-1925年)、J.ミロ(1893-1983年)ら「音楽主義者musicalist」を評価する[xxxii]。音楽は絵画にくらべ、ものを「再現する」要素が希薄で、そのぶん自律性と自己組織化において先進的である、というわけだ。
フォーマリズムは、芸術、あるいは、それぞれの芸術ジャンルの自律原理を追究するゆえに、芸術の「モダニズム」を駆動させる一つの動機ともなった。その行き着く先に「抽象の限界」、たとえばR.ラウシェンバーグ(1925-2008年)の「ホワイトペインティング」(1951年)や、J.ケージ(1912-1992年)の《4分33秒》(1952年)が現れる。
抽象的な限界とは、ひとつの芸術の窮極的な可能性を表象するものであり、かつまた、ひとつの芸術に本質を設定し、それと異質なものを分離する壁を打ち立てるものである。だが限界が具体的なものになるとき、もう限界は同じもの同士を分離したりはしない。というかむしろ、限界の機能はもはや分離することではなくなり、逆に諸芸術を、想定される各々の本質とは異質の諸要素と交流させるようになるのである。絵画が絵画でないものと、文学が文学でないものと、演劇が演劇でないものと、ダンスがダンスでないものと交流することこそ、それぞれの芸術が駆動するための条件であると述べることは、いまや常套句といってよい。芸術は本質的に不純なものとなるのだ。
ラプジャード『ちいさな生存の美学』2022(原書2017) p.132
「ホワイトペインティング」や《4分33秒》が、抽象化の極致でありながら、なおかつ具体的な作品であることの意味を考えれば、むしろ「限界」は、ジャンルを閉じるのではなく、開き、解体する。はたして「横断性」、「リサイクル」、「ハイブリッド」、「マルチメディア」[xxxiii]に彩られ、芸術は、「不純」であることを旨とする。
こうして限界点は転換点となり、到達点は出発点に読みかえられる。この主張は、たとえば外山紀久子[xxxiv]が言う、「内向きのモダニズム」と「外向きのモダニズム」という図式に沿う。芸術のモダニズムは、自律性を求めて「芸術(ジャンル)」の内側へと純粋化していくのと同時に、芸術の外へと自らを解体しつつ解放する。
この二つのヴェクトルは、芸術化と「反芸術」[xxxv]化と整理することもできる。したがって、到達点から出発点への読みかえには、ラプジャードによる最もアクロバティックなスーリオ美学の読みかえが、重ねられている。つまり、『ちいさな生存の美学』はそのウルトラCにおいて、スーリオ美学を、反芸術の美学へ導こうとしている。
たしかにスーリオは、「反芸術」をけっして語らなかった。しかし、先の外山の図式によれば、芸術化は反芸術化と同時に進んでいた。瞬間ごとの「反エグジスタンスcontre-existence」[xxxvi]に対峙するという点で、スーリオの芸術もまた、反芸術を含んでいる。「でないもの」に、たえずさらされている。
それは転落のようなものだが、そこから立ちあがる必要はもうないだろう。そもそも立ちあがることなどできるだろうか。アナフォラ(anaphore)は文字どおり、カタストロフィ的ないしカタフォラ的(cataphorique)なものとなった(anaが下方から上方への運動を、kataが逆向きの運動を指すという意味において)。
ラプジャード『ちいさな生存の美学』p.133,l.14
「ホワイトペインティング」や『4分33秒』は、フォルムを欠くがゆえに、かえって「超高感度hypersensible」[xxxvii]なしかたで、形成formalisationをうながす。作品に立ち会う者は、知覚のいわば閾値を下げることで、よりささやかな、それゆえに、より潜在性の高いエグジスタンスをすくいとることができるというわけだ。
ⅲ. 脱権威化へ
スーリオはいっぽうで、前進あるいは上昇の修行に向かうしたたかな存在を要請する。たほうで、瞬間に起ちあがるささやかな存在をすくいあげる。ラプジャードは、後者の面をクローズ・アップすれば、スーリオを、いわばポストモダンに生かすことができると発想したのだろう。
しかし、アナフォラはそもそも、エピフォラと対比をなす。前進のヴェクトルだけではなく、反復性を宿す。反復の内実は、そのたびに自身「でないもの」となることでそれ自身でありなおすことである。「反芸術の再芸術化」[xxxviii]になぞらえられる動きによって、スーリオの芸術が含む反芸術は、つねにすでに乗りこえられていることになる。
スーリオは、こうした他者化に連なる自己化の機構を、超エグジスタンス、あるいは超越モードというしかたで設定した[xxxix]。超エグジスタンスは、エグジスタンスがいかなるかたちになるべきかを問いかけることで、エグジスタンスを試し、導く。このとき、エグジスタンスが反エグジスタンスをいかに乗りこえるか、そのかたちが問われている。
はたして反エグジスタンスの克服のかたちこそが、エグジスタンスのまさにフォルムとなる。そして、エグジスタンスが体現するフォルム=応答によってこそ、逆に超エグジスタンスは、その存在を保証される。つまり、応答することによって、そもそもの問いかけのかたちが明らかになるとも言える。
こうしてエグジスタンスが超エグジスタンスとともにあるかぎり、創建はしたたかさをゆずることはない。スーリオは、制作プロセスのなかのつぎの一手に対峙する場面を、「スフィンクスの問い」にたとえた。不正解は死、つまり存在の霧散を意味する。こうして、アナフォリクな前進である創建は、失敗するという危険をたえずはらんでいる。
すくいあげた瞬間のフォルムは、連鎖されなければならない。存在のささやかさとしたたかさは表裏一体であり、切り離せない。そこでラプジャードが採った方策は、いわば微分だ。ある瞬間へとフォーカスすることで、「最小のものから無へと向かう」[xl]プロセスにわけ入る。起ちあがらんとする存在を、アナフォラのサイクルに乗せないわけだ。
ラプジャードが行くのは、「失敗」を回避する途であると言える。はなから失敗しきったカタフォラの地に身を置いたうえで、ささやかなアナフォラの発芽に立ちあうというのが、ラプジャードの図式であろう。対してスーリオは、たえず襲ってくるカタフォラの危機にカウンターを浴びせることでアナフォラを生きていく。
が、ラプジャードによって、もうひとつの危険が回避されている。それは、ラプジャードが言うところの「権利の要求」が、権威の獲得に転化してしまうという危険だ。ともすればそれこそが、冒頭で概観した、スーリオ美学、あるいはスーリオの生それ自体の創建が陥った危険であった。
アカデミーでの権利の獲得をなかば目的にするとき、スーリオのささやかな視点は、したがって「生き生きした生」は、閉じた権威に覆われてしまったのではないか。たほうでラプジャードが提示する、微分にとどまる視点(微細化原理amoindrissement)は、いわば、脱権威化des-autorisationを生きることだ。
だとすれば、ラプジャードの論考は、「復権」に対する警句となるとも言える。つまり「メインストリート」で陽の目を浴びたいまこそ、ぼくらはスーリオの著作のあちこちに散在する、あるいは、スーリオをとりまく、ささやかなエグジスタンスを見のがさないように、感受性を研ぎすませるべきであろう。
おわりに
変わることでかえって変わらぬ自己を強化するという、ダイナミックではあれ一つの本質主義をスーリオは採った。それは、ひとは放っておけば非自己化すると考えたからではないか。二度の大戦にすくなからず生を翻弄されたであろうスーリオにとって、自己であることの輝きを放ち続ける傑作群は、生きる糧であり、確固たる参照点だった。
他者性たる現実にもまれ、他者になりつつ、それでも瞬間ごとに自己でありなおすこと。異なることによって同じであること。「どうしようもなさ」に抗い、自己であり続ける生きかたこそが、スーリオの出発点での問題であったことは、最初の著作の記述が示している。
生きる者とは、自分の夢の形式を、実体の流れにもまれながらもなんとか維持することにより、想像物が永遠に霧散するのを、つねに最も客観性豊かなある種の統合よって、なんとか埋めあわせる者である。――危険なのは、意志がわかないことではなく、願いをかなえないこと、つい願いをあきらめてしまうことである。
スーリオ『生き生きとした思考とフォルムの完全』(1952年/初版1925年) p.247[xli]
[i] 原書は、Les Existences Moindres,Les Éditions de Minuit, 2017
[ii] ダヴィッド・ラプジャード(堀千晶訳)『ちいさな生存の美学』月曜社 2022年 p.140
[iii] 訳者解説「反時代的な美学のために」(ラプジャード(堀)『ちいさな生存の美学』2022 pp.140-172)。
[iv] スーリオが後続の流れをつくらなかった理由にかんしては、下記のド・ヴィトリィ=モブレイの著作をふまえた拙著が、考察している。
Luce de Vitry-Maubrey: La pensée cosmologique d’Étienne Souriau, Klincksieck, Paris, 1974、春木有亮『実在のノスタルジー――スーリオ美学の根本問題』(行路社 2010年)を参照。
[v] Étienne Souriau: Les différents modes d’existence, Presses universitaires de France, Paris, 1943.
[vi] Voici le livre oublié d’un philosophe oublié.
Isabelle Stengers et Bruno Latour :Le Sphinx de L’Œuvre, Étienne Souriau: Les Différents Modes d’Existence, suivi de L’Œuvre À Faire, pésentation de Isabelle Stengers et Bruno Latour, Métaphysiques, Presses universitaires de France, Paris, 2009, p.1
[vii] Souriau: Les différents modes d’existence, 2009, p.66
[viii] Souriau: Les différents modes d’existence, 2009, p.1
[ix] Coordination Scientifique Fleur Courtois-l’Heureux et Aline Wiame :Étienne Souriau-Une Ontologie De l’Instauration, Annales de l’Institut de philosophie et de sciences morales, Université libre de Bruxelles,Vrin,2015,Paris
[x] Nouvelle Revue d’Esthétique 2017/1 n° 19 ,Presses Universitaires de France, 2017
[xi] 堀によれば、ラプジャードの2011年の論文を単行本にしたものである。
[xii] 今道友信『美について』 講談社 1973年 p.167-169
[xiii] 今道『美について』1973 p.168
[xiv] ラプジャード(堀)『ちいさな生存の美学』2022 p.18
[xv] 春木『実在のノスタルジー』2010 pp.24-26, pp.86-87
[xvi] Luce de Vitry-Maubrey: La Pensée Cosmologique d’Étienne Souriau, Klincksieck, Paris, 1974
[xvii] Étienne Souriau : « Art et Philosophie », Revue philosophique n° 1,1954,p.15
(Luce de Vitry-Maubrey :Une Ontologie Solitaire, L’art instaurateur, Revue d’esthétique 1980/3-4, Union Générale d’Edition, 1980 p.228)
[xviii] 『講座 美学』第1・3・5巻(今道友信編集、東京大学出版会 1984、1988年)にも、スーリオへの言及がある。また、船木治義「アランの芸術論とスーリオの美学――芸術に於けるノエーシス的性格」(『哲学論叢』第15号 東京教育大学哲学会 1953年)は、最初期の、日本でのスーリオの紹介である。
[xix] 谷川渥『構造と解釈』 ぷろぱあ叢書 世界書院 1984年
[xx] 『ぺりかん・エッセンス・シリーズ 西洋美学のエッセンス 西洋美学理論の歴史と展開』今道友信編、ぺりかん社、1987年 pp.297-314
[xxi] 春木『実在のノスタルジー』2010 p.212
[xxii] 「ささやか」という形容動詞は、行為や行為の結果を修飾する。しかしながらここでは、行為の主体を修飾する。すなわち、創建という行為において、行為の主体と行為の結果が一体となるというスーリオの考えになぞらえつつ、破格かつポエティックな用法を採った。
[xxiii] ここでは、instaurationの日本語訳に、今道が創案した「創建」を踏襲つつあてる。が、「うち建てなおし」という訳語もありえるであろう。また、建築のコンテクストでのinstauratioの意味にかんしては、岡北一孝「De re aedificatoria における第十書の位置づけと「修復」«instaurare»の意味」(博士学位請求論文 京都工芸繊維大学 2013年)がくわしく論じている。
[xxiv] スーリオにとっては、受けつぐこととは、つくりなおすことである。じっさいわれわれがこうしてスーリオを読むねらいがスーリオを「つくりなおす」ことだったのだとすれば、それは、つくりなおしたものを、保存するためではなく、つくりなおされ続けるようにするためである。
Stengers et Latour :Le Sphinx de L’Œuvre,Souriau: Les différents modes d’existence, 2009, p.74
[xxv] 春木『実在のノスタルジー』2010ほかでは、スーリオが使うexistenceを「実在」と訳してきたが、『ちいさな生存の美学』の訳者堀は、「実存」と訳す。本論では、混乱を避けるために、エグジスタンスと訳す。existenceを「実在」と訳す理由は、春木『実在のノスタルジー』2010, pp.146-147(注1)を参照。
[xxvi] Étienne Souriau: Pensée Vivante et Perfection Formelle, Presses Universitaires de France, Paris, 1952(1ère édition 1925) p.XVIII,l.10
[xxvii] 春木『実在のノスタルジー』2010, p.123(注5、注7)を参照。
[xxviii] 春木『実在のノスタルジー』2010, p.37参照。
[xxix] 春木『実在のノスタルジー』2010, pp.195-210、あるいは、春木有亮「将来への帰還、過去への投企―エチエンヌ・スーリオの、創造する「ノスタルジー」 」(『人間科学研究』12号 北見工業大学 2016年 pp.49-66)を参照。
[xxx] スーリオは『美学の将来』(Étienne Souriau: L’avenir de l’esthétique essai sur l’objet d’une science naissante, Paris Libraire Félix Alcan,Paris, 1929, p.9)で、「フォルム」を「素材matière」と対比させるのであって、「内容fond」や「中身contenu」と対比させるのではないと言う。
[xxxi] Étienne Souriau: La correspondance des arts, Ernest Flammarion, Paris, 1947, p.242
[xxxii] Étienne Souriau: La correspondance des arts, Ernest Flammarion, Paris, 1947, p.93
[xxxiii] ラプジャード『ちいさな生存の美学』2022(2017) pp.132-133
[xxxiv] 外山紀久子『帰宅しない放蕩娘 舞踊のモダニズムとポストモダニズム』 勁草書房 1999年
[xxxv] 外山『帰宅しない放蕩娘』1999、 p.V、p.65、p.68、p.69
[xxxvi] 春木『実在のノスタルジー』2010、p.107、p.208。ただし同書では、contre-existenceを「対実在」と訳している。
[xxxvii] ラプジャード『ちいさな生存の美学』2022(2017)p.129、 p.133、ラウシェンバーグのことばをラプジャードが引用。
[xxxviii] 外山『帰宅しない放蕩娘』1999、 p.65
[xxxix] 春木『実在のノスタルジー』2010, pp.139-141、pp.185-187、pp.197-206を参照。
[xl] ラプジャード『ちいさな生存の美学』2022、p.126
[xli] Étienne Souriau: Pensée Vivante et Perfection Formelle, Presses Universitaires de France, Paris, 1952(1ère édition 1925) p.274