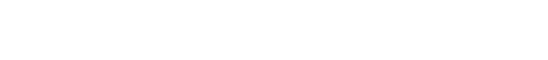0.本展覧会について

新宿駅から地下鉄とバスで40分ほど、府中駅周辺の喧騒からは少し離れた閑静な公園の中に府中美術館はある。筆者がここに足を運んだのは、『諏訪敦 眼窩裏の火事』(2022年12月17日〜2023年2月26日)に訪れるためだ。
諏訪敦は北海道出身の油彩画家で、現在は東京周辺を活動拠点としている。彼の作品は一見写実的に見えるが、徹底した取材と観察に基づき、記憶や想像力、知識を駆使して生み出されており、「写実」という表現では到底表し得ない次元を内包している。同展は諏訪のこれまでの画業を3つのテーマに即してとらえつつ、それぞれにおける画家の思索や制作過程を辿るものとなっている。展覧会は3つの章によって構成されている。「第1章 棄民」では諏訪敦の家族史をテーマにしている。続いて「第2章 静物画について」では、静物画に対する様々な試みと成果に焦点を当てている。展示の最後を占める「第3章 わたしたちはふたたびであう」では諏訪の代表的な作品ジャンルといえる肖像画が展示の中心となる。この3章の空間は2つに分かれている。うち片方は肖像画の展示空間であり、もう一つの空間は肖像画の中でも特に舞踏家・大野一雄氏を描くプロジェクト、そしてパフォーマー・川口隆夫と共に「札幌国際芸術祭2020(以下、SIAF2020)」に向けて構想していたプロジェクトを引き継いだ新作の展示である。
この展覧会では、画家が抱いていた絵画そのものの空間と作品の外部にある展示空間との関係について問い直す展示となっている。展示のサポートを行う美術館や技術者の支援も厚く、一作家の個展に止まらない挑戦的な展覧会となった。本評では作品と展示方法からこの展覧会を総覧し、展覧会の意義について論じていきたい。
1.「第1章 棄民」―家族の物語―
最初の展示室は、油彩画の《father》(1996)[1](図1画面左手前)をはじめとする諏訪の父の姿を描いた作品群から始まり、難民収容所で亡くなった諏訪の祖母の記録と取材を元に描かれた《HARBIN 1945 WINTER》(以下、《HARBIN》)(2015-16)[2]を中心とした展示が行われている。画家の父・息子の観察を通して得た表情や骨格の様子は《HARBIN》で描かれる亡くなった叔母を描くとき、資料や写真だけでなく家族の表情を大いに参考にしたという。まさに諏訪が「家族の物語」であると語った通り、家族の旅の軌跡であるとも言える。
入場口から右手に進むと、ICUのベッドに横たわる父を描いた油彩作品《father》(1996)、その隣には息を引き取った父の顔を観察しながら描いた2枚のスケッチ、そして諏訪の実子の寝顔のスケッチが並ぶ。通路の反対側には、後述する諏訪のハルビンへの取材旅行の際に描いた、祖父が少年だった頃のスケッチや日本人学校を描いた作品《日本人は樹を植えた》(2016)[3]がある。その隣には室内で横たわったまま宙に浮かんでいる女性を描いた油彩画《Untitled(未完成/Unfinished)》(2017/2021-2022)[4]が並ぶ。横たわる2人の男女は対になっているように見え、旅路の始まりを思わせる。歩みを部屋の奥へと進めていくと、諏訪が取材旅行で目にした哈爾浜の建物や取材資料、それらをもとにした習作が並ぶ。部屋の奥には大画面の《棄民》(2011-13)[5]が我々を見下ろすように掛けられている。突き当たりを右に進むと、《HARBIN》制作過程の記録写真を写したスライドアニメーションが進行している。スライドショーの裏手へ向かうと《HARBIN》が私たちの眼前に現れる。

諏訪が《HARBIN》を描く契機になったのは父だったという[6]。諏訪の父は生前に自分史のようなものをまとめていた。手記を通じて諏訪は父が幼い頃に一家で太平洋戦争後のハルビンでいわゆる「棄民」として収容所に収監されており(いわゆる「棄民」である)、さらにそこで祖母と叔父が命を落としていたことを知る。第二次世界大戦時下、満洲国は同国への開拓移民を募り、45年の終戦までにおよそ27万人の日本移民を送りこんだ[7]。その中にいたのが諏訪の父を含む祖父一家(祖父周吉、祖母信子、父豊、叔母、叔父邦夫)であった。しかし一家の渡満直後に旧ソ連軍の攻撃が始まり、一家は満州からの避難を始める。一家は哈爾浜桃山小学校(現・哈尔滨市兆麟小学校)へ、そして冬には新香坊の難民収容所に収容された。収容所の環境は劣悪で発疹チフスなどの病、栄養失調、飢餓、もしくは満州地元民の襲撃によって元開拓団員およそ7万8500人が死亡したとされる[8]。諏訪の祖母・信子と彼の叔父もまた栄養失調と発疹チフスにより命を落としている。残された家族が日本に帰国することができたのは46年の10月のことであった[9]。
彼女たちが経験したもの、見た風景とは何か。諏訪は祖母と叔父の経験をより深く知るために「彼らが見た風景」を辿ろうと試みた。しかし2012年に取材旅行として初めて旧満州地域を訪れた際は思うような成果を得ることができなかった[10]。このことを知ったNHKで放送されたETV特集「忘れられた人々の肖像 ~画家・諏訪敦 “満州難民”を描く~」(2016)担当ディレクターの中沢一郎氏の協力などにより、資料や当事者たちの証言が揃うようになり、再度の取材旅行の機会に恵まれる。多くの資料などによって帰国後に描かれた大作が《HARBIN》である。


《HARBIN》は、大きな油彩の作品だ。荒涼とした雪原に1人の女性が横たわっている。肢体は棒切れのように曲がり固まっており、既に彼女の身体が亡骸になってしまっていることを見る者に伝える。白い襦袢がはだけているのは、収容所では持ち主の死後はその夜着すらも食糧などの交換のために剥ぎ取られていたという証言を基にした表現という。女性の身体は肋骨や大腿部の筋が浮かび上がって見えるほどに痩せ細っている。肌は土気色でチフスの症状である赤い斑点が散らばっている。長い間横たわっていたのだろうか、彼女の喉元や腹部には雪が積もっている。彼女の頭部に目を向けてみる。《棄民》で描かれた祖母の姿よりも髪が短く描かれているのは、男性のような見た目になることで現地民やソ連兵の性的暴行から身を守ろうとしたという当事者の証言によるものだ。顔色は身体同様に悪く、頬がこけているのがわかる。閉じられた瞼が身体の凄惨な状態に対してどこか安らかな表情に見えるのは描いた画家の願いによるものだろうか。《HARBIN》の彼女の顔を見ていると第1章の展示室に並ぶ家族のさまざまな眠る肖像と重なり合う。展示室の中で我々が出会ってきた眠る画家の息子、ICUで横たわる父、そして永眠する時の父の顔が想起される。
諏訪は祖母たちが見た風景、そして彼女たちに起きたことを絵画に描く際、興味深い描き方をおこなった。まず健康な女性の肉体を描く。その上で飢餓による衰えや、断髪、そしてチフスの症状を描きこむことで絵の中の女性にそれらを「経験」させていくのである。「棄民」の人々の経験を現地調査、資料、医学的知識に基づいて、祖母という個人の身体描写を通じて想像するのである。徐々に痩せ衰えていく親族を描くことは家族である画家自身にとっても過酷で残酷な仕事である。それでもその描き方を選んだのは、祖母たちが経験したであろう、さまざまな過程を絵の中の彼女に経験させることが重要だったからである[11]。
描き込まれた身体変化の過程は一旦完成した画からは全て推察することはできない。そこには「経験」後の彼女の姿が残されている。その代わり、その過程は同じ展示空間にある8枚のスライドアニメーションで見ることができる。

画家が記録用に残した作品の各過程を写した写真記録がもとになっているスライドであり、それらの写真によって我々は、描かれた女性の身体変化、つまり彼女がいかなる「経験」をしたのか知ることができる。身体の変化と不在の祖母の経験が描かれた絵画作品が並び立つこの空間において、観察と歴史に裏打ちされた家族の物語が提示される。
《HARBIN》を一旦完成させた後、諏訪はもう一枚の作品を描いた。モノクロの画面の中に裸体の女性が横たわる作品《依代》(2016-17)[12]は《HARBIN》で描いた祖母や祖父の経験、そして投影し続けたさまざまな記憶を悼むようだ。
この展覧会における主眼でもある「ものを見る」ということについて、我々は横たわる飢餓と病で命を落とした1人の女性を通して問いかけられる。彼女はあくまで画家の祖母のような人物に起きたと考えられることをベースにしており、祖母本人の克明な記録ではないことは了解しておかなくてはならない。そして彼女は諏訪の祖母に代表される棄民の一般像であると見なすこともまた正確ではないと言えるだろう。緩やかに変化していく女性の身体を見ていると、その変化を目で追いかけようとする自分に気が付く。それはあたかも「見る」という時に乱暴な行為を内省するようだ。彼女の身体の感触や、彼女が横たわる大地の冷たさを目から脳へと取り入れようとして私たちは一体「誰」を見ているのかとふと我に帰る。家族の物語を紡ぐ諏訪の試みは同時に戦争を間近に経験していない現代の一個人が戦争に肉薄するための終わりない模索であり、その一つの試みと成果が視覚が拡張されていく感覚を覚える。その収穫はもちろん画家のものだけではなく、鑑賞者にも共有されるものである。
2.「第2章 静物画について」―視覚の標本室―
既述のように、第2の展示室は静物画をテーマにしている。壁面や台座が黒いことも相まって、第1の展示室、これから向かう第3の展示室とは異なった趣を見せる。作品は展示室の壁面だけではなく、空間全体に配置されておりインスタレーション展示の形態に近しい。描かれているモティーフも相まって、絵画の展示というよりもむしろ博物館の標本展示室を思わせる。
展示室では部屋天井からのライトアップはLEDで正確に画面に合わせて矩形の光をあてた。ミリ単位の精度で絵画そのものだけに光を当てる精度を上げることにより、あたかも絵そのものが光源となり光を放っているような錯覚を促すような演出が可能になった。
この展示空間の構成には美術設営事務所であるHIGURE 17-15 cas.[13]の有元利彦氏をはじめとした設営のプロたちの協力があった。同展示では額縁に低反射ガラス(アクリルの場合もあり)が使用された。諏訪はあえて低反射にこだわった理由について以下のように述べた。
「絵画と鑑賞する私たちの関係性は重要で、たとえばゲルハルト・リヒターやフランシス・ベーコンは、リフレクションを作品の効果に積極的に取り入れたことで知られている。しかし私はむしろ反射がないことで、鑑賞する人間の自意識を希薄にし、気づけば「目」だけになっているような錯覚を導くことを構想した。」
また、画面の反射を抑制するために用いられた大きな面積のアクリルボックスは三菱ケミカルのモスマイト™[14]のプロトタイプ製品の供与を受けている。

このような展示形式は諏訪の希望が実現したものであった。その狙いは絵画と絵画の外の世界の関係において、視覚のありかを問い直すことだ。
「因習的な絵画作品と額縁の関係は、結界としての額縁に守られていて、環境が変化しても、つまりどんな壁面にかけられていても額縁に区切られた絵画の内部そのものは、異世界の窓として守られている。しかし実際はそんなはずはなく、作品は周囲の環境と無関係ではいられない。周りの状況で作品のありようは変化する。状況に左右される。それを無視して体裁だけを整えるというものは嫌だった[15]。」
この章で展示されている作品が制作された経緯は実に多様であり、静物画に対し諏訪が抱く問題意識や関心は多岐に渡り、重層的であることを示している。展示作品からいくつか考えてみる。《不在》(2015)(図6)[16]、《東と西》(2015)[17]をはじめとする豆腐を描いた諸作品の中でも、《不在》(2015)はまな板の上に豆腐が乗っているという一見すると非常にシンプルな作品である。この作品には明治期に活躍した洋画家高橋由一(1828〜1894)の《豆腐》(1877)[18]という原型がある。諏訪は高橋の作品の構図を引き継ぎながらも、高橋の作品にはあった焼き豆腐と油揚げは描かなかった。「日本洋画の開拓者」とも称された[19]高橋の作品を基にその欠如を描き、日本美術史における西洋画の需要度合いの問題などが重ね合わされている。日本美術史における西洋画受容とその発展の歴史は本家本元の西洋美術史と比べてもいわく言い難い複雑さと不確かさをもっており、その不安定さや問題が意識されている。

同展のタイトル「眼窩裏の火事」は近年諏訪の視界に現れるようになった閃輝暗点の症状も作品制作に深く関係している。閃輝暗点とは眼を酷使するとしばしば起きると言われる現象で、詳しい発生メカニズムはまだ解明されていないが眼から脳への血流もしくは神経回路の異状により明滅や陽炎のようなゆらめきが視界に現れるようになる。モチーフやキャンバスを凝視することが多い諏訪であるが、彼はこの光を嫌うのではなくむしろ興味を示した。《眼窩裏の火事》(2020-2022)[20(図7)は60.6×90cmの画面にガラス瓶や食器が描かれている作品だ。一つ一つのグラスや水差し、カップが持つ質感があたかも実際に触れることができるかのような質感で描かれている。グラスの側面は絵の外の景色を反射しており、グラスの置かれた風景の向かいにある景色を私たちに想起させる。こうしたリアルな光景の左に寄ったあたりに鬼火を思わせる白い光のようなものがあることに気がつく。この揺らいだものが閃輝暗点の症状の描写である。
誰が見ても同じはずのガラス瓶のある空間、一輪の百合の花に閃輝暗点による光や揺らぎを作品に描き込むことで、鑑賞者は視覚のありかについて問いかけられる。誰が見ても変わらないものの精巧さを鑑賞しているはずの我々は静物に、そして写実的な描き方が対象の普遍性を提示しているのだと誤解していたことに気づかされる。

このような諏訪が静物画に対して持つ様々な問題意識が重なり合っていることを示すのがこの展示室の特異な空間であると筆者は考える。展示室では作品は壁面に展示されているものもあれば部屋の中央部の黒い台の上に乗った状態で展示されている場合もある。ある程度の順路を持ち、会場で配布された一覧表には便宜上作品のナンバリングはなされているが、筆者が訪れた時来館者はそれぞれ散り散りになって中心部に向かう者もあれば、入り口すぐの壁面に向かうものもあった。1章の部屋と比較してこの部屋にはプロセスを辿ることの必要性は弱まる。その上で、ひとつひとつの作品が持つ目的や課題の重層性は作品という独立した境界を超えて互いに結びつきあっていることを鑑賞者は感じ取ることができる。その点で「作品のありようは変化する」という考えから展示室をインスタレーションの形式にした効果がまさに表れていると言えるのではないだろうか。
3.「第3章 わたしたちはふたたびであう」―交差する記憶―
静物画の空間を抜けた先には無数の肖像画が並ぶ白い空間が広がっており、肖像画や石膏像が並んでいる。SF映画の一場面や病院の無菌室を思わせる非日常的なその場所が「第3章 わたしたちはふたたびであう」の舞台である。

諏訪は亡き人と作品で関わることがしばしばある。モデルの幾人かは鬼籍に入ってしまったことでもう描くことの叶わない人々だ。例えば、若くしてシリアで命を落としたジャーナリスト・山本美香を描いた《山本美香(五十歳代の佐藤和孝)》(2013-14)[21](図9)がある。彼女の瞳の奥をよく見ると、パートナーであった佐藤の姿が描きこまれている(図10)。10年の節目ごとに佐藤の肖像画を描き続けていた諏訪はもう会うことの叶わない彼の妻・山本美香の眼の中に50代になった佐藤を描いたのである。


図10(画像下). 《山本美香(五十歳代の佐藤和孝)》(部分) 山本の瞳の奥に立つ人影は
パートナーの佐藤である。
細い通路のような展示空間の最奥にはシャツ姿の長髪の女性が描かれた作品《Solaris》(2017-21)[22](図11)が掛けられている。この題はスタニスワフ・レムの古典的SF『ソラリス』を基にしている。惑星ソラリスの生命体たちは他者の記憶を読み取り、喪失などのトラウマにより強い感情を抱いている人物のコピーを生み出す習性を持つ。描かれている女性の太ももあたりから頭部にかけて青白い煙のようなものが立ち上っている様が線香の煙や鬼火のようにも見え、彼女もまた今は亡き誰かであるのかと思わせる。

右へ曲がると、この展覧会最後の展示空間へと入る。同じ3章ではあるがそれまでの展示と比べてその趣は異なる。展示されているのは90年代後半から取り組み続けた、舞踏家・大野一雄氏への取材と制作[23]、そして本展覧会で公開されたパフォーマー・川口隆夫との新作インスタレーションである。

3章ふたつ目の展示室内を入って正面の壁面には90年代終盤より取材と制作を繰り返してきた対象大野一雄の最晩年を描いた油彩画《大野一雄》(2008)[24](図13)が、そして作品の左手の壁には90歳代の大野を描いた《大野一雄立像》(1999/2022)[25]が並ぶ。《大野一雄》(2008)では、100歳を超え寝たきりで過ごすようになっていた大野一雄を描いている。布団や服にあったはずの模様は簡素化されており、口を開けた状態で床に横たわる大野一雄の身体に注力している。手の皺やシミ、頬のこけた様子が克明に描かれ、大野自身がどれほどに老いても身体には自身の経験と記憶が刻まれているということを画家は対峙し描くことで証明しているかのようだ。

大野一雄にまつわる作品と共に、大野の舞踏を映像資料などで観察し完全コピーして研究し、パフォーマンス《大野一雄について》を行なってきた川口隆夫[26]を描いた《大野一雄「タンゴ」を踊る川口隆夫》(2020)[27]をはじめとした川口隆夫のパフォーマンスを諏訪がスケッチした作品や舞踏研究所で川口をスケッチする様子を撮影した写真が展示されている。
《《Mimesis》のためのイメージボード》(2020-2022)[28](図14)では後述する作品《Mimesis》に象徴的な幾重にも重なる人間の身体を彷彿とさせるラフスケッチが描かれ、その背後に川口の過去の公演や中止となったSIAF2020のフライヤーがあり、《Mimesis》のみならず、展示インスタレーションを形成する出来事や人物が組み合わさったイメージが構築されている。

メディア、90×60cm、作家蔵
これらの経験や習作、イメージを基に描かれた展覧会の最後を締めくくる新作《Mimesis》(2022)[29](図15)は259×162cmという縦に大きい作品で、白壁を背にして踊る川口の姿が描かれている。バレリーナのように左足を宙に浮かせ、右足だけで立っている川口の身体からは数本の腕が伸びている。腕は裸であったり、ワイシャツのようなものを着ていたり、あるいは半透明で描かれているが、それぞれが踊りの所作を示しているように思われる。腕それ以外の部分にも腹部と衣服が混ざり合うように描かれることで腹部がシャツの裾のように丸まっているように見える。川口の頭部から少し右に視線を移すと、眼窩と鼻だけの仮面のようなものが描かれているのがわかる。複数の色が混ざった絵の具が垂れるように画面下部へと流れ、腕や胴の周りにプリントエラーを思わせる絵の具の混ざり合った線がいくつもある。全体のそうした様子も相まってか、川口の身体はどこか1人の人間としては規定されないようになっており、地面から浮かぶように見える。

作品タイトルの“mimesis”という言葉は模倣を意味している。諏訪は同作の中に3人の人物を投影した。前述の通り、川口は大野一雄の舞踏を模倣する形でさまざまなパフォーマンスを作り上げた。そして大野一雄もまた、《ラ・アルヘンチーナ頌》というダンス作品を通してその功績を讃えているようにスペインの舞踊家ラ・アルヘンティーナの踊りに多大な影響を受けている。それぞれが受け継いできた踊りがさらに他者の表現に影響を与えていく様が表れている作品なのだ。
この展示の原型は諏訪が招聘されていたが現地開催が中止となった札幌国際芸術祭2020(以下、SIAF2020)で構想されていたインスタレーションである。大野一雄を描いたプロセスと作品の展示に加えて、パフォーマーである川口隆夫氏との共同作品を公開することを検討していた。府中市美術館の展示では同案を引き継ぎつつ、展示空間では壁面と床の双方を白く「漂白」することで空間をSF的な空間、あるいは無菌室のような空間に仕立てた。訪れた人が非日常的な空間に迷い込み、果てはどこにいるのかということさえもわからなくなる空間を目指したという。その効果について実際の鑑賞者のコメントを踏まえて諏訪はこの展示空間を次のように言い表している。
『鑑賞者の実際の感想には、「重力の差を感じる」というものが散見されたが、それは錯覚に過ぎない。しかしその知覚体験はとても重要で、絵画はそもそも錯覚を利用した一種の詐術であることも無視のできない事実であろう。強引に感覚を歪めるようなインスタレーションとは違う……それよりもささやかな感じ……鑑賞者の方が自ら幻惑に歩み寄れるような空間を目指した。[30]』
諏訪の作品の特色は多岐に渡る。本展覧会のこの章においてそのうち一つを語るとすればそれは個々の身体が持つ人間との関係や記憶の残滓を丁寧に描き出していることではないかと私は考える。あらゆる個人の所作から時に他者の面影を見るように、1人の身体の中にはその個人が影響を受けてきた、その場にはいない他者の所作が現れる。その他者もまた、その場にはいない誰かの身体や記憶、関係性を受け継いでいるのだ。そのように身体に宿る記憶の表出を諏訪は非常に慎重に描く。その表れが《山本美香(五十歳代の佐藤和孝)》における山本美香に描きこまれたパートナーの佐藤和孝であり、《Mimesis》における重なり合う3人のダンサーたちの表象なのだ。
このアプローチを支えるのが展示空間である。「漂白された」とも言うべき白い空間に作品を置くことで、鑑賞者は画中のささやかな記憶の表象と対峙することが可能となる。
4.鑑賞を終えて
本展覧会では、3つの章を設けて画家・諏訪敦の画業の一部を振り返った。1章では父の死と手記の発見をきっかけにはじまった「棄民」であった祖母のことを知り作品へと繋げる経験を画家と鑑賞者が共有した。展示室では制作の時系列を追うものに近い構成を取っていた。2章は静物画をテーマとし、多様な課題をもとに描かれた作品を展示していた。作品は壁面だけでなく中央空間にも配置され、鑑賞者は作品の間を歩き回り、作品が持つ問題意識同士の結びつきを見る。最後の3章では肖像画、特にもう会うことが叶わない人との邂逅を焦点に当てた作品の展示だ。ここでは2章と一転してSF空間を思わせる白い空間へ変わることで描かれた人物はもちろんのこと、その人の身体に潜む他者の記憶の残滓に近づくことの補助役となっていた。
近代以降の視覚情報が氾濫し、雑多なイメージの括りとそれに対する想像力が乏しくなる中で、リアルなイメージに全てを委ね、対象を乱暴に理解することに対して一石を投じるまたとない展覧会であると痛感する。作品の制作意図や狙いと展示の手法が呼応しあって絵画、ひいては対象を見ることの可能性について鑑賞者に問いかける。鑑賞者は作品を通して、描かれる対象の集積した時間、画家の思惑が融合していることをあらためて認知し直す。
今や古典的なメディアとなった絵画、特に油彩画ならびに写実的描法であるが諏訪敦は絵画の空間との関係性において絵画表象の模索だけでなく、展示という観点からも絵であるからこそできること、そしてこの長い美術史の中でまだ明るみになっていない絵の可能性を模索し続けている。
本レヴュー執筆にあたり、インタヴューを快諾くださった諏訪敦様、執筆をご指導いただいた浅沼敬子先生に深く感謝を申し上げます。本文で引用している展示室の画像は府中市美術館の鎌田享様にご提供いただきました。画像提供と使用許可をくださいましたこと感謝致します。
展示室以外の作品の画像は諏訪敦様からご提供いただきました。なお一部の図は本展覧会図録『諏訪敦作品集 眼窩裏の火事』(諏訪敦著、美術出版社、2023年出版)から引用し、画像の部分使用やトリミングは全て執筆者によるものです。
上村麻里恵(北海道大学修士課程2年)
[1] 《father》(1996) パネルに油彩、テンペラ、122.6×200cm、佐藤美術館寄託
[2] 《HARBIN 1945 WINTER》(2015-16) キャンバス、パネルに油彩、145.5×227.3cm、広島市現代美術館蔵
[3] 《日本人は樹を植えた》(2016) 紙、パネルにミクストメディア、45.5×33.3cm、個人蔵
[4] 《Untitled(未完成/Unfinished)》(2017/2021-2022) キャンバス、パネルに油彩、145.5×227.3cm、作家蔵
[5] 《棄民》(2011-13) キャンバス、パネルに油彩、259×162cm、個人蔵
[6] 執筆者の諏訪敦へのインタヴュー、2023年1月28日より
[7] 二〇世紀満州歴史事典、貴志俊彦ほか編、吉川弘文館、2012年、P.542坂部
[8] 貴志前掲書、P.543坂部
[9] 諏訪敦作品集 眼窩裏の火事、諏訪敦著、美術出版社、2023年、《棄民》関連年表、P.57-59
[10] 現地で諏訪の取材旅行は現地の人々にとって戦没者遺族のよくある遺骨探しの旅であるとみなされ、資料の捜索などがほとんどできなかった。満州での戦中戦後の歴史は現地の人々にとって被害者でもあれば加害者でもある出来事であり、積極的に当時のことを語ってくれる者も少なかったようである。
参照:なぜ戦争をえがくのか : 戦争を知らない表現者たちの歴史実践、大川史織編著、小泉明郎ほか著、みずき書林、2021年
[11] 執筆者の諏訪敦へのインタヴュー、2023年1月28日より
[12] 《依代》(2016-17) 紙、パネルにミクストメディア、86.1×195.8cm、個人蔵
[13] HIGURE 17-15casのwebサイトよりhttp://higure1715cas.com/#top
[14] モスマイト™の特色は蛾の眼が持つ凹凸構造を基にした低反射フィルムである。表面反射を押さえ、高い透明性を維持することができる。
参照:モスアイ型反射防止フィルム モスマイト | 製品情報|三菱ケミカル株式会社 https://www.m-chemical.co.jp/products/departments/mcc/hp-films-pl/product/1200589_7370.html
[15] 執筆者の諏訪敦へのインタヴュー、2023年1月28日より
[16] 《不在》(2015) キャンバス、パネルに油彩、32.5×45.3cm、個人蔵
[17] 《東と西》(2015) キャンバス、パネルに油彩、32.5×45.3cm、個人蔵
[18] 《豆腐》(1877) キャンバスに油彩、32.8×45.2cm、金刀比羅宮 高橋由一館所蔵
[19] 金刀比羅宮 | 高橋由一館ウェブサイトより https://www.konpira.or.jp/articles/20200710_takahashi-yuichi/article.htm
[20] 《眼窩裏の火事》(2020-2022) 白亜地パネルに油彩、60.6×91cm、作家蔵
[21] 《山本美香(五十歳代の佐藤和孝)》(2013-14) 白亜地パネルに油彩、53×41cm、佐藤和孝蔵
[22] 《Solaris》(2017-21) 白亜地パネルに油彩、91×60.7cm、作家蔵
[23] 大野一雄、大野慶人と諏訪敦の関わりは90年代終盤からのことだった。それまでスペインに滞在しながら作品制作を行なっていた諏訪は自らの日本人というアイデンティティについて考えるようになる。帰国後に取材を申し込んだのが、日本人の身体性や文化に深く根差した前衛ダンス「暗黒舞踏」の大家である大野一雄であった。大野一雄はこの時すでに90歳を超えていたが第一線に立ち続けていた。諏訪は大野自身への取材はもちろんのこと、文献を調査し、映像資料見直しを行い、そして故郷である函館に実際に足を運んだ。その結実として描かれた作品の一つが《大野一雄立像》(1999/2022)である。その後その息子であり舞踏家の大野慶人に対しても取材と作品制作を行なった。2006年、諏訪は再度大野一雄への取材を行い、《大野一雄》(2008)として100歳を超え寝たきりとなった大野の姿を描いている。
[24] 《大野一雄》(2008) キャンバスに油彩、テンペラ、120×194cm、作家蔵
[25] 《大野一雄立像》(1999/2022) 綿布、パネルに油彩、145.5×112cm、作家蔵
[26] 川口隆夫(1962〜)は佐賀県出身のパフォーマーである。96年からアーティスト集団「ダムタイプ」に参加を始める。2000年以降はソロ活動を開始する。川口自身は生前の大野のパフォーマンスを直接見ることは叶わなかったものの、映像資料などの見直しを通じて徹底的にその踊りをコピーすることで作品《大野一雄について》(2013〜)を発表する。川口を諏訪が知ったのは大野一雄が亡き後のことだ。川口との出会いを通じて諏訪は後述する札幌国際芸術祭の展示構想を練り上げていく。
[27] 《大野一雄「タンゴ」を踊る川口隆夫》(2020) 紙、パネルに鉛筆、32.5×32.5cm、作家蔵
[28] 《《Mimesis》のためのイメージボード》(2020-2022) パネルにミクストメディア、90×60cm、作家蔵
[29] 《Mimesis》(2022) キャンバス、パネルに油彩、259×162cm、作家蔵
[30] 筆者による諏訪へのインタビューより