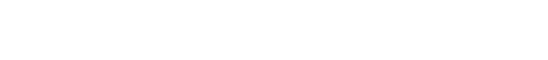1992年に「シアターキノ」を設立して28年、42日間もの休館が起きようとは。日常生活が静かな不安で脅かされていくこの体験は、ポストコロナを新しい芸術表現がきっと描くことになるだろうからここでは語らないが、人類が自然領域に踏み込んだ地球環境の破壊がもたらしたことには間違いないだろうと思っている。
私は、札幌市民交流プラザSCARTSの企画公募事業に昨年採択され、市民参加型のアートプロジェクト「記憶のミライ」展を7月11~20日に開催した。制作が新型コロナ感染が拡大し始めた時期だったので、少なくない影響があったと思っている。制作準備から本開催までのプロセスを振り返りながら、考えてみたい。
70年頃から映像制作をはじめた私は、80年代からは映像、インスタレーション、パフォーマンス、舞台美術など表現の枠を広げていき、個展やグループ展、映画祭などで発表を続けていた。92年にアート系の映画を上映していた4スクリーンが閉館し、映画に関わっていた者としての札幌での役割を考え、ミニシアター「シアターキノ」を市民出資で設立し、運営に専念するために制作活動を休止した。その後、シアターキノを運営しながら、ワークショップや講座、フィルムコミッション、プロデュースや映画祭、芸術祭スタッフなど、裏方としての様々のマネージメント活動をやってきたが、ほぼやり尽くした感があり、また表現することの喜びは忘れがたく、2018年から制作活動を再開させることになった。
初めは、ちょうど紅櫻公園アートannual(札幌市南区)が開催されることになり、参加させていいただいた。28年ぶりの制作ではあったが、休止中もメディアへの関心はずっと続いており、メディアの現状を可視化する「公平中立」というLGBTのレインボーカラーを使った作品を制作。そして70年代より関心があった水、水道管、窓、メディア、記憶を題材にして、「水の部屋 世界の窓」(2019 500m美術館)、「水がなくなる日」(2019 紅櫻アートannual 2019)と発表してきた。どれもがその時に感じたり考えたりしている社会のことを題材にしていた。特に「水の部屋 世界の窓」は、企画を応募しようとしていた時に、胆振東部地震があり、私たちが当たり前と思っていた水や電気や情報が断ち切られるという体験をした結果、私自身も急遽企画を考え直して別のものになった。
今回の「記憶のミライ」は、それらを経験した上で記憶を扱おうと考えていた。最初のコンセプトはこうだった。「札幌という街は、どんどん発展し変貌を続けていますが、歴史が浅いと言われる札幌でも、その根底には市民による毎日の小さな暮らしの積み重ねがあります。名もなき市民の小さな営みが実は大きな波となって、札幌の歴史を作っています。そして、私たち人間は記憶を積み重ねて生きています。数ヶ月で細胞が入れ替わるように、私たちの体は日々変化しています。記憶もまた細胞が新しいエネルギーを生み出すように、積み重ね変化することによって、新しいミライを作り出していきます。そうやって、私たちは、長い歴史の中で、少しずつ記憶という知恵を活用する術を覚えてきました。今回の市民参加型アートプロジェクト『記憶のミライ』は、市民の皆さんから記憶の積み重ねの一つである8ミリフィルムの映像を提供していただき、その風景や生活、そして文化という営みの知恵を、現代また次世代へつないでいくための芸術表現として創作します」
一つには、できるだけ市民参加型にしたいと思ったこと。また私にとっても8ミリフィルムには様々な記憶があることと、このメディアが持つ特有の質感が好きだったこと。そこで札幌市民の皆さんから、昔の8ミリフルムを提供してもらい、それをデジタルへ変換して編集する映像と、8ミリの物質性を表現に取り込みたいと考え、8ミリの一コマ、一コマを切って、数千個の8ミリのコマが会場内に設置された透明な球体(バルーンのようなもの)の中を浮遊するインスタレーションと8ミリ映像で構成しようとプランをたてた。そこで昔切り取っていた新聞記事の北大工学部の流体力学の実験を思い出し、19年の5月にまず相談に行った。関心を持っていただいたが、夏の「水がなくなる日」の制作や、20年に撮影しようと企画していた短編映画の資料集めでそのままになっていた。その後SCARTSの企画公募があることを知り、SCARTSスタジオでこの企画が実現できないかと考え、19年秋から正式に企画としてまとめて年末に採択された。
2020年になって、8ミリフィルムの募集をまず始めて、同時に小林大賀くんに8ミリフィルムのコマを浮遊させるテストを開始してもらい、北大工学部にも再度来訪し、協力の快諾をえた。だが、3月に入って新型コロナ感染状況が悪化して、連絡が途絶えてしまった。8ミリフィルムは最終的に33名の市民のみなさんから247本、約45時間分が集まり、3月中旬からGWにかけてほとんどを見て、その中から5時間分を選び、5月中旬にスタジオでデジタルへの変換作業を行った。同時にインスタレーションの方は北大の協力を諦め、空中での浮遊ではなく、私が素材として使い続けていた水の水槽を作り、8ミリが水中を浮遊するプランに変更していった(※空中に浮遊するプランは、また挑戦したいと思っている)。
さて、メインになる8ミリ映像は、先述のように札幌の昔の風景や生活文化、行事やイベントなどをまとめて、市民が積み重ねてきた歴史を表現したいと考えていた。ところが集まってきた膨大な市民の軌跡を見るにつけ、子どもたちや登場する人々のあまりに自然な表情に引き込まれていく私がいた。それはちょうど新型コロナで北海道から緊急事態宣言がでて、さらにシアターキノが休館になっていく時期だった。私は、何に魅かれていたのだろうか。これは後に開催して観客の方々と話していくうちに気づいていったのだが、この8ミリ映像にある世界は、今私たちが共有を強いられているソーシャル・ディスタンスとは真逆の、距離の近さがあることだった。被写体の子どもや家族や友人たちは、カメラがあることをわかっていながら、あることを忘れているかのように自然に振る舞い、笑顔をみせ、写そうとする作者もまたカメラを回していることを忘れているかのように被写体に近づいたり、振り回したりする。この間にある媒体としてのカメラの存在とは一体何なのだろうかと考えつつ、私は映像が持つ圧倒的な力を感じていた。ここにはワンショット、ワンショットの映像の根源的な力を見ることができる。約2時間のいわゆる映画的な物語ではなく、ワンショットの背景にあるものを想像して、見るものが物語を自身の中に築いていっているのだ。

1895年の映画の誕生期に作られた膨大な30秒程度の作品群からは、今の映画の多様な原型を見ることができる。まだ自分では分析できてはいないとはいえ、私はなぜかその誕生期の作品に似たような感覚を覚えてもいた。そして、この文章を書く1週間前に日帰りで訪れた神田日勝記念美術館(鹿追町)で見た神田日勝の絵を思い出してもいた。あの圧倒的な原初的な絵の力はなんだろうか。この場で例に出すのはあまりに失礼とは思いつつ、映像や現代アートの表現者の一人としては、このことをもっと考えてみなくてはと思っている。
さて、そんな試行錯誤の結果、私は編集方針を人を中心としたものに変更し、デジタルに変換した5時間の中から今度は約1時間分を選んで編集を始め、担当する中野均くんが編集しては一緒にチェックをしてまた編集する過程を何度も繰り返し、約17分程度の映像作品が出来上がった。これをスタジオの4面と真ん中の水槽に天井から投影しようと考えていた。そこでまず企画協力者であるシアターキノ支配人で妻の中島ひろみに見てもらった。正直酷評であった。詳細を述べる余裕はないが、要は私がせっかく感じていたワンショットが持つ映像の力が活きていないことだった。私は8ミリをデジタルにすることにおいて、デジタル的な画像や編集技術をかなり使おうと努めていて、約1時間近くある膨大な量の映像を17分程度にうまくまとめていったつもりだった。けれども、そこには情報はあっても、大切なものは映ってはいなかったのだ。遅くまでひろみと話しあい、私が感じたワンショットの大切なものを伝え、この8ミリのオリジナルをリスペクトして、できるだけサイズも変えずに伝えるために、一つの映像にまとめるのではなく、4面+1の映像を全部違うものにして5つの映像を作ることを決め、編集を始めからやり直すことにした。その結果、5つで合計約40分の映像として最終的に仕上げることができた。
同時に、全体の会場設計を頼んでいた丸田知明くんとテストをしてくれていた小林くんたちと会場の下見を何度かさせてもらい、アイディアを出し合って話し合い、4面には布のスクリーンを作って会場内に部屋を作ることにした。これにより、部屋の内側では4面+水槽の画面をぜんぶに囲まれた体感型で見ることができ、外側からは一つ一つの画像をじっくりと見られる構造を作ることができた。さらに設営間際には、SCARTSのテクニカルディレクターの岩田拓朗さんはじめチームの皆さんのご協力もあり、プロジェクターとの見切りのラインなどを計算すると少しでもスクリーンを大きくするために、部屋の位置を会場に対して斜めにすることにした。水槽の大きさや天井との距離ほか、水道管からの水の落とし方など、様々なことが現場で決まり、変更することも当然あった。そして、編集が最終段階に入って、音楽の井上大介くんとの話し合いが何度も続いて、まさに「記憶のミライ」チーム。映画で言えば私が監督で、編集や、撮影や、美術や、大道具小道具、音楽などのスタッフがいるようにそんな制作のプロセスを経験したことは学ぶことも多く、また現代アートの制作はこのようなチーム制が増えているのだろうと実感した。

そういえば、チームには広報デザインや、デジタル化のスタジオはじめ、スクリーンやプロジェクターの設置、水道管の設置、水槽制作などプロの業者を含めて大変お世話になった。また、8ミリカメラや映写機の展示も登別映像機材博物館の提供で、館長の山本敏さんにも会期中ほとんど在廊いただいた。懐かしいと思われる以上に、映像に関心を持つ若い観客が彼らにとって新しいメディアとして高い関心を示し、私が例の一つとして語った「古民家を改装したカフェ」のイメージで、古いものや、昔の知恵を忘れず、未来に活かすことのコンセプトを理解してくれもした。

そして、会期中に観客の方々と色んな話をしてまた感じたのは、先述のソーシャル・ディスタンスとは真逆の距離の近さ、またグローバル社会で世界の大きさと成長が語られる中で、むしろこのホームムービーという小さな世界の中にある暮らしを大切にした生き方こそが、新型コロナ状況下でより大切に感じられたのではないかということだ。
新型コロナと共生していくことになるであろうこれからの社会は、小さなコミュニティ、ネットワークを大切にし、その外側ではSNSやリモートでも結びつく、そんな姿を描いている。決して懐かしさや思い出だけのためではなく、これからの私たちが生きていくための知恵と工夫になるものが、「記憶のミライ」の中に積み重ねられていたのではないかと思っている。
中島洋(映像作家、美術家、シアターキノ代表)
※写真は露口啓二
中島洋WORKSは、yonakajima.comでご覧いただけます。
※若い友人が、オンライン3Dで「記憶のミライ」の部屋を再現することを作業中です。9月ころにはオープンできるのではないかと思っていますので、ご覧いただければ幸いです。