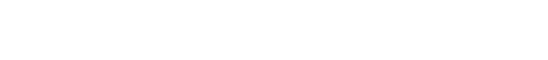4.北海道表象の二面性―大正~昭和前期の博覧会―
明治期からさらに時代が下がって、大正・昭和期になると、北海道における博覧会はより活発になるとともに、派手になっていく。たとえば、1918(大正7)年に開催された「開道50年記念北海道博覧会」は、公式の事業報告によれば「明治二年開拓使設置以来既往五十年間の治績を回顧して其の現状を展示し汎く朝野の人士を招請して其の視聴を喚起せしめ以て将来益々本道の拓殖の促進の費に供せんとする」1目的で企画され、主要な会場は、現在の札幌の中島公園と北1条西4丁目に造成された。明治期にはまず、中央で開催された博覧会に、「開拓使」が北海道を出品することで中央にその存在感をアピールした。では、大正・昭和期に北海道を舞台に展開された大掛かりな博覧会で「視聴を喚起せしめ」る相手である「朝野の人士」とは、具体的に誰を想定していて、「益々本道の拓殖の促進の費に供せん」という経済的な大義は欠かせないとしても、その「費」の獲得につなげるために、何をどのように「視聴」させることが目論まれていたのだろうか。


当時の写真帖や絵葉書(fig. 1-2)から会場の様子を探れば、上述の目的に沿って北海道の物産や農工業の様子など、それまでの「拓殖」の成果の展示に加えて、協賛者であった「内地」のいくつかの都道府県のパヴィリオンや、当時日本領だった台湾や朝鮮のパヴィリオンも見受けられる(fig. 3-4)。こうした展示構成は、実は北海道に限ったものではなく、台湾、朝鮮、満州、樺太などにおける博覧会にも共通するものだった。現在ではこの表現は憚られるきらいがあるが、北海道開拓初期に刊行されていた『移住案内』では、北海道は明確に「殖民地」と記されている2。つまり、当時の人々にとっては、北海道は、台湾、朝鮮、満州、樺太などと並んで、日本がその外部に新たに獲得した植民地のひとつであり、誰に向けて何を見せようとしたのかは、そのことを踏まえて考える必要がある。


植民地博覧会を詳しく研究した山路勝彦が、満州での博覧会について述べた考察によれば、「興味あることに、それぞれの博覧会で満州が見せる表情は異なっている。日本で行われた博覧会に出場した時は日本に対して豊富な資源の供給国としての姿を見せ、シカゴに登場した時は独立国としての威厳を見せようとする。これに対して、満州で行われたときは満州の豊かさを説いて、日本各地から参加した数多くの出品者に伍していけるという自己表現をする」3。満州と博覧会をめぐるこの構図は、満州を北海道に置き換えてみてもほぼ通用するだろう。ただし、日本(内地)、外国、当地という開催地の違いにもとづくこの切り分けは、実際にはそう単純にいかないところもある。
佐藤真名の整理4に基づけば、開道50年博の総入場者数は140万人を超えており、当時の北海道の人口が208万人余り、札幌の人口がわずか9万5000人だったことを考慮すると、道民の多くがこぞって訪れたとともに、これほどの来場者数は道外からの旅行者も多数あってこそ達成されたのであろうと推測される。一般来場者の属性がわかる記録までは探し出せなかったが、先の事業報告には、「来賓」の項目があり、そこには政府の要人や国会議員をはじめ、地方自治体の首長、省庁所属の技師たち、大学研究者、新聞社、その他さまざまな業種の会社の幹部が名を連ねている5。仮設のイベント会場とは思えないほど立派な建物や、そこに所狭しと並べられた物産やジオラマからは、こうした来賓たちに、50年の開拓事業の成果を誇示しようという意気込みが伝わってくる。しかし同時に、「拓殖・教育・衛生館」に設けられた、アイヌの案内で北海道を視察する黒田清隆像(fig. 5)や、「林業館」の熊の展示(fig. 6)に目を向ければ、背景の「深林」まで含んだ等身大の模型や剥製による大掛かりなセットを組んでまで、北海道の、内地とは一線を画す異質性、ひとことで言えば未開性を強調しようとしているようにも思われる。こうしたことから、この時期の北海道の博覧会には、山路が指摘したところの「豊富な資源の供給国」として、すなわちフロンティアとしてのふるまいと、すでにほかの地域にも「伍していける」近代化された日本の一部としてのふるまいが、同じ博覧会において共存していたといえる。言い換えれば、外地であり続けることと、内地化されたすがたを見せることを同時に達成しようとする表象の二面性が、そこには潜んでいたのである。


5.スペクタクル化と凡庸化、そして雪像へ
大正~昭和前期に大きな盛り上がりを見せた北海道の博覧会だが、戦後に入ると、少し状況が変わってくる。たしかに、開道50年のつぎの節目である開道100年の年、1968(昭和45)年にも、再び大掛かりな博覧会が開催されたことは事実である。しかし、50年博ではたとえば穀物の標本や農具など、当時の農業の実態を直截に示す資料が展示の中心を占めていたのに対し、100年博の折には、「20年後」の農林水産業を展望するという趣旨で制作された、近未来的なジオラマが目玉として登場する。安っぽいSF映画のセットのような、どこかキッチュなこのジオラマは、海中輸送システムや農作業の完全自動化など、「20年」という案外短期的なスパンで見据えた未来としては非現実的な、ヴァーチャルな北海道を観客に提示する。そのほか、モーターショーや宇宙開発関連の展示など、もはや北海道とは直接関係のない企画も多くあり、全体として過去を検証/顕彰することよりも、未来を(いささかファンタジックに)思い描くことに重心を移したその展示構成は、「風雪百年、輝く未来」というこのときのキャッチコピーにも端的に表れている。もちろんこうした趣向は、同時期に開催された大阪万博なども思い起こせば、高度経済成長期という時代背景を受けた全国的な流れに沿うものだったのだろう。また50年博の段階でも、日本の名所を再現したミニチュアの(といっても人間が歩き回れるサイズの)「東海道五十三次」という一種のアトラクション、演芸館での多数のプログラム、売店など、集客のための娯楽的な要素はすでに見られた。だが、100年博に至って、その傾向には一層拍車がかかり、従来博覧会の中心となってきた歴史的検証や実態調査にもとづく展示―それらにはもちろん、政治的意図が反映されていたとしても―が、上記のとおり、もはや会場に居合わせた観客が刹那的に楽しめればそれでよいという「ショー」の様相を呈していく。加えて、もともとは付録的な位置づけだった娯楽プログラムの方も100年博においては肥大化していった感が否めない。たとえば100年博では、会場の三分の一を遊園地が占めたという。端的に言えば、博覧会はスペクタクル化していったのだ。
しかしスペクタクル化の道を辿りはじめた博覧会が迎えるのは、皮肉にも、凡庸化という結末である。未来志向のショー、商品や新技術の宣伝を兼ねた企業協賛型の展示、娯楽要素の強化が押し進められた結果、そこで立ち現れてくるのは、もとより外地と内地のはざまで葛藤する北海道ではなく、もはやいかなる北海道でもない。見せる装置としての博覧会というメディアの形式だけがアンバランスに肥大化した結果、見せられるはずの北海道は、形式の横溢に呑み込まれて消失してしまったのだ。つい最近迎えた150年の節目に、もはや博覧会自体が開催されなかった、あるいはできなかったのは、このことを暗示しているのかもしれない。では、開道から100年が経過し、良くも悪くも均質化された地方のひとつとなってしまった北海道には、日本近代史上の特異点としての表象は必要なくなったのだろうか。そうではない。博覧会的な北海道表象は完全に消え去ったのではなく、戦後発展したもうひとつの祝祭の場、「雪まつり」に伏流していったのではないかと私は考える。
「さっぽろ雪まつり」は1950年に地元の中高生たちによって始められたが、その後の観光ブームの後押しも受けて、今や北海道の冬の一大イベントとなっている。とりわけ、大通公園の区画ごとに出現する大雪像がその見どころだが、「ヴンダーカンマー」展にも模型を出品した過去の作例のなかには、世界の名所・名建築シリーズとでも呼ぶべきものがあった。たとえばそのひとつ、2006年の「ハッピー台湾」(fig. 7)を、前節でみた開道50年博のパヴィリオン・台湾館に重ねる解釈は、恣意的に過ぎるだろうか。1918年の時点では、同じ植民地として北海道の博覧会に展示された日本統治下の台湾は、それから88年の時を経て、無害化された国際交流のシンボルとして雪まつりに登場したのだ。ただ、ここで重要なのは、二つの台湾像のあいだに横たわっているのは、時代や政治的状況の違いだけではないということである。

1918年の台湾館は、建物それ自体が植民地・台湾のシンボルであると同時に、展示施設でもあり、観客は中に足を踏み入れ、台湾にまつわる陳列物を見学することができた。そこには、実際に、台湾から持ち込まれた品々、つまり(ほんの断片だとしても)本物の台湾という中身があったのだ。すなわち、博覧会場という大きな展示空間のなかで見れば、パヴィリオンの建物が台湾を指し示すシニフィアンであるとともに、その内部のもうひとつの展示空間には、指し示される意味内容であるシニフィエが包み込まれていた。一方、大雪像のハッピー台湾にはまず中身がない。いやむしろ、中までぎっしりと雪が詰まっている。それに対して外観は、台湾の有名な建築を象っている点で、博覧会のパヴィリオンと同じシンボルとしての機能を負っているかに思われる。だが、その造形が精巧であればあるほど、再現性が高まれば高まるほど、奇妙なことに、雪像は自らが雪の塊であることをますます露わにする。
博覧会という展示空間は、北海道内の産業の紹介のみならず、内地の都道府県や台湾をはじめとする他の植民地のパヴィリオンを並べることで、政治的かつ地理的な布置関係(Konstellation[独])において北海道を浮かび上がらせようとした。同じ大正から昭和前半にかけての時代、日本各地で多くの鳥瞰図を手掛けた吉田初三郎による北海道図においても、道内各地が緻密に描かれているのはさることながら、はるか遠くに樺太や朝鮮が認められることを思い起こしてもよいだろう(ただし北海道鳥瞰図において、残念ながら台湾は、南から北を臨む視点の関係上描かれないのだが)。したがって、台湾のパヴィリオンはそれ自体としては台湾のシンボルだが、北海道の博覧会場という布置関係に置かれることで、間接的に北海道の表象を構成する一要素として機能することになった。一方、雪まつりという展示空間は、一見すると博覧会にも似て、雪でできたパヴィリオンで構成されているように思われる。しかし、雪像というのは、実はそれが外観を象っているところの対象を指し示すことにその意義があるのではなく、だから雪像のテーマはなんであってもよい。実際70年におよぶ雪まつりの歴史を紐解けば、第1回のミロのヴィーナスに始まり、横綱大鵬のようなその年の人気者(1962年・第13回)、人類の月面着陸(1970年・第21回)のような歴史的出来事、さらに1990年代以降はアニメキャラクターの増加など、時世や流行を反映した、要するに節操のないテーマ設定が行われてきたことがわかる。ハッピー台湾のような世界の名所・名建築シリーズは1970年代後半から定番化したようだが、選ばれる地域やモティーフはさまざまで、博覧会のように北海道との必然的な関連性があるわけではない。つまり雪像にとっては、何を再現しているかではなく、雪の像であるというまさにそのことこそが重要なのである。現実的な布置関係に基づいた、あるいは鳥瞰図的な表象がスペクタクル化の果てに凡庸化して終局を迎えたあとで、それに取って代ったのは雪像だった。なぜなら、雪像はそれがどんなモティーフであろうと、雪の塊である限りにおいて、直截に北海道を指し示すからだ。
6. 雪辱のオリンピック―スポーツの祭典の傍らで
雪が新たな北海道表象となった、などというと、あまりに短絡的かつ素朴な関連づけだという誹りを免れないかもしれない。ここでは、「ヴンダーカンマー」展でも取り上げたもう一つの重要な祝祭に言及しつつ、議論を補っておきたい。
スペクタクル化が頂点を極めた1968年の100年博の4年後に開催されたのが、札幌オリンピックだった。これはアジア初の冬季五輪であるとともに、札幌にとっては、1940(昭和15)年には戦争で、1968(昭和43)年には投票で敗れ、実現が叶わなかった過去の雪辱を果たす機会でもあった。また、オリンピックの開催地に決まるのと前後して、急激に増加した札幌の人口は、1970年には100万人を突破、これにあわせて地下鉄開通をはじめとしたインフラ整備も推し進められ、全国屈指の大都市に成長する。「開道」からわずか100年で、まさに開道50年博をその起爆剤のひとつにしようとした「将来(の)益々本道の拓殖の促進」が見事に実現したわけである。しかし近代化の達成とは裏腹に、このころから北海道表象のあり方はその近代化が克服しようとした当のものであるはずの異国性や未開性を、むしろ強調する方向へと舵を切ったように思われる。
言うまでもなく、オリンピックはスポーツの祭典であるばかりではない。それは、近代オリンピックの父クーベルタンが古代の精神を引き継いで構想した芸術競技(のちの文化プログラム)の存在という意味においてでもあるが、もっと身も蓋もなく、開催地の観光振興の絶好の機会であるということだ。札幌オリンピックの折にも、さまざまな観光パンフレットが流通しており、「ヴンダーカンマー」展でもその一端を紹介した。そこで目を引くのは、雪まつりの大雪像を背に、振袖姿でたたずむ女性の写真を使った絵はがき、現在も主要な観光名所のひとつである羊ヶ丘で、羊の群れを背景に、柵に腰掛けて笑顔でとうきびを頬張る女性たちが表紙を飾る「国際観光都市さっぽろ」パンフレット、「日本の北欧」と銘打って「雪と味覚と温泉」に焦点を当てたパンフレットなどである。「風雪百年」に耐え、せっかく念願の近代化を成し遂げた札幌/北海道が、しかし国際的な脚光を浴びる機会に打ち出したのは、やはり雪であり、そしてのどかな牧場風景であり、食べ物や温泉なのだ(ただし羊ヶ丘の向こうには、すっかり都市化した札幌の街が一応写り込んではいる)。村上春樹の小説の読み解きに仮託して、北海道をめぐる負の近代史の隠蔽を暴いた春木晶子の言葉を借りれば、これらは「ナチュラルでピースフルなポジティブイメージ」6であり、たしかに50年博に登場した「アイヌに案内される黒田清隆」像の無骨さを思い出せば、異国性・未開性の強調というベクトルは共有しつつも、すっかり軽やかで明るいイメージに変貌を遂げているだけにかえって欺瞞的である。雪まつりの雪像、加えて冬季五輪の開催で否が応でも再び強調される雪、そして雪に乗じて自然や気候や動物や食にまつわる無害なアイコンが、新たな北海道表象の定番となっていく。テクノロジーによる近代化の称揚と非近代的な素朴さの礼賛―一見、相矛盾する二つの態度の宥和は、ジェフリー・ハーフがナチス・ドイツのイデオロギーを論じる際に呈示した「反動的モダニズム」の構造にも通ずるところがある7。ただし、北海道表象をめぐる問題においては、それが扇動的な政治運動にまで高じたわけではない点でまだマシと見るか、むしろ消費文化という、言ってみれば軟派な位相に吸収されて人口に膾炙したぶん慎重に吟味すべきか、議論の余地はあるだろう。
さらに補足すれば、この手の北海道表象はちょうど札幌オリンピックの頃を機に、映画やテレビへとその舞台を移していく。ここでは個々の作品に細かく立ち入ることはしないが、1970年代〜1980年代初頭に製作された山田洋次の『家族』『遥かなる山の呼び声』『幸福の黄色いハンカチ』といった映画、1981年からテレビ放映が始まった倉本聰の『北の国から』シリーズ、ドキュメンタリーであるもののどこかフィクショナルな設定で、おそらくそれゆえに人気を博した『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』など、北海道に、雪国・北国、美しくもときに猛威を振るう大自然と共存する土地、駆け落ちや敗走の終着地、外国のような場所、動物の楽園といったイメージを定着させることに一役買った映像作品には枚挙にいとまがない。大石和久が、北海道で撮影された複数の映画を詳しく論じながら指摘したように、こうした表象は、北海道自身というよりは、「内地」の側が戦後日本社会において自らのアイデンティティを確立するためのうつし鏡として、「憧憬と侮蔑の大地」を必要としたことで生み出されてきたと解釈できる8。
ただ、注意しなければならないのは、こうした二面性は、本稿で見てきたとおり戦前の博覧会にもすでに内包されていたのであり、はたして北海道は、ただ鏡として、内地からまなざされるだけの受動的な立場にとどまり続けてきたのだろうかという点である。あるいは、「北海道」や「内地」と、場所を指す言葉で表現するときの、ではそれを実際に引き受ける主体は誰なのか、と問うてもよい。さしあたって個々の局面では、北海道の主体は北海道に住んでいる道民であり、内地の主体は内地から北海道をまなざし、そうして北海道にやってきた人間を指すだろう。山田洋次も倉本聰も畑正憲も、(揃って東大出なのは偶然かもしれないが)内地からやってきた人たちだ。しかし、問題の核心は個々人の出身地や居住地ではない。個々人の属性がそのまま単純に場所を引き受ける主体性を決めるのではない。そうではなく、北海道は、内地から特定の枠組みでまなざされるたびに、そのまなざしを自らも内面化してきたのであり、反対に内地は、北海道をまなざすことを通じて、北海道に同化してきたのだ。これにはもちろん、台湾をはじめとするかつての海外植民地と北海道とでは、住民の構成が大きく異なることも多分に寄与している。あるいは沖縄と比較してみてもよい。北海道にはアイヌという先住民族がいた/いることはたしかだが、明治以降に開拓が進められていくなかで、内地から移住した和人が圧倒的多数を占めることになり、戦争を経て手放されることも、一時的に日本以外の国に接収されることもなかったため、「外地」であるという感覚はもともと相対的には希薄で、そして薄れるのも早かっただろう。加えて、「北海道―内地」という構図は、「日本―欧米諸国」あるいは「アジア諸国―日本」という構図とも相似的である。北海道をまなざす内地の人は、他方では欧米諸国からまなざされる極東辺境の日本人としてふるまう。北海道に暮らす道民も、ときにアジアの先進国日本の住人として、後進国とされる他のアジア地域をまなざす。私個人が道産子かどうか、北海道に居住しているかどうかという問題とは別に、近代以降の日本人が集合的に共有してきた、こうしたまなざしとふるまいの多層的な往還が、私を内地の主体にすると同時に、北海道の主体にもするのだ。
むすびにかえて―まなざしの消失した展示空間で
張小船(Boat ZHANG)と小林耕二郎の二人によるrow&rowは、「ヴンダーカンマー」展の「祝祭」のパートにコラボしてくれたアーティスト・ユニットである。中国と日本という自らの出自をめぐる問題意識や体験をベースにしながら、博覧会、雪まつり、オリンピックというこの章のトピックに独自の解釈を与えたインスタレーション《ハマナス and オオハンゴンソウ/浜茄子 和 大反魂草》(fig. 8)は、北海道における主体性の問題への鋭い批判であるとともに、今になってみれば予言的でもあった。

たとえば、作品の一角を占める小ぶりな展示ケースの中には、ごく小さな紙片の植物がいくつか並べられていた。全体のタイトルにもある「ハマナス」と「オオハンゴンソウ」の姿もそこにある。作家ステートメントではこう述べられている。
例えば、植物の世界。
外来種が、在来種のいる土地にすっかりなじむことを人間は『帰化』(naturalization)と名付け、外来種が、新しい土地で領地を確保することを『侵入』(colonization)と名付けます。
在来種(native)とはなんですか。外来種(よそ者、エイリアン、侵入種)とはなんですか。
競争以外で一緒にいるには?
在来種にとっての外来種は、もともと彼らの土地では在来種だったのだし、彼らはあなたかもしれないし、あなたは私かもしれないし、私は彼らかもしれない。
私たちは、外来種でもあり在来種でもあり交雑種でもある。
私たち自身それぞれの立場から、一方のメンバーは「ネイティブ」、もう一方のメンバーは「アウトサイダー」でもありえるし、そして二人は北海道の部外者かもしれない、だけど他者と一緒にいる方法を想像しています。何度も何度も。
「ハマナス」は、北海道の花に指定されており、『しれとこ旅情』(森繁久彌・作詞/作曲/歌、1960年)や『網走番外地』(高倉健・歌、1965年)など往年の歌謡曲にも歌われ、今では六花亭の包装紙でもおなじみである。一方、「オオハンゴンソウ」は、明治期に観賞用として日本にもたらされた外来種で、帰化植物として広く分布したが、現在では在来種への影響を懸念して駆除の対象となっている。生物学的観点からいえば、もちろん種の多様性の保存は重要であろう。しかし、二人が問うように、在来種と外来種は立場に依存した概念である。また、帰化と侵入の線引きも難しい。人間の手で持ち込んでおいて、予想を超えて繁茂しはじめると駆除されるとは、理不尽な話である。そしてすべての関係項は交換可能であり、重複可能でもある。つまり、「彼らはあなたかもしれないし、あなたは私かもしれないし、私は彼らかもしれない」というどっちつかずの潜在性を、私たちは北海道の主体として、また内地の主体として、引き受けるべきなのではないか。
また別の一角には、コミカルな映像作品があった。1972年のオリンピックの実際の記録に残された、フィギュアスケートの実況中継が響くなか、稚拙なカップルのアイスダンス演技を繰り広げるのは、やはり紙製のハマナスとオオハンゴンソウである(マグネットを仕込んだ花の紙工作が、アイスリンクに見立てた板の下側のマグネットを動かすことでくるくると操られる)。実況に混じって、時折挿入されるのは、トワ・エ・モワの『虹と雪のバラード』、ただし、オリジナルの歌唱ではなく、いま現在、札幌市営地下鉄で電車到着ベルとして使われているメロディである。札幌オリンピックへのオマージュともいうべきこの作品のタイトルはしかし、《さようなら、オリンピック》。本稿前編の冒頭で述べたとおり、開幕から間もなく未知のウイルスが忍び寄り、混乱のうちに突然の終幕を迎えたこの展覧会の現場では―私を含む美術館側のスタッフ以上に、開幕を見届けてすぐ上海に帰る予定だったBoatさんを取り巻く状況はもっと複雑だった―ついぞその「Good bye」の真意を尋ねることができなかった。ただ、それからほどなくして、1972年札幌とは別のあるオリンピックに、しばしの別れが告げられたことは周知の事実であり、それがさらに今生の別れになるのかどうか、私たちはいま固唾をのんで(いないかもしれないが)見守っている。
さて、本来ならば展覧会の図録にでも書くべきことを、低予算ゆえ図録が作れなかったことを言い訳に、1年も経ったいま書き終えようとしている。
博覧会、雪まつり、オリンピックという軸を辿り、北海道の「祝祭」とは何だったのかということをあらためて考えると、それは「展示」の場だったということができる。地域に根づいてきた祭りや行事というのは、本来、その地域の人々のためのものであり、誰かに見せるためのものではなかった。それを外部の人にまで披瀝するようになったのは、やはり観光という営みが一般化する過程においてである。国鉄のキャンペーン「ディスカバー・ジャパン」の名のとおり、もともと存在しつつも、ひっそりと隠されていた地域が、発見されていったのである。
ただ、北海道では少し事情が異なる。明治の初めに名を与えられ、それ以降の時代に直接接続する過去を持たない北海道では、祝祭は共同体の歴史に遡及するものではなく、いまここで、自分たちに、そして他者に、見せることによって寿ぐものだった。それは、たんに北海道の形成期が観光の時代と重なったからというだけではない。私たちが新しい名の実体をつかみ、自らのうちに思い描く(vorstellen[独])ために、その表象(Vorstellung[独])を欲したからであり、それはまずもって展示(Ausstellung[独])をつうじて得られるものだったからである。絵画や写真、映像でも、もちろんそれは可能であり、その一部には本稿でも触れた。しかし、譬えるならば、生まれた子どもの成長を、とりわけ幼少期はお七夜、お宮参り、お食い初め、初節句、初誕生、七五三などと、なにかとお披露目しては確かめるように、誰かが、その場所で、誰かに見せるという臨場の機会としての展示空間が、近代日本に生み落とされた北海道には必要であり、また北海道そのものが展示空間として形成されることになったのだろう。
北海道をめぐる表象は、幸か不幸か功を奏して、おそらく日本の他のどの地域にも勝るぐらい、「北海道らしさ」というものを私たちに植え付けてきた。実際のところ、雪といっても冬の終わりに道端に積層した塊などは、排気ガスにまみれてとても美しいとは言えないし、みなが「ルールルー」とキタキツネと交信できるわけでも、どこもかしこもラベンダーで覆われているわけでもない。そうした表象は歪曲や欺瞞に満ちている。けれど、その歪曲や欺瞞の向こう側に、「本当の北海道」や「偽りのない北海道」を想定することこそ、実は欺瞞に満ちているのではないか。「らしさ」の露悪的な糾弾とはく奪は、牧歌的な理想化とは正反対の方向から、しかし北海道の形而上学化という同じ陥穽にはまりはしないか。札幌オリンピックからさらに半世紀を経て、いまや完全に広告代理店の掌上で繰り広げられているかのような、数々の祝祭のなれの果てにはたしかに嫌気がさす。でも、それらをかなぐり捨てたとして、そこで出合えるのはどのような北海道なのか、そもそもそれは北海道と呼べるのか、私にはまだよくわからない。いささかの不謹慎を承知で言えば、ウイルスのおかげで、一時的にまなざしが消失した展示空間に、なんらかの変化が兆すことを、少し期待している。
松山聖央(武庫川女子大学生活美学研究所)
脚注
- 北海道庁編『開道五十年記念北海道博覧会事務報告』大正9年、1頁。本引用では、漢字の旧字体は新字体に、カタカナはひらがなに筆者が改めた。
- 北海道拓殖部編『北海道移住案内第5』、1897年。
- 山路勝彦『近代日本の植民地博覧会』、風響社、2008年、147頁。
- 佐藤真名「さっぽろ閑話「大正7年の博覧会と札幌の都市発展」(https://www.city.sapporo.jp/kobunshokan/kankobutsu/documents/h29ronkou2.pdf)、URL最終確認は、2021年3月19日。
- 北海道庁編、前掲書、715-726頁。
- 春木晶子「あなたに北海道を愛しているとは言わせない(前篇) 『羊をめぐる冒険』をめぐる冒険」(2020年10月23日公開)および「同(後編) 「世界の終り」とナチュラルピースフル・ワンダーランド」(2020年11月20日公開)、『ゲンロンα』、ゲンロン。
前編:https://genron-alpha.com/gb054_05/、後編:https://genron-alpha.com/gb055_05/(いずれもURL最終確認は2021年3月19日、ただし無料公開は一部のみ) - ジェフリー・ハーフ『保守革命とモダニズム:ワイマール・第三帝国のテクノロジー・文化・政治』、中村幹雄、谷口健治、姫岡とし子訳、岩波書店、2010年(原著は1984年刊行)。
- 大石和久「北海道と映画―北海道の表象とそのアイデンティティ」、『開発論集』第75号、北海学園大学開発研究所、2005年。なお、大石はこの論考のなかで、映画にみられる北海道の表象を、「換喩的表象」と「隠喩的表象」に分類して分析している。修辞学者・佐藤信夫による有名な説明にあるとおり、「換喩」とは「赤ずきんちゃん」型の比喩で、その対象の一部(=赤ずきん)が全体(=この少女という人物)を表象することを指す。一方、「隠喩」は、「白雪姫」型で、この姫の肌の白さと雪の白さの類似に基づいて、「白雪姫」と命名するような表象である。大石は、換喩的表象の成功例として、黒澤明の『白痴』をあげ、とくにその「雪塊」の表現に注目する。「雪塊のみを枠取り、映像として示すこと、それ自体は、北海道をステレオタイプのイメージに閉じ込めるような換喩的表象にすぎないだろう。[中略]」しかし、黒澤明は『白痴』の中で雪塊の物質的な無表情から最大限の「表情」を引き出し、それを原作の理念の象徴にまで昇華させたのだった」と評価している。本稿で、雪まつりの雪像が、新たな北海道の表象になったと主張するとき、この表象構造はまさに大石の言う「換喩」である。これはひとつの想像だが、最初期の雪まつりにおいて、学生たちの手づくりで出現した「ミロのヴィーナス」などには、もしかすると黒澤映画に匹敵する表情があったのかもしれない(この写真は現在でも雪まつりの公式HPで見ることができ、粗削りな造形のなかに鬼気迫るものを感じさせるのだ)。しかし、その後、モティーフの再現性の点ではどんどん洗練されていった雪像は、反面その表情を失い、ステレオタイプに陥っていたといえるだろう。また、先に紹介したパンフレットのうち、「日本の北欧」と表現していたものは、大石のいう「隠喩的表象」に該当する。