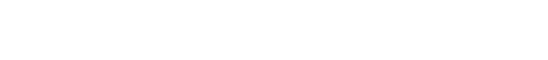美術家 端 聡(はた さとし 北海道出身)の「平面作品展」(6月25日~7月18日、CAI現代美術研究所/CAI02)を訪れた。
作品との邂逅により現れる幻影ともいうべきものをそぞろ歩いて得た私感を記す。

裏通りに面した古びたビルの入り口から地下2階へと続く階段を降りると、両脇に頑丈で背の高い鉄の扉がある。開かれた扉の向こうには、地下とは思えぬ高さを持ち四方を囲むコンクリートブロックの壁、頭上に太い鉄釘や張り巡らされた金属管、至るところには湧き出る錆色が、見える。作品の背後となるための白い壁や上方からの照明と機材が設けられているので展示空間なのだとわかるが、展示された作品に用いられている色はこれらとほとんど変わりがないので、まるで展示空間全体が展示であるような、あるいは作品であるような錯覚を覚える。逆に、時を経た壁や静止した金属類に光を発する照明と、展示された作品は遠目にも同じ表情をしているので、これらが――素材への傾倒、時の経過と静止する物質、光への志向が――空間全体から受け取られる。制限された素材の使用、絶対的な時の経過、あらゆるものが静止した様、そして静かに焚かれる灯明を思わせるこの場所は、さながら巨大な墓あるいは石棺の中の玄室に足を踏み入れたなら感じるだろうと想像するような空気がすでにある。空間全体、そして画面全体から漂う圧倒的な静寂の中、まず目に入るのは、白と黒、透明、褐色や錆色、色のない写真に鉄そして文字。



作品の表面は、さらりとした一枚皮の表面というよりも物質の厚みで覆われている。わずかな色と素材の質感を纏った物質は、個々に混じり合うことなく別々の存在感を放ち、それぞれ自体が何か固有の意味を物語るように見える。けれども作家は、「ただそうすることが心地よいから」「格好いいと思って」と、無心に素材を載せると言う。心が作家に、あるいは手が作家に命じるままに。表面にある物質の厚みは、まるで何もかもを覆い沈める滑らかに光る黒であり、まるで時の経過に万物が錆びゆく様を映した鈍色であり、まるで物質の記憶が積み重なって却って色を失った白である。そんな風に、色や質感にこちらから語りを付与してしまう存在感。そして厚みはしまいに、風景を、森を、世界も歴史をも覆い尽くしている。多くの作品に見られる表面の外側に盛られた透明な厚みは、視覚に対して奥行きを創り出すだけでなく奥にある物質を氷結させて見せ、どんなに表面の外側――作品の外側――が変化し時が経過したとしても、奥の物質は静止したまま、閉じ込められた瞬間の姿を明らかにさせている。却ってその厚みが厚ければ厚いほど、奥の物質が安定して静止をし、そのままの姿を保ち続けていられるとの願いあるいは不安が込められているかのように。

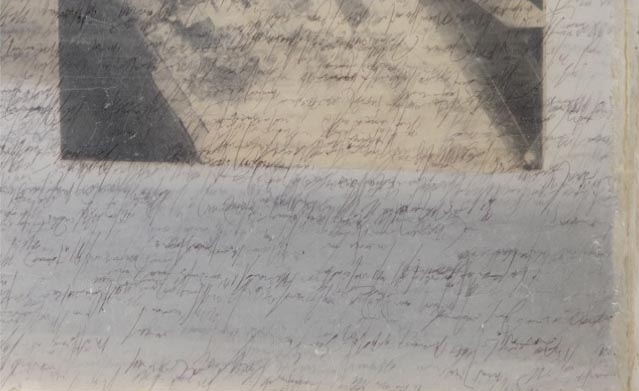
ときに表面の透明な厚みは増し何層にも重なり、層ごとに流れる時をも静止させようとしている。各々の時を語る風景の写真や古びた手紙の一葉を共に閉じ込めながら。強大な力で流れる時は分厚い氷で結晶させるだけでは足りず、その姿を留めるため覆うようにも見えるのは、特徴的な「アルファベットの鏡文字様」の線模様だ。等間隔で並べられた同様な線形状のパターンの反復は、何かしらの意味を持った「知らない国の文字」にしか見えないが、これがなんであるかは作家にもわからないと言う。以前から作品に文字を――意味のある文字を――取り入れてきたが、レオナルド・ダ・ヴィンチ文字を模写したり引用したりしているうちに傾斜は逆になり、意味や内容もわからないまま、自動書記的にスラスラとまるで宇宙と繋っている感覚で、「宇宙と繋がっていることに感謝、世界のありとあらゆるものに感謝、芸術に感謝、創造に感謝、肉体に感謝、自分という存在に感謝、…等々、いろいろな事柄に感謝や『ありがとう』をつけながら」手を動かしているのだと。こうした感謝の念を込めて綴られた知らない国の文字ならば、それは轟々とした時の流れを静止しようと意図したのではなく、あたかもそれを穏やかな音楽に――たとえば静かに神を祈るバッハの調べに――変えようと試みているかのようだ。感謝の祈りを宿す護符号、楽譜とでも言い得るだろうか。
また何点かの作品には、厚みある表面を遮って無造作に画面上に出現したかに感じられる中間の繋がった二つの塊が見える。それらの塊は作家の創造の痕跡、身体の痕跡を映すものに他ならないが、それとは別に塊自身の意図でそこに存在しているかのように、ときに動的に、ときに静かに画面に現れている。静謐の占める展示空間の中で唯一それらの塊は意思ある生命を感じさせ、いまその瞬間にも脈動をはじめるかの様な魂を秘めている。



二つの塊はいくつかの作品の表面に現れて、画面内の空気をあるいは重力を視覚化しているかのようだ。ある場所では浮かび、ある場所で沈み、あるときは蜜の粘度を保ってへばりつき、あるときはさらさらと流れ落ちる。時間は歪み、あるいは逆行する。塊はブリッジのようなもので繋がれているが、幅は狭かったり近接していたり、途切れそうであり離れている。見たことのないものであるはずなのに、どこかで出会っている気がする。馴染みのないものであるはずなのに、何故か、古くから見知ってさえいる感じがする。作家に問うと、「宇宙…いろいろな言い方があるけれど、そこと現世がつながっている」という答えが返ってきた。最初は楕円のような不定形のものが「にょろっ」と繋がっているフォルムが頭に浮かび良い感触を得、最近では上下でも左右でも良い感じだと思う、はじめは上下の繋がりだったので何か天と地とが結ばれているのかなと思ったという。「その頃、ちょうど空海の曼荼羅、真言密教に関心を持った。仏と生身の人間の関係性を説いた哲学に惹かれたのである。感覚的ではあるが空海の語るこの世と仏の世界の関係性、要するにこの世と仏の世界は繋がっており我々現世の人生とは物質世界の摩擦や困難を体験し魂の覚醒を求めつつ、この現世で成仏する、悟ることこそ魂の最大の学びであると言う哲学だ。先に述べた通り感覚的ではあるが、二つ繋がる塊、形状に対して私の何処かで腑に落ちるところがあった」、と。
塊の背景には、「仏と生身の人間の関係性」あるいは「空海の語るこの世と仏の世界の関係性」に対する「哲学」、いうなれば世界に対する理解があった。作家の言葉に従いこの理解を繙けば、「この世と仏の世界は繋がって」おり、「この世=我々現世の人生=この現世」では、「物質世界の摩擦や困難を体験」する。そこで同時に「魂の覚醒を求め」ることによって、「この現世」での「成仏」あるいは「悟り」がなされる。そして「現世での成仏」が、「魂」にとって「最大の学び」だという。「感覚的にではあるが」と作家は述べるが、こうした哲学を抱きながら創造活動に向かったならば、複数の作品に見られる「二つ繋がる塊」の形状はどこかその哲学と共振し、「腑に落ちる」との表現そのままに作家の脳内へ創造を行う体内へ、そして画面へと沈着したのだろう。
展示に目を戻し、物質世界を映す厚みある表面を、宇宙とつながる感謝の文字を、体験するこの世と悟りを経た仏の世界からなる二つの塊を、そのようなものとして眺めてみる。するといずれの作品にも、人間や世界の在り方を描こうとする眼差しが見えはじめる。たとえば、二つの塊の描かれ方や背後――現れているどの場合でも二つの塊の姿は異なり、背後に描かれている画面の世界もそれぞれ異なっている――との関係を問うと、「素材も違うし、使っているモチーフも違っています。多分、それは国が違っても民族や人種が違っても宇宙と現世のつながりは共通していると感じているのです」としている。塊の様子の違いや背後の世界は人間の置かれている状況と同じく様々で、人間全体がこのつながりを経験していること、どのような背後の世界にあっても人間は同じくこのつながりを共通に持っているのだと。見たことがないものへ懐かしさは、何かつながりあるものを見たときに起こる原初の懐かしさなのだろうか。または、古くから見知っている気がするのは、へその緒でつながる母体にも現世でつながる宇宙に対してもそれらとつながっていたことへの記憶はないとしても、それらは魂や身体が無垢のまま通り過ぎてきた場所であるような、そのような場所へのすでに覚えていない記憶、予感なのだろうか。あるいは、現世で摩擦や苦悩を抱えながら覚醒を経ようとする魂には、そうした記憶が辿るべき道筋として書き込まれているのか。
作家のこうした世界理解への関心は、空海の曼陀羅や真言密教にとどまらず、人間のより深い意識の底にある全体像を求めて、神話へ、古事記へ、そして聖書へと展開する。レオナルド・ダ・ヴィンチの壁面絵画『最後の晩餐』、ベルニーニの彫刻『福者ルドヴィカ・アルベルトー二』にモチーフを採った作品には、各々の時代におけるこの現世で、今まさにその瞬間「物質世界の摩擦や困難を体験」している人間の苦悩や驚愕の表情がまざまざと描き出されている。ここに姿を現す彼ら彼女たちはまさに「魂の覚醒」を経て「悟り」へ至ろうとする途上に、ないしは「悟り」へ到達したまさしくその瞬間に――法悦の瞬間に――いる。作家は、物質世界の摩擦や困難を体験する人間を常に眼差し、人間たちにそうした体験をさせる物質世界を厚みとともに表出させ、さらにそれらを超えて魂の覚醒に至ろうとする様を顕にしようと模索する。そして最終的に意図されているのはおそらく、現世に留まり続ける魂のあり様でなく、覚醒を経ようとする魂のあり様であり、至ることのできる「魂の最大の学び、喜び」なのであろう。そのあり様はおそらく一方通行ではなく、片方からもう片方への絶えることのない志向と還元の循環を繰り返すということなのだろう。こうしたことすべての反映として、二つの塊が描かれているように見える。


モチーフが採られた元々の二つ作品はどちらも、ある劇的な瞬間を捉えている。片方は、ともに歩む布教の路にある晩餐の中で敬愛するキリストに「あなた方のうち一人がわたしを裏切ろうとしている」と宣言され「まさかわたしではない」と使徒たちが驚愕する一瞬(マタイによる福音書26章21−22節、図版11引用文献参照)。もう片方は、財産や健康を貧者への救済に充てた高貴の女性が死の淵を彷徨いながら苦痛の中で法悦を体験する瞬間(図版12引用文献参照)。そもそもはどちらも教会の祭壇の中におかれ、観る者は宗教的な文脈の中で作品と対面することになる。つまり、聖体礼儀あるいは宗教的法悦という特別な瞬間を視覚的に理解しようと。また、宗教的な意義や精神的な営みを理解すると同時に、作品により純粋な感動を与えられ、使徒たちの表情や身ぶりに示されている驚きや慄き、そして、彼女の表情や仕草に現れている肉体的な歓喜に、同じ人間としての共感と追体験を獲得する。



元々は色彩に彩られ光に包まれた二つの劇的な瞬間は、作品に移されるにあたりどちらも色が剥がれ黒く覆われている。むしろ明確に強調されたその表情からは裏切りを告げられた苦悩や驚愕が、宗教的な歓喜や肉体的な悦楽が静かに迫ってくる。どちらにも神との合一への志向を――一つは苦悩から、一つは歓喜から――読み取ることができる。黒い表面で覆われているためか、自らも巻き込まれる宗教的な臨場感を保つものとしてではなく、ある時代の遠い出来事として客観視されるのと同時に、同じ人間としての感情的な出来事として浮かび上がってくる。黒い表面は加えて透明な厚みで奥行きを与えられた上、奥にあるその瞬間の表情を氷結させているように見える。透明な厚みで与えられた奥行きはそのまま、観る者と出来事の間に横たわる隔たりであり、同時に同様な感情体験をもたらす透明の持つ透明さでもある。
さらに画面の半分以上、あるいは半分を覆っているのは、作家にとっての「物質界」を思わせる「白い表面」であり、神との合一の瞬間を「反転させた」福者の像である。片方の黒い部分が神を志向する部分であるとするなら、もう片方の白い部分ないし黒く反転した部分は、物質界そのものあるいはそこにいる人間であろう。翻ってみると、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品でも、ベルニーニの作品でも、神と人間は一体のうちに扱われた。つまり最後の晩餐で神への志向と人間の有り様が同時に一体のうちに語られ、ヴェロニカで宗教的な歓喜と肉体的な悦楽が同時に一体のうちに表された。一方で、作品ではどちらも同時に接する二つの部分、二体として現れている。これはそのまま、他の作品に見られる二つの塊を想起させる。異なる作家の手によって創作された作品であるから必然的なつながりを問うことは難しいが、なぜ一体のうちで扱われていたものが二つに分かたれなければならなかったのか。作品に即して言えば、なぜその時代一つであった塊は現代で二つになったのか。作家は、旧い時代の作品の像を現代に移し替えるとき、黒く覆い、反転した像を――一つは反転させた像そのものを、一つは色を反転させたものを――接置した。ただ当時の宗教的な文脈から分断するためという理由には留まるまい。却って、一方では当時と同様神の世界を志向する人間という連続性を発見しつつも、もう一方では我々人間は間違いなく物質界にいるのだという両輪を持つものとして世界を理解するに至ったと言えまいか。
展示された13点の作品を振り返り世界観をトレースしたとき改めて感じるのは、目に入る視覚で捉えたものと、想起されるものの間で良い意味でのズレが生じていることだ。作家が「画面に物質そのものの痕跡を残したい」と言うように、目の前には物質がある。けれどもその物質は物質そのものだけでなく、作家の手の痕跡――錆加工により時の経過を付加し、厚みある透明により瞬間の姿を氷結する痕跡――が加えられた、物質のとある姿、制限された物質の姿だ。その姿から受け取るのは、そのような物質そのものの姿であると同時に、物質に課せられた制限、つまり時の経過と氷結する像の方だ。また「色はそれぞれ特定の周波数があり、それぞれ特定の感情と結びつくので使わない。色を使わず、現象だけ描き出すことに集中している」とする言葉通り、色はほとんど用いられていない。しかし目の前の世界のどの現象も白黒のみで生成されることはない。色を使わないという時点で、またはモノクロのフォトグラフ像を用いているという時点で、白でさえすでにある生きた現象の影である。物質も現象も制限され、白と黒に収斂するとしたら、それらは物質の影だ。黒と透明で覆われた『最後の晩餐』と『福者ルドヴィカ ・アルベルトーニ』は、感情と結びつく一切の色を剥奪された上瞬間だけ氷結されているが、人によっては、目の前の物質や像だけでなく様々なことがらを思うことだろう。たとえば、元々の文脈から断たれ黒く姿を変えていることに違和感や戸惑いを覚える者。元々の作品を思い浮かべ宗教的な感覚や敬虔さが削がれたと見る者。裏切りが告げられる瞬間のドラマを、肉体の悦楽と重なる法悦の瞬間を目撃しているという自らの姿が自覚され、そのことにエロスやまたは不快を感ずる者もいるかもしれない。あるいは、元の文脈を全く知らぬまま眺めた者は、はじめて出会う像をどう感じただろう。「深く考えず、こうすることがかっこいいと思って」と言う作家の姿に通じるだろうか。これらは15世紀そして17世紀の元々の作品が引き起こした衝撃と似たものであるに加え、像が変容されたことにより引き起こされた受け取られ方の両方であるだろう。作品は、作品の外、画面の外を映し出す黒く透明な鏡になっている。オリジナルの姿から変容されている時点で作品の生命は言わば一度剥製にされていると言いうるだろうけれども、ただの剥製ならば、これだけ多くの反応を映し出すだろうか。オリジナルの姿で放つ力が大きければ大きいほど、その像を用いた姿により顕わになるのは用いた作家の力量でもある。オリジナルの印象が強く残れば、新しく創造された作品の印象が上回ることはないからだ。(たとえオリジナルについての知識がなくても、目の前の像が何かの「転用」であればそのことは様子で分かるものだ。「転用」であることをあえて前面に押し出すやり方――オマージュやパロディーなど――もあるだろう。そのときに浮かび上がるのは、新しく置かれた文脈や像を取り扱う作家の姿勢だ。) 総じて、像を用いた目の前の作品が目の前の作品として見えるのならば、それは作家の手で再び新たな生命を吹き込まれたと言うことになる。
同様に、作品上の二つの塊に対してもまた、このままの姿で見る向きと、これはなんであるかと考え何を映しているかと見る向きがあるだろう。なんであるかと考える場合でも、作家の考えを聞きなるほどと受け取りそのようなものとして眺める者と、ますますその考えについて考察を深める者に分かれるだろう。神と物質界のこうした関係性にそのまま没入できる人もいれば、その関係性に疑問を呈する者もいるだろう。たとえば、神と人間の両界が描かれているとするなら、それを眺める作家はどこに存しているのか、などと。そのようにして作品を端緒に自論を展開することになれば、やはり画面は鏡のように見る人の内面を映し出している。作品という鏡に映し出された、作品の外の世界が観る者それぞれの心に映る。人は鏡の前に立った時、注視するのは鏡に映る像であり、鏡ではない。鏡に映る像がありありと――歪まずそのままの姿で――見えるということは、その鏡が鏡として優れているということに他ならない。興味深いことはそのズレの生成、つまり目に入る視覚で捉えた物質そのものを表すことを志向する画面と、そこから想起され作品の外を映し出す鏡面の両者が、どちらが優れているというよりどちらも優れているという仕方で、目の前に現れ出ることだ。
確かに、作品を鏡とする見方は、この作家の作品に限らないかもしれない。どのような作家の作品を見る場合でも、作品の表面だけに着目して見る場合はむしろ少なく、作家のメッセージや制作の時代背景、制作史など、あるいは、芸術作品であれば必ず持つような特性のようなものを論じることができるのだろう。「自分にとっての鏡である」と感じるような作品は、もしかすると人それぞれにあるのかもしれない。少なくとも筆者にとって、この作家のこの展覧会で出会った作品は、「鏡だ」と感じるようなものであった。個人的には、「幻影」と言って差し支えないほど豊かなイメージを創出する経験であった。作品によって目の前に様々な「幻影」が現れる体験は、驚きであり感動であった。制限された色合いは過度の刺激に得意ではない精神に落ちつきをもたらしたし、世界を眺めようとする姿勢や静寂に挿す光や影からもたらされる知恵、時の流れが目に見え僅かな感情の響きのみが抽出される透明さは、自らの内面世界と呼応した。感官の与える感覚とそれのもたらす情報そして直観の声のようなものからなる自らの内面世界はおよそロジックにそぐわないのだが、幻影はそれらが具現化されたイメージの総体のようなものだ。加えて幻影を体験すればそのイメージに自分なりの表現を与えたいという思いを感じるようになる。確かに、幻影を与えてくれるような特に力強い作品に出会ったことはこれまでにもある。けれども、それぞれの幻影はあまりにも異なっているのでかろうじて幻影という言葉で括ることができるという程度にしか共通していない。またそれぞれの幻影は、自分とその作品によってのみ取り結ばれるものなので、幻影を思い起こすことと作品を思い出すことは個人的に同じ体験と言えるほど密接なものだ。今回の展示で体験した幻影は、自らの言霊をのせた詩的言語を呼んだ。まるで自分自身の内面世界を眺めるような幻影であり、自分自身の内面世界を表現する詩的言語だった。作品によって自らの内面世界が鮮明に映し出された、これが作品を「鏡面」だと呼ぶ最も大きな理由である。
したがって、見方は二つある。目の前の視覚で捉えたものに集中し物質を見るというもの。そしてもう一つは想起される像――時の経過や氷結する像、観るものの心、描くものの姿、あるいは幻影――を見るというもの。作家は何ものをも指し示さない物質そのものを描くことに成功しながら、作品は優れた鏡面として画面の外を映すとはなんと逆説的だろう。色は剥奪され、時の経過が錆と付与され、瞬間が氷漬けにされ、像は剥製にされ、制限された物質に還元された。それらから流れ出す静寂は墓のように大きく、同時に、墓の内部に描かれるはずは魂の旅の行先であるし、魂のあり方であるだろう。それらはおそらく作品の描き出すまま、映し出すままであり、または観る者の心の内に浮かぶままである。終着としての墓のイメージから、行き先としての魂の姿が描き出されるとは。神と人間界の両輪である姿はそのまま、画面にある二つの塊の姿はそのまま、訪れる者が鏡像と向かい合う瞬間そのものと見まごう。こうして、展示を訪れる者、作品を詳しく訪れる者は知らぬうちにこの逆説的な出来事をずっと経験することになる。画面に光を描こうとすれば無色となるように、色の制限は光の希求であるように。影を描けば、それは同時に光の存在を前提するように。静寂により、作家の願う希望が聞こえ出すように。次に作品を訪れる者は、どちらを見るのだろう。

なお本項に掲載されている画像はすべて(筆者撮影の部分写真を除く)、CAI現代芸術研究所/ CAI02(写真:小牧寿里氏)に提供のご協力をいただいた。この場をお借りして謝意をあらわしたい。また、3Dギャラリー「端聡平面作品展」 https://my.matterport.com/show/?m=tcm8jb3Lteoにおいて作品写真の閲覧が可能である。
伊藤佐紀(美学)
画像提供:CAI現代芸術研究所/CAI02 写真:小牧寿里
3Dギャラリー「端聡平面作品展」
https://my.matterport.com/show/?m=tcm8jb3Lteo