はじめに
少女表象をめぐる論考の中でも、澁澤龍彦の「少女コレクション序説」1は現在も影響力を持っている考察の一つである。主体性をもたず、自らは口を開くことのない語らないオブジェ、すなわち「純粋客体」と少女を位置付けた澁澤のこの言説は、これまでひたすらに純粋なものとして描かれ、また論じられてきた少女の、隠された性的な部分をあぶりだしたという点で評価することができる。戦後の少女表象には、澁澤が「少女コレクション序説」で明確化した、戦前戦中には描かれてこなかった少女のもつ性的な魅力が表象されていることは明らかであり、2000年以降の少女表象においても少なからずその痕跡を見ることができる。ゆえに、現代の少女表象を分析してゆく際には澁澤の論には触れておかねばならない。
しかし、近年、澁澤の述べたような性的な範疇に収まらない少女も描かれるようになってきた。また、フェミニズムの視点からは、少女を「語らない」存在として位置づけたこの論は、当然批判されるべきである。少女表象を分析するにあたり、フェミニズムの観点が重要な視座であるため、澁澤の論を否定的に取り扱わざるを得ないのである。にもかかわらず、澁澤のこの論説に関して批判的に論じたものは管見の限りない。本稿では、少女表象の美術史的文脈を踏まえ澁澤の論の意義を認めつつも、フェミニズムの視点からその批判を試みる。

1. コレクションとしての少女
澁澤龍彦は、1928年から1987年に活躍したフランス文学者であり小説家である。周知の通り、多数の美術評論も手掛けている。『少女コレクション序説』(中央公論新社、1985年)は、1964年から1981年の17年間に書かれたエッセイを再編し、まとめたものである。表題作「少女コレクション序説」は、その内のたった13ページではあるが、澁澤が実際にコレクションした四谷シモンの球体関節人形2を撮影した、表紙と口絵の写真と相まって強いインパクトをわれわれに与える。
「少女コレクション序説」において澁澤は、少女がコレクションとなり得る理由について独自の美的感覚でもって論じている。はじめに澁澤は、「おそらく、美しい少女ほど、コレクションの対象とするのにふさわしい存在はあるまい」3と述べ、さらには「可憐な少女をガラスの中にコレクションするのは万人の夢であろう」4とまで述べている。
澁澤は続く論考の中で、少女という存在自体が「物体(オブジェ)」5であることを強調し、人々が少女を追い求める理由について、当時の社会状況を交え、以下のように述べる。
現代はいわゆるウーマン・リブの時代であり、女権拡張の時代であり、知性においても体力においても、男の独占権を脅かしかねない積極的な若いお嬢さんが、ぞくぞく世に現れてきているのは事実でもあろう。しかし、それだけに、男たちの反時代的な夢は、純粋客体としての古典的な少女のイメージをなつかしく追い求めるのである。6
澁澤によれば、〈語る女〉は男性の欲望の対象とならないという。澁澤は、現実の女性が語り始めたからこそ、〈語らない少女〉、「物体(オブジェ)」としての少女、つまりは「純粋客体」を求めるのだと説く。
さらには、「女の側から主体的に発せられる言葉は、つまり女の意思による精神のコミュニケーションは、当節の流行言葉でいうならば、私たちの欲望を白けさせるもの」7であり、「小鳥も、犬も。(原文ママ)猫も、少女も、みずからは語り出さない受身の存在であればこそ、私たち男にとって限りなくエロティックなのである。」8と、少女を、小鳥や犬、猫と同列の語らない存在と位置付ける。つまり、主体性を持ち、これまで男性の領域であった公的な場で発言する女性、知性を持ち語る女性は、男性の欲望の対象とはならず、あくまで受身の、身体的存在として客体につとめているものだけが欲望の対象となるのである。少女は、主体的に物事を述べることのない、純粋無垢で安全な存在であると考えられているからこそ、欲望の対象として都合よく機能するというのが澁澤の見解である。
もちろんこれは、澁澤独自の見解であり、現代のフェミニズム的視点においても反論の余地が十二分にあることは言うまでもない。語り出す女性が、欲望の対象とならず「私たちの欲望を白けさせるもの」になるという澁澤の論は、女性を男性より劣った存在であるとし、男性を脅かしかねない言葉を発する女性に対する根深いミソジニー(女性嫌悪)を孕んでいる。そこには、男性中心の古典的言説にみられるような、男性は精神的存在でありで知的で理性に富んでいるという位置づけに対し、女性は身体的で感情的であるという今日では批判の対象となる前提が横たわっていよう。
とはいえ、澁澤同様、動物と少女を同列に結び付ける論説はしばしば見受けられる。美術評論家の倉林靖は、少女についての論説をまとめた『少女論』(青弓社、1988年)の中に収録された「夢想する身体 バルテュスの描く少女たち」において、バルテュス(Balthus: 1908-2000)の描いた少女を取り上げ、その魅力について、「無限定的であらゆるものに対して開かれ、無意識的で、原始的で、本能的な魅力をそそる動物的(たとえば猫!)なものだ。」9と述べ、少女を、「猫」というもの言わぬ動物に例えている。少女の魅力は、語らずともわれわれを魅了する存在に結び付けられやすいのである。彼らにとって、犬も猫も小鳥も、そして少女も、その「物体(オブジェ)」性が強調された「純粋客体」なのである。
しかし、当然のことではあるが、実際、少女は「みずからは語りださない」10存在ではない。澁澤の論は、あくまでオブジェに対する欲望についての分析である。それを承知のうえでも、現実に存在する少女たちには当てはまらない点があまりに多く、それは男性中心に生み出された表象として批判されるべきであろう。
少女雑誌の全盛期、明治後期から昭和中期には、少女たちは自らのアイデンティティを探すため、詩や小説を書き雑誌へ投稿した。そこには確かに彼女たちの言葉がある。また、現代においては、少女たちには、情報源の普及11によって、知識量に関して大人に引けを取らず、さまざまな場で意見を述べること、自分について語ることができる。つまり、少女は、――もちろん元来からそうではないはずであるが――無知な完全客体ではない。少女たちは言語を持ち、語る。にもかかわらず、少女は「純粋客体」と見なされ、またそのように表象されてきたのである。
2. 「純粋客体」――少女表象の美術史
では、少女はいかにして「純粋客体」として描かれるようになったのであろうか。その過程をたどるため、まずは少女表象を美術史的文脈においてみてゆこう。
少女という概念は、1899年、中等教育を、男子に限らず尋常小学校を卒業した女子に対しても行えるよう、その詳細を規定した高等女学校令12をきっかけとして誕生した。これまで、主に農村地域では13歳頃を目途に女性は大人になったとみなされていた。しかし、高等女学校令の発令によって、出産可能な身体を持ちながらも大人ではない、婚約と出産を猶予された女性、すなわち少女が生まれたのである。当時まったく新しい存在であった彼女たちのアイデンティティは、当時の少女雑誌によって形成された。雑誌の投稿欄には、「純潔」にアイデンティティを見出した少女たちの投稿が目立つようになり、またその「純潔」を軸に彼女たちは団結を深めていった。しかし、先行研究には、少女たち自身による「純潔」の重要視は、単に少女たち自身の事柄に留まらず、国家が推し進めたかった「良妻賢母」の育成にちょうど一役買ってしまったという指摘もある。少女概念は、近代社会のうねりのなかで近代国家政策つまりは、国家の思惑と密接にかかわりながら形成されていったのである 13。そして、その存在の誕生以降、さまざまな媒体で少女は表象されてゆく。
高等女学校令以降に刊行され、少女たちから絶大な支持を得た少女雑誌には、さまざまな姿の少女が描かれてきた。『少女倶楽部』には、はつらつとした健康的な少女が、『少女の友』には、中原淳一に代表されるリボンやフリルを纏った儚げな少女が描かれた14。はつらつとした少女は、将来良妻賢母となるのにふさわしい健康的な理想像であった一方、中原淳一に代表されるような線の細い少女は、センチメンタルとも評される、「純潔」をアイデンティティとした少女たちによる、雑誌等における繋がりの中で夢見られた理想像であった。

また、商品広告などに描かれた少女は、きらきらした眼差しでこちらに微笑みかけている。キリンビールやアサヒビールの広告15には、いかにも従順で可愛らしい、理想的な少女が描き出されている。
さらに、油彩などの絵画の領域になると、モデルの少女を描き手が優しい眼差しで見つめた作品が散見される。白瀧幾之介(1873-1960)や霜鳥之彦(1884-1982)などの描いた編み物や読書に夢中になっているその少女16の姿には、純粋さが描き出されている。描き手の視線に気づかない彼女たちのありようは、ただひたすらに見られる存在であるといえよう。
以上、明治から戦中の少女表象を美術史的にみてゆくと、それらがいかに純粋で従順な存在として描かれてきたのかがわかる。しかし、少女表象をはじめて美術史的にまとめた展覧会、『美少女の美術史展』17の企画者のひとりである川西由里は、美術史的に少女表象を振り返り、終戦後の少女表象に、これらとはまた違った少女への視線を指摘している。それは、単なる可愛らしさ、純粋さとは異なった点をもつ少女表象である。
川西は、澁澤の「少女コレクション序説」と芸術家中村宏(1932-)が繰り返し描いた不気味なセーラー服の少女を挙げ、これらを「一般に無垢な存在とされている少女に向けた性的な眼差しを隠すことなく、不条理の象徴、あるいは欲望の対象とする動き」18であるとした。中村は、のちに述べてゆくが少女をグロテスクともとれるような描き方をしており、澁澤の述べる少女とは一見異なるようにみえる。しかし、性的な部分を意識的に扱うという点においては共通している。川西は中村と澁澤を並べ、「少女を客体としてとらえた作品は、漠然とした「憂い」ともまた違う、少女が持つ「毒」ともいうべきものをあぶりだした」19として評価している。つまり、戦後にみられるようになったのは、少女を性的に「純粋客体」として扱った表象であり、そこではじめて少女の「毒」なるものが見出されたのではなかろうか。川西はその論の中で、先にあげた一か所でのみ「毒」と述べるが、本論ではこの「毒」という言葉に注目し、それをキーワードとし考察を進めてゆきたい。(続)
山田萌果(北海学園大学大学院)
脚注
- 澁澤龍彦「少女コレクション序説」、『少女コレクション序説』、中央公論新社、1985年、10-22頁。
- この人形は1982年に制作され、展示を経たのちに澁澤の家に運ばれた。詳しくは『少女コレクション序説』のあとがき「シモンの人形」(207-209頁)を参照。
- 『少女コレクション序説』中央公論新社、1985年、10頁。
- 同上。
- 同上、11頁。
- 同上、12頁。
- 同上。
- 同上。
- 倉林靖「夢想する身体 バルテュスの描く少女たち」、『少女論』、青弓社、1988年、62頁。
- 澁澤龍彦『少女コレクション序説』、12頁。
- メディア論を専門とするアメリカのニール・ポストマンは、子ども大人の違いは情報量であったとし、現代は情報化社会によってもはや16世紀以に発見された、かつての「子ども」は存在しないのではないかとまで述べている。子どもと情報の関係性については、ニール・ポストマン『子どもはもういない』(小柴一訳、新樹社、2001年)を参照されたい。また、さらにさかのぼって「子ども」の成り立ちについては、フィリップ・アリエス『〈子ども〉の誕生―アンシァン・レジーム期の子どもと家族生活』(杉山光信・杉山恵美子訳、みすず書房、1980年)を参照されたい。
- 高等女学校令とは、女子に必要な中等教育を行うことを目的とし、高等女学校に関して規定した1899(明治32)年2月7日に公布、同年4月1日に施行された全20条からなる勅令である。高等女学校令と女学生、少女の関係については本田和子『女学生の系譜・増補版 彩色される明治』(青弓社、2012年)、渡部周子『〈少女〉像の誕生』(新泉社、2007年)に詳しい。
- 少女に関する研究は、本田和子の「ひらひらの系譜―少女、この境界的なるもの」(本田和子『異文化としての子ども』紀伊国屋書店、1982年収録)をきっかけとし、行われてきた。主な内容としては、高等女学校令の発令以降、出産可能な身体を持ちながらも婚約と出産を猶予された期間が女性に与えられた。それ以前の農村社会では、性的な成熟と労働力が備わるとされた13歳頃を境とし、子どもは「大人」とみなされた(赤松啓介『夜這いの民俗学 夜這いの性愛論』ちくま学芸文庫、2004年、大塚英志『少女民俗学 世紀末の神話をつむぐ「巫女の末裔」』光文社、1989年参照)。将来「良妻賢母」となり国に貢献する可能性のある者たちとして投資の対象となった当時の少女たちに対する言説は、男性に選ばれるために、女性に自然に備わるとされる「愛情」を持ち、「純潔」を保つこと、そして「美しく」あるべきであるといった論が中心であった(渡部周子『〈少女〉像の誕生』新泉社、2007年参照)。少女たちのコミュニケーションの場であった少女雑誌についての研究は数多くあるが、中でも、社会学者の今田絵里香は、少女雑誌における少女たち同士の繋がりを「少女ネットワーク」と呼び、その場においては「純潔」という価値観が重要視され、「純潔」であることこそが少女たちのアイデンティティであったことを指摘する。しかし、少女たち自身による「純潔」の重要視は、単に少女たち自身の事柄に留まらず、国家が推し進めたかった「良妻賢母」の育成にちょうど一役買ってしまったと今田は指摘している。以上の先行研究から明らかとなるのは、本文でも述べたように、少女概念は、近代社会のうねりのなかで近代国家政策つまりは、国家の思惑と密接にかかわりながら形成されたということである。また、このほか先行研究では、少女を近代的存在として位置づけるものも目立つ。それを主張したのは主に1980年代の少女論ブームの論者たちである。この時期の研究については、繁富佐貴「1980 年代の「少女」論の構造」(『日本女子大学人間社会研究科紀要 第15号』日本女子大学、2009年)を参照されたい。
- 『少女の友』は1980(明治41)年に実業之日本社より創刊。『少女倶楽部』は1923(大正12)年に大日本雄弁会講談社より創刊。『少女倶楽部』は、主に地方の小学校上級生から女学校下級生を読者層としたのに対し、『少女の友』は大都市の女学生を読者層としたことからも両誌の趣向の違いが理解できよう。より詳しい分析は、中川裕美『少女雑誌に見る「少女」像の変遷――マンガは「少女」をどのように描いたのか――』出版メディアパル、2013年を参照されたい。
- 参照したのは次の作品である。高木葆翠、ポスター「アサヒビール」(1930-31年頃)、多田北烏ポスター「キリンビール、キリンレモン」(1932年)(「美少女の美術史」展実行委員会編『美少女の美術史』、青幻社、2014年、164頁参照)。
- 参照したのは次の作品である。白瀧幾之介「編み物をする少女」(1895年)、霜鳥之彦「少女(休憩)」(1926年)。他にも関連作品がある。詳しくは『美少女の美術史』「お部屋で/お庭で」のセクション(青幻社、2014年、91-100頁)を参照。
- 『美少女の美術史』展は、2014年から2015年にかけて、青森県立美術館(7月12日~9月7日)、静岡県立美術館(9月20日~11月6日)、島根県立石見美術館(12月13日~2月16日)の三箇所を巡回し開催された企画展である。
- 川西由里「美人画と少女画のあいだ」芸術新聞社監修『美人画ボーダレス』芸術新聞社、2017年、49頁。
- 同上。
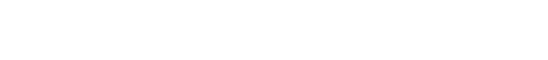

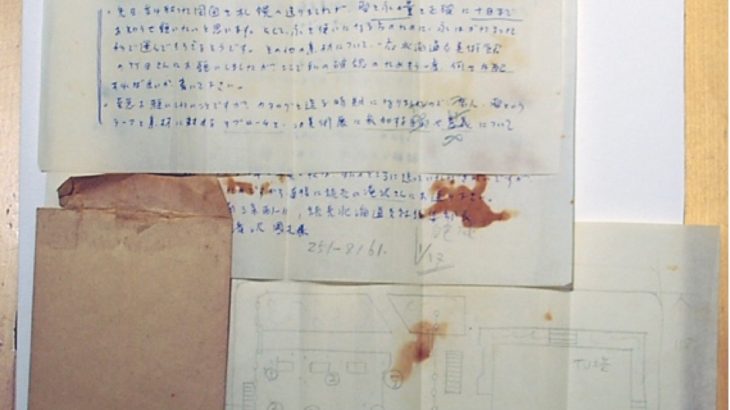


-730x410.jpg)

