*本稿は、「少女の魅力の一側面としての「毒」――澁澤龍彦「少女コレクション序説」 が戦後の少女表象に与えた影響―― (1)/山田萌果 │ Hokkaido Art Forum (hokkaido-art-society.net)」、「少女の魅力の一側面としての「毒」――澁澤龍彦「少女コレクション序説」 が戦後の少女表象に与えた影響―― (2) 山田萌果 │ Hokkaido Art Forum (hokkaido-art-society.net)」の最終編である。
6. 現代に引き継がれる「毒」
澁澤は、少女に対する性的眼差しを包み隠すことはなかった。彼が明らかにしたのは、少女の持つ「毒」である。その毒は三種類に分類できるのであった。つまり、変形した姿で悪意をむき出しにする少女の「毒」、したたかさを持ち誘惑する少女の主体性と関連する「毒」、欲望する者を観念上に閉じ込め、静かに生命力を奪う、無機質で不気味な「物体(オブジェ)」にみられた「毒」である。それらの「毒」は、女学校令発令以降の少女雑誌全盛期にみられた純粋無垢という少女のステレオタイプとは、対極にあるその不純な部分を意味していた。現代においても、その「毒」は描かれ続けている。
まず、少女の性的魅力を前面に押し出した少女表象の例としては、村上隆(1962-)や会田誠(1965-)の描く少女が挙げられる。村上の著名な作品、《Miss KO2 original》(1997)や《HIROPON》(1997)など、一連の等身大の少女のフィギュアは、欲望を刺激する性的魅力となる身体の部位が強調され、身体が変形されている点において、「毒」を引き継いでいるといえる。中村宏が描き出した「悪意」とは異なるが、あまりに巨大な乳房や長すぎる脚には、欲望する鑑賞者を戸惑わせる「過剰性」がある。同じくフィギュア作品である《3m Girl》(2011)も、同様に身体の一部が強調され、さらにはそのタイトル通りフィギュアそのものが、等身大をはるかに超える大きさである。これらの作品は、フィギュアというジャンルの通り、澁澤の述べたところの「物体(オブジェ)」そのものでもある。
また、一時物議を巻き起こした会田誠の《犬 (雪月花)》シリーズ(1996-2003)1は、もの言わぬ動物である犬に見立てられた少女が描かれている。手足を切断された裸の少女が犬の首輪を付けられ、微笑んでいるというこのセンセーショナルな作品もまた、澁澤が述べた少女の「物体(オブジェ)」性が強調されている。自ら語ることのない犬に見立てられ、手足の不在ゆえに動くこともままならない少女は、澁澤の述べた、「オナニスト的」な欲望を満たすための、ひたすらに受身の存在となる。また、この少女は不自由で繋がれた状態であるにもかかわらず、自身の性的魅力を意識的にアピールしていると受け取ることのできるポーズや表情をしている。もちろんそれは、少女が自発的に性的魅力をアピールしているという、一種の主体性があるというようにも解釈できる。
しかしながら、少女が性的魅力を自ら前面に押し出したことによって生じるように思われる、成人男性を破滅へと向かわせる危険性は初めから無効化されているのである。なぜなら、前節で述べた通り、少女は〈前女性〉であるからである。そのしたたかさは、成人男性にとって安全な存在であることはそのままに、少女を危険な香り漂う存在に仕立てるための、いわばスパイス程度のものでしかない。さらに会田のこの作品においては、少女の手足を切断し鎖に繋ぐことで、スパイスと言うべき少女の自発性に伴う、男性に及ぼす危険をより抑制している。鑑賞者は作品におけるその残虐性に、はじめは引きつけられるものの、徐々に少女の誘惑するような視線や姿勢に気づき、性的魅力を感ずるのではなかろうか。《犬 (雪月花)》シリーズは、残虐な表現でもって、少女の「物体(オブジェ)」性を示した上で、少女の持つ「毒」のうちの、「したたかさを持ち誘惑する少女の主体性と関連する「毒」」を引き継いでいる。しかし、少女の手足の自由を物理的に奪う描き方でもって、その「毒」の持つ危険性は解消されているとも言える。
さて、前節でも引用した美術評論家の相馬俊樹の論考「女性像に秘められた毒」には、澁澤に対する言及はないが、現代の女性像に描かれている「毒」について述べられている。相馬は、「日常の秩序を愚弄する〈毒〉がいざなおうとするのは労働を基盤とする世界とは正反対の世界、すなわち無益なたわむれと遊びの世界である。」2と述べ、ゆえに「たわむれ遊ぶことにしか興味を示さない少女」3は毒の世界に誘う存在として最適であると述べている。さらに、相馬は、少女と高級娼婦の類似に注目する。労働から程遠く遊びの世界に生きる存在としてこの二者は似ているのだという。相馬は高級娼婦について、「少女と同じように労働からは最も程遠い無為な生を生き、先のことには目もくれず今現在の逸楽に耽り切って奢侈を繰り返す」4のだと述べている。
まさしく、『ロリータ』のドロレスは、相馬の述べる高級娼婦のイメージと一致し、また、会田が描く少女もそのイメージを踏襲している。例えば、会田の作品《滝の絵》(2007-2010)には、美しい滝を背景に、スクール水着を着用した少女たちが異様なほど大人数集い、各々笑顔で遊んでいる様子が描かれている。少女たちのすがすがしい表情からは、なんの不安や不満も読み取れない。また「百花繚乱」を意味するタイトル《ジャンブル・オブ・100フラワーズ》(2012-)には、裸の少女たちが大勢描かれている。ゲームの中のような空間にいる彼女たちは、体を打ち抜かれている状態にも関わらず血も涙も出ず、笑顔のままである。これら二作品には、ではしゃぐ少女たちが、どこか不気味に描かれていると言えよう。
以下に述べてゆく通り、この「無益なたわむれと遊びの世界」にいる「高級娼婦」のイメージは、村上や会田の作品には当てはまるが、実際の少女たちとはかけ離れている。にもかかわらず、なぜそれらは表象において接近するのであろうか。その理由は、「高級娼婦」のイメージもまた、澁澤が述べたような欲望する主体が描き出す観念上の存在にすぎないからなのではないか。相馬の述べる「高級娼婦」の文脈からは、「今現在の快楽だけに貪欲な、自らの意思でその道を選んだ娼婦」という、欲望する主体にとって都合の良い観念上の娼婦が巧妙に描き出されている。
さらに同論考において、観念的に解釈された「高級娼婦」と結び付けられる少女は、既にみたように「労働からは最も程遠い無為な生を生き、先のことには目もくれず今現在の逸楽に耽り切って奢侈を繰り返す」と表現されていた。娼婦のイメージ同様に、ここにも少女の実際とかけ離れた観念上の像が作り上げられている。
もちろん、欲望する主体にとって都合の良い観念上の娼婦と重ね合わされた、観念上の少女は、澁澤の論同様に魅力的を持っている。また、性的魅力を通して表れてくる少女の「毒」には、純粋ではつらつとした少女という国家にとって理想的な少女には描き出されない、暗く淀んだ不健康で不純な部分に光を当て、不純な少女を表象可能としたという点において、評価できる。しかしながら、そのような部分を性的魅力に引きつけた表象によって零れ落ちてしまうものもある。それは、少女の持つ、人間として当然の苦悩ではないか。
第一節でも述べた通り、明治後期から昭和中期の少女雑誌には、少女たちの切実な言葉が投稿されているし、そこにはもちろん、自らの人生や将来に対する不安の言葉もある。当然のことであるが、少女にも悩みはある。その悩みの中には、少女以外の人間と同様に将来に対する不安が含まれている。ゆえに少女たちは、「先のことには目もくれず今現在の逸楽に耽り切って奢侈を繰り返」しているとは言い難く、むしろ、それは、少女に眼差しをむける他者が「そうであってほしい」と願う姿なのではないか。
さて、会田は、自身が1990年代に頻繁に少女を描いていたことについて「“日本”を表現するのに、少女がなんというか、合っていた時代」5と述べている。会田は、自身の描く不気味にも無邪気な少女たちに、90年代以降の日本の経済の行き詰まりをひた隠しにする様相を重ね見ていたのではなかろうか。痛みのあるはずの状況下で表面的に無邪気さを装う少女は、経済的不況にも関わらずどこかあっけらかんとした当時の世情や過剰に明るいエンタメ市場などと重ね合わされている。それは、本論で繰り返し言及している本田和子の論を火種とした1980年代の少女論ブーム6にもみられた、少女を「鏡」として時代を見る見方と通じてはいないか。
少女論ブームは、自らの少女時代を反芻しつつ女を述べた本田の論を嚆矢としたにもかかわらず、その後は主に成人男性の研究者から見た、少女の「異質」性についての論が中心となった。7児童文学者の横川寿美子は、「異質」な少女文化に迫ることによって明らかにされたのは、少女についてではなく、近代日本の特性のようなものであり、少女を当時の日本を映し出す「鏡」として論じているのだと指摘している。8それを踏まえると、会田の描く少女は、現代日本の空虚さを映し出す「鏡」の機能を果たしていることが明らかになる。
村上、会田は、「毒」の中でも、性的部分を中心に引き継いでいる。また、それらは、少女の「毒」の内、暗く淀んだ部分を中心に引き継ぎ、現代日本の暗く淀んだ部分をも捉えている。しかし、性的部分に着目すること、また現代日本を映し出す「鏡」として少女を表象することによって見落とされている点がある。それは、少女たち個々人の苦悩や主体性ではなかろうか。現代では、苦悩し自己主張する、より人間的な少女表象がいくつかある。次節では、そのような作品を中心にみてゆこう。
7.これからの少女表象
澁澤などが、少女を性的視線で捉えたことであぶりだされた少女の「毒」なるものは、もちろん少女表象の魅力のひとつではあるが、それは男性の欲望を満たすためのものとしてこれまで機能してきたのではなかろうか。近年の少女表象に目を向けると、これらの言説とはまた違った側面をもつ作品が見受けられる。それらは、澁澤の少女論にも含まれ、またこれまで明らかになった「毒」の中にも存在した、少女の不健康的な、暗い側面に焦点が当てられている。
ここで幾人かの芸術家を例に挙げよう。イケムラレイコ(1951-)、イヂチアキコ(生年非公開)、内田すずめ(生年非公開)、加藤美佳(1975-)、工藤麻紀子(1978-)、後藤温子(1982-)、黒木美都子(1991-)、コヤマケンイチ(1973-)、篠原愛(1984-)、鈴木弥栄子(1979-)、唐仁原希(1984-)、橋爪彩(1980-)、濵口真央(生年非公開)、松井冬子(1974-)、松本潮里(1973-)、村瀬恭子(1963-)など、国内外で積極的に活動している芸術家である。上記の芸術家たちは、これまで男性が描き男性が批評してきた芸術分野、特に女性表象や少女表象に新しい視点から切り込んでいる。また、それらが可能になった背景には、のちに見ていく通り、女性が芸術家として活躍し、自ら主体性を持って表現ができるようになったという社会の変化がある。

彼女たちの描く作品の少女は、可愛らしく微笑みかけることはない。むしろ、こちらを鋭い目つきで睨んでいたり、目を見開いていたりする。そこには、あたたかさはなく、冷たさがある。その冷たさは、澁澤の述べたオブジェ性を帯びているとも言えるが、澁澤の言及するような性的な魅力は強調されていない。例えば、第一節で言及した『美少女の美術史』展でも紹介された作品であるイヂチアキコの《真夜中》(2013)には、暗く淀んだ背景に虚ろな、しかし鑑賞者を強く捉える視線の少女が描かれている。彼女の肌や髪の詰めた印象を与える青みと対極に、虚ろな目の淵、少女が手にしている実、花は鮮やかな赤で描かれている。それは生と死のコントラストのようにも見える。

*本画像は『美少女の美術史展』画集(青幻社、2014年)を撮影したものです。
また、同展覧会に展示された唐仁原希の《優しさにさようなら》(2013)には、下半身が魚類の少女が車いすに腰掛けている様子が描かれている。可愛らしいリボンとワンピースを身に付けた少女の表情は暗く不満げで、しかし目はギラリと光っている。その姿はまるで、地上にいることの理不尽に耐えているようである。

*本画像は『美少女の美術史展』画集(青幻社、2014年)を撮影したものです。
先に例に挙げた芸術家の描く少女たちはイヂチ、唐仁原の描く少女同様に、暗く陰鬱な印象をわれわれに与える。少女たちは皆、不満げであり不安げでありながらも、どこかに強さを携えている。さて、少女の陰鬱さといえば、かつて竹久夢二や鏑木清方が描き出した少女の「憂い」とも関連があるようにもみえる。相馬は、竹久夢二などが描いたかつての美人画における「憂い」を微弱な「毒」であると述べている。9鏑木や竹久の描き出したのは、「憂い」、つまり、不健康とも評されてきた線の細い少女の、純粋さゆえの傷つきやすさや虚弱さである。相馬は、「憂い」の微量な「毒」に対し、現在描かれている少女には大量の「毒」があるのだと述べる。
前節で述べたように、その大量の「毒」には相馬の述べる「高級娼婦」的な側面が含まれているが、それとは異なる側面を見出すことができる。イヂチ、唐仁原らの描く少女は、先述の通り、性的な魅力は強調されておらず、また、先のことに目もくれずにいる様子でもない。また、相馬が微量の「毒」と述べた憂いを帯びてはいるものの、虚弱さというよりは、強さが押し出されているのではなかろうか。その点が、彼女らの描く少女の新しさなのではなかろうか。
芸術家本人の言葉からも分かる通り、それらの作品には芸術家自身が重ね合わされている。イヂチは、「男性作家は理想の女性美などを投影しているかもしれませんが、女性の場合同一の性であるが故に、自己投影や同調のしやすさがあ」10り、自身の作品において伝えたいことは女性美ではないと述べている。単に見られるものとして美しい少女ではなく、描かれた少女にはイヂチ自身が重ねられている。つまり、自身を重ねることで強さが浮き上がってきている可能性がある。
また、長年少女を描き続けている松本潮里は、描いている少女について、「ネバーランドに取り残されたままのもうひとりの自分でもあります」11と語り、さらに「私にとって少女像は好ましい形に自己を投影できる器であり、かつて空想の中に求めでいた「ここではないどこか」を手元に引き寄せるための装置でもある」12とも述べている。松本は「ネバーランド」と表現しているが、年を重ねても彼女が持ち続けている少女性なるものが彼女の作品には描かれている。ここではその全てを取り上げないが、多くの芸術家が、自己と少女を重ね合わせていると語っている。13自己と作品の少女を重ね合わせる芸術家は、少女期において、ただ「たわむれ遊ぶことにしか興味を示さない」14状態ではなく、生きる者として当然抱く苦悩を伴った状態であったであろう。その苦悩が、強さとして描かれているのではないか。
自身と重ね合わされ、描き出されているのは、憂鬱や不安、死への意識などの、無邪気さや無垢さと表裏一体の、影なる側面でもある。それらは広く一般的に、少女期、いわば思春期に突出して現れると考えられている。彼女たちは、社会的に生産活動を行わない保護された存在であり、ときに子どもらしさを求められる。にもかかわらず、彼女たちは、出産可能な大人の女性の身体を持ち、さらに特に現代においては大人同様の扱いを受け、多くの情報に触れている。それゆえ、身体や性に関する苦悩、家族や友人との問題など、大人同様の悩みも持っている。大人と子どもの間を揺れ動く中間的存在には、大人と子どものどちらにもまたがる苦悩がある。少女研究の第一人者である本田和子の言葉を借りるならば、少女は、大人と子どもの間に「宙吊り」15にされた状態である。居場所の定まらない彼女たちは、不確かな将来に不安になり、苦悩する。16そのような苦悩を伴う影の部分とともに描き出された鋭い眼差しや強い目力は、悩み、もがき、疑問を抱きながらも、どうにかこの世界と対峙し生きてきた少女たちの強さなのである。
川西は、現代に活躍する芸術家が描く多種多様な少女について、芸術家自身が漫画やアニメを一種の教養として育ってきたこと、インターネットの普及により描き手と鑑賞者の距離が縮まったことによって、現実の少女たちの欲望や悩みがダイレクトに表出していると分析している。17もちろん、メディアの変化というべき特色はあるだろう。それに加えて、さきに述べてきた通り、芸術家自身に引きつけ描かれた作品においては、単なる客体として受け取ることはできようもない、当事者としての切実さが描き出されている。
その切実さというべき、少女の実際を描くことを可能にしたのは、女性が主体的に発言をできるようになったからである。しかし澁澤は、ウーマン・リブの真っただ中、発言する女性を嘆き、物言わぬ「物体(オブジェ)」として少女を求めた。18それからさらに半世紀の時を経て、散見されるようになったのが、芸術家自身の代弁者や分身としての少女像である。
美学者でフェミニストのキャロリン・コースマイヤーが、「歴史上の記録には女性の芸術家は存在したが、彼女たちはほんの少数であっただけでなく、その存在は芸術家についての言説にはほとんど影響を及ぼしていない」19と述べているが、日本美術にも同様のことが言えよう。明治以前の絵師のほとんどは男性であったし、また、西洋の芸術形態を借用することで成立した明治以降の日本美術にも同様のことが言える。しかしながら、フェミニズム運動の成果もあり、以前よりも着実に女性は語る存在になってきている。20一見、芸術家の個人的なことが少女表象を通して描かれているにすぎないようにもみえるが、そこには、男性中心主義的な芸術を批判するという社会的な側面がある。
芸術家自身と重ね合わされることで強さを纏った少女は、少女雑誌の全盛期、純粋で無垢で純潔であることが、近代国家形成そして少女たち自身にとって重要であった時期にはほとんど描き出されることがなかった。さらに、戦後の性的眼差しを主とする論や作品においても描かれてこなかった。それは、少女を「他者」「物体(オブジェ)」と位置付けていたためである。本節で例に挙げた芸術家たちは、「毒」、つまりは、純粋無垢とは相反する不純な部分を引き継ぎつつも、男性の自己愛として「物体(オブジェ)」化された少女とは異なる、生々しい少女の声にならない叫びのようなものを描いている。その切実な叫びは、複雑な社会をなんとか生き抜こうとする現代人の苦悩と共鳴しうる。これまでの、純粋無垢な理想的少女、語ることのないオブジェとしての少女、憂いを帯びた病弱な少女といった表象には描かれなかった強さが、これからの少女表象を分析する上での鍵となるであろう。
おわりに
少女を「純粋客体」としてコレクションにふさわしいとした澁澤の論は、「純潔」が少女にとってなにより重要であった明治から戦中には描き出されることのなかった、性的視線を前提とした「毒」をあぶりだし、その後の少女表象や少女論に影響を与えてきた。
澁澤は、少女に対する欲望は、「語らない女」に対する渇望であると述べた。その「フェティスト的」で「オナニスト的」な欲望を叶え、自己愛を満たしてくれる存在であったのが、少女なのであった。本論ではまず、少女が語らない存在であると位置づけている点に、フェミニズムの視点から批判を行った。
しかし、川西が澁澤の論を少女の「毒」をあぶり出したと評価したことを起点とし、少女の持つ「毒」について分析してゆくと、少女はただ単純に客体化されているのではないということが明らかとなった。そこには、少女があたかも自発的に性的魅力をアピールしているという主体性が見て取れたのである。本論では、その主体性にも注目し、「毒」を、これまでの表象から三種類に分類した。
一つ目は、中村の描いた少女のように性的眼差しをあざ笑うかのように変形した少女の悪意としての「毒」、二つ目は、性的魅力に無自覚か自覚的かという点で欲望する鑑賞者をゆり動かす、『ロリータ』のドロレスのように男性を翻弄させるという「毒」、三つ目が、欲望する主体を澁澤の述べた自己と重ね合わせた観念上のオブジェような「オナニスト」的欲望に閉じ込め、現実世界から乖離させ、静かに生命力を奪う「毒」であった。
これらの「毒」は、純粋無垢な少女表象によって巧妙に隠されていた少女の不純な部分を明らかにした点において評価できる。しかし、このような「毒」を描き出す作品の芸術的価値とは別に、本論で見てきたような、澁澤を中心に展開された欲望の対象として少女を捉えた論を、フェミニズム的視点からそのままの形で受け入れることはできない。澁澤を中心とする少女に関する論は、鑑賞者を女性の身体に欲望する異性愛男性に絞り、またその異性愛男性の視線をフェティッシュなものとして画一的に捉えすぎてはいないか。女性による少女への眼差し、男性による欲望の対象ではない少女への眼差しなどが欠けており、さらなる批判と、より踏み込んだ議論が行われるべきである。また、異性愛男性の眼差し以外の眼差しを多角的に取り扱っていくことも今後の少女論には必要となるであろう。なぜなら、既に現在、「毒」を引き継ぎつつも、これまでの異性愛男性の眼差しに根差した言説だけでは語ることのできない作品が生まれてきているからである。
近年の少女表象には、村上や会田のようなこれまで述べてきた「毒」を性的魅力に引き付け、描き出す形で継承しているものの他に、「毒」という不純なものの内に含まれる暗さに重点をおいた作品がある。それらには、「憂い」に近接しつつも、「憂い」とは同一できない、人間らしく苦悩する少女の姿、そしてそれを抱えながらも生きてゆこうとする強さが描かれている。主に2000年代に入ると散見されるようになる、新しい魅力とも言える強さを持つ少女表象の個々の作品分析は稿を改め詳しく分析する必要があり、この点については今後の課題となる。
澁澤が、少女論、少女表象に与えた影響は、可視化されてこなかった少女の性的魅力を露わにし、「毒」という一側面をあぶりだしたという点において大きく、今後も少女表象に影響を与え続けてゆくであろう。しかし、近年の多様な、性的視線だけで捉えることのできない魅力を持つ少女表象について分析するには、これまでの男性的な強者により言説や、少女を外から眼差す他者としての視点から一度離れる必要もある。少女は、「物体(オブジェ)」ではなく、また、時代を映し出す単なる「鏡」でもない。彼女たちを血の通う生きた存在として扱うことで、血の通う存在という前提の下で描かれた少女を分析することが可能となるのではなかろうか。
山田 萌果(北海学園大学大学院)
脚注
- 会田誠の《犬(雪月花)》シリーズは、森美術館で開催された『天才でごめんなさい』展(2012-2013)に展示された際、市民団体「ポルノ被害と性暴力を考える会(PAPS)」が撤去を要求した作品である。会田氏はこれに対しツイッターで見解を示し、森美術館と共にウェブ上で声明を発表し、抵抗した。本論において、その倫理的問題点や議論に対することについては詳しく触れないが、森美術館は、展示の際に十八歳未満禁止のエリアを設けるゾーニングにより作品を展示していることを再度アナウンスし、現代美術は評価の定まらないものを議論していくことが重要という見解を示している。また芸術教育を研究する神野真吾は、2016年に開催された社会の芸術フォーラムをまとめた「表現の自由と規制との間で考えるべきこと」において本問題について、森美術館が芸術家に責任を押し付けなかったことを評価している(社会の芸術フォーラム運営員会 北田暁大・神野真吾・竹田恵子『社会の芸術/芸術という社会 社会とアートの関係、その再創造に向けて』フィルムアート社、2016年、56-74頁)。
- 相馬俊樹「女性像に秘められた毒」芸術新聞社監修『美人画ボーダレス弐』芸術新聞社、2020年、72頁。
- 同上、73頁。
- 同上。
- HUFFPOST特集「ピカソがああ描くなら、俺はどう描くか?」かつて“少女”を描いた会田誠さんが見る“日本”とは」 (最終アクセス日2021.11.30)。
- 1980年代の少女論ブームについては、本連載第一回の註(13)を参照されたい。
- 代表的な研究に、大塚英志の『少女民俗学 世紀末の神話をつむぐ「巫女の末裔」』(光文社、1989年)、少女たちが使用する丸文字という特殊な字体を分析したジャーナリストの山根一眞による1986年の著作『変体少女文字の研究』(講談社、1986年)や、1987年に発表された美学者の増渕宗一による『リカちゃんの少女フシギ学』(新潮社、1987年)が挙げられる。
- 『初潮という切り札 〈少女〉批評・序説』(JICC出版局、1991年、39頁)において、横川は、当時の論は少女を「現代日本の文化情勢をくまなく映し出してくれるまたとなくすぐれた鏡」であったと述べ、「鏡が鏡である限り、結果は同じだろう。誰も鏡の未来など心配したりしない。鏡は、それを覗き込む者が見たいと思うものを上手に映し出していられるうちが花なのであり、少しでもひびが入れば捨てられるだけである。」と、日本を映し出すための鏡は、少女以外にも代替可能であり、男性の視点で語られる少女が少女たちの本来の姿を覆い隠していること、さらに、少女が日本を映し出す鏡として機能しなくなれば、もはや研究対象とはなり得ずに放り出されてしまうのではないかと1980年代の少女論を批判している。横川は、少女が「どのように生まれ、どのように時代と関わり、どのような問題を抱え、どこへ行こうとしているのか」を明らかにする本当の意味での少女論が生まれてこなくてはならないと述べている。
- 相馬俊樹、同上、74頁。
- 池永康晟監修『美人画づくし』芸術新聞社、2016年、89頁。
- 芸術新聞社監修『美人画ボーダレス』芸術新聞社、2017年、17頁。
- 同上。
- 他にも数人の芸術家が自分自身の作品への投影や悲しみや苦痛との関連を指摘している。濱口真央の発言や(『美人画ボーダレス』芸術新聞社、2017年、131頁)後藤温子の発言(『美人画ボーダレス弐』芸術新聞社、2020年、77頁)を参照されたい。
- 相馬俊樹、同上、74頁。
- 本田は、高等女学校制度を、「宙吊りの固定化」と例え(本田和子『女学生の系譜・増補版 彩色される明治』青弓社、2012年、154頁)、明治の少女たちを、「宙吊りにされ、特異化されて囲い込まれていくその経緯を、さながらに生き」たと述べている。(同上、194頁)。
- われわれ成人もまた、生と死などのあらゆる地点の間で「宙吊り」にされているにすぎない。多くの現代人が少女表象に魅了される理由のひとつに、この「宙吊り」が関係しているのではなかろうか。この点については紙幅の関係上今後の研究で述べてゆきたい。
- 川西由里「美人画と少女画のあいだ」、芸術新聞社監修『美人画ボーダレス』芸術新聞社、2017年、49頁。また、美術評論家の山下裕二も、篠原愛の画集の解説にて、アニメとの関係を指摘している。(山下裕二「寡黙な少女の分身――篠原愛の10年」篠原愛画集『Sanctuary』復刊ドットコム、2017年、135頁)。
- 日本におけるウーマン・リブ運動は、1970年前後に起きており、澁澤龍彦の「少女コレクション序説」の初出(『芸術生活』1972年4月号時期)と一致している。
- Carolyn Korsmeyer, Gender and Aesthetics: An Introduction, New York: Routledge, 2004, p.34.(キャロリン・コースマイヤー『美学 ジェンダーの視点から』長野順子・石井美紀・伊藤政志訳、三元社、2009年、66頁)
- しかしながら、コースマイヤーは、「芸術の世界や社会一般における女性の地位がラディカルに変化したにもかかわらず、過去の数世紀にわたって形づくられてきた概念的基盤はなかなか揺るぎ難い」(Ibid., p.34. [同上、67頁])と、フェミニズム運動によって女性の地位が向上しているにもかかわらず、哲学や芸術の領域における概念それ自体の不均等については未だ議論の過程であるとしている。この点については、今後の哲学、美学における課題として残されたままである。
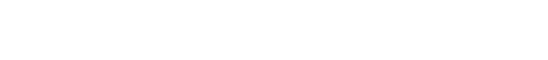

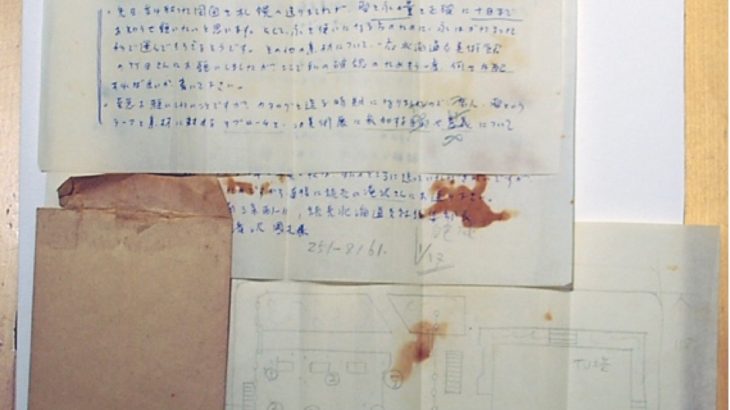


-730x410.jpg)
