*本稿は、「少女の魅力の一側面としての「毒」――澁澤龍彦「少女コレクション序説」 が戦後の少女表象に与えた影響―― (1)/山田萌果 │ Hokkaido Art Forum (hokkaido-art-society.net)」 の続編である。 http://hokkaido-art-society.net/newartforum/2021/06/22/post-863/
3. 少女の「毒」
少女の「毒」とは一体何であろうか。まずは、川西が「毒」という言葉をどのような意味で使用したかを明らかにし、そのうえで澁澤の論に立ち戻り、「毒」に関する他の論説を織り交ぜつつ、少女の「毒」とは一体何であるかを考察してゆこう。
川西は、前節でも引用した通り、中村と澁澤を例に挙げ、彼らのような作品によって「一般に無垢な存在とされている少女に向けた性的な眼差し」 1そして「不条理の象徴、あるいは欲望の対象とする動き」 2 が表れたと述べている。さらに、そのことについて、「少女を客体としてとらえた作品は、漠然とした「憂い」ともまた違う、少女が持つ「毒」ともいうべきものをあぶりだした」 3 と述べる。
川西は、少女の「毒」を「憂い」のような、少女の属性のひとつとして捉えている。川西の論において、「毒」という語は先の一か所で使用されるのみであるが、この語は少女表象の特質を照らし出すキーワードになり得ると考えられる。川西の解釈を押し広げながら、少女の持つ「毒」とは何かについて、以下考察したい。
では、川西が「毒」をもった少女の例として澁澤の論と並べ取り上げた、中村宏の描く少女を詳しくみてみよう。中村が描く不気味に笑うセーラー服を着た少女たちは、股を広げスカートの中を見せつけるような体勢をしている。『美少女の美術史』展において展示された油彩画《遠足》(1967年)には、目が一つしかない少女二人がそれぞれの陰部に互いの顔と足を擦りつける様子、骸骨のようなものを陰部にあてがい股を広げた少女、スカートを翻して自転車に跨る少女が描かれている。そこに、性的な意味合いが込められていることは言うまでもなかろう。またそこには、純粋な少女とは全く異なった、悪意という「毒」を巻き散らかす少女が描かれている。

*本画像は『美少女の美術史展』画集(青幻社、2014年)を撮影したものです。
少女は、先に述べた少女概念の形成期から少女雑誌の全盛期においては、純粋無垢、つまりは未だ自らの性的部分に無知で清らかな存在として描かれることがほとんどであった。やがて、澁澤の論により少女への性的な眼差しが白日のもとに晒され、また、中村の絵画にみられるように、性的な意味合いを前面に押し出し、悪意をむき出しにする少女までもが描かれるようになった。さらにのちに述べてゆくが、まるで誘惑するようなそぶりを見せる少女も描かれるようになったのである。それらは、純粋無垢な少女表象が描き出してこなかった部分であり、純粋無垢な側面を光とするならば、影となって表れる邪悪な側面であろう。
川西が述べた「毒」は、「憂い」と近接する領域、つまりは、純粋無垢とは異なった、その影となる少女の属性のひとつであり、少女を性的眼差しで捉えたときに浮かび上がってくるものであった。この点を踏まえたうえで、一度澁澤の論に戻ろう。以下に詳しく見てゆくが、澁澤の論と中村の絵画は、同じく少女の性的部分を扱っていながらも、その捉え方は随分異なっている。では、澁澤は、少女の性的な部分をどのように解釈したのであろうか。澁澤は、現実の女性が語り始めたからこそ、「物体(オブジェ)」としての「純粋客体」、つまりは少女を求めるのだと説いた後、論を以下のように続けている。
女の主体性を女の存在そのもののなかに封じこめ、女のあらゆる言葉を奪い去り、女を一個の物体に近づかしめれ ば近づかしめるほど、ますます男のリビドーが蒼白く活発に燃え上がるというメカニズムは、たぶん、男の性欲の本質的なフェティシスト的、オナニスト的傾向を証明するものにほかなるまい。そして、そのような男の性欲の本質的な傾向に最も都合よく応えるのが、そもそも少女という存在だったのある。4
一節で述べた通り、女性をひとつの物体として捉え、手の内に秘めておきたいというのが澁澤によれば男性の性的欲望の本質であるという。生身の言葉を奪われた女への欲望は、ひとつの「物体」への執着という意味で「フェティスト的」であり、さらに、その「物体」と自己との関係のみで欲望を完結させるという意味で「オナニスト的」なのである。澁澤はこの論で、その欲望に答える存在として少女がふさわしいのだと述べ、さらに以下のように続ける。
当然のことながら、そのような完全なファンム・オブジェ(客体としての女)は、厳密にいうならば男の観念のなかにしか存在し得ないであろう。そもそも男の性欲が観念的なのであるから、欲望する男の精神が表象する女も、観念的たらざるを得ないのは明らかなのだ。要は、その表象された女のイメージと、実在の少女とを、想像力の世界で、どこまで近接させ得るのかの問題であろう。5
男の欲望は、実体を伴わず、男性の想像の中で完結するのだと澁澤は述べる。彼らの欲望の対象は、彼らの観念の中で作り上げられた実体を伴わない「ファンム・オブジェ」である。実態を伴わない観念としての欲望の対象は、当然自ら語りだすことはない。彼らの理想像として従順な姿かたちをしている観念上の欲望の対象は、言葉を持たず、主体的に語りだしはしないとされる少女と重ね合わせられるのである。
また、澁澤は指摘していないが、少女が「オナニスト的」な欲望の対象となる理由のひとつに、少女の身体の変容可能性が影響してはいないか。少女の身体は、女性として完成した身体を持つ大人の女性と異なり、成長過程にある。身体が変化する状態は、言い換えれば変容の可能性を秘めているということになる。つまり、成長過程の身体を持つ少女は、欲望する眼差しの主が好むような性的存在となり得る可能性を持つ存在なのである。自らの観念上の欲望の対象である「ファンム・オブジェ」に接近させ、自分好みの「物体(オブジェ)」に変形できる可能性を持つ少女という存在は、「オナニスト的」欲望を持つ者にとって非常に都合が良いのではなかろうか。では、澁澤の論における、少女の「毒」とは、何であるか、この点については第五節で詳しく述べてゆくとしよう。
さて、川西が例に挙げた中村の作品もまた、少女の身体を変形させた作品である。しかし、そこに描かれる変形した少女は、澁澤が述べるような欲望の対象となる理想像としての「ファンム・オブジェ」とは全く異なっている。中村の描く少女たちは、実際にはあり得ないプロポーション、あり得ない顔の造形をしており、ぐにゃぐにゃとした異形のもののように描かれている。それは、セーラー服を着た少女に性的眼差しを向ける男性にショックを与えるような恐ろしい姿である。加えて、その異形の少女たちは、自らの性的部分を積極的にアピールしているようにみえる。そこには、次節でより詳しくみてゆく、〈男性を翻弄する〉という少女の「毒」の一側面が描かれているのである。
繰り返すが、川西が述べた通り、少女の「毒」とは、これまで扱われてこなかった、少女の「性」を積極的に扱うことで浮かび上がった少女の一属性である。本節では、そこからさらに踏み込んで、川西が例に挙げた二者の作品を分析した。そこで明らかとなったのは、澁澤の論と中村の作品は、少女を変形させているという一点において共通しているということである。少女が変形させられ描かれるのは、先に述べた通り、少女が成長過程にあって身体に変容の可能性を秘めているからではなかろうか。しかし、澁澤、中村が描き出した少女の変形は、同一ではなく方向性が全く異なっていた。澁澤が述べるのは、欲望の対象として男性の好みに変形させられる少女であり、また、中村が描いたのは性的眼差しを弄ぶかのように変形する少女である。その二つは、少女が性的な眼差しを向けられ、変形させられた際に現れる二つの姿なのではなかろうか。
4 少女表象における「毒」の中毒性
毒は、一度摂取してしまえば死を招く危険性がある。そのような危険を孕む毒に夢中になってしまった場合、中毒症状に陥ることとなる。少女表象にも、一種の中毒性が認められよう。前節で述べた通り、少女に性的な眼差しを向ける欲望する主体は、その少女を自由に変形させようとする。変形させた際には、欲望する主体の好みに都合よく変形した少女と、性的眼差しを向ける者が恐怖するようなぐにゃぐにゃと変形した少女の二つが浮かび上がる。一見相反するものと捉えたくなる、少女のこの二つの姿は、実は、純粋無垢という少女の光の部分と表裏一体の影の部分として一体化している。澁澤の述べる少女は、二節で述べた高等女学校令発令後に描かれていた純粋無垢な少女ではない。そこには、中村の描き出したようなぐにゃぐにゃと変形した、観る者を恐怖させる少女にいつ変化してもおかしくないような不気味さがある。欲望の主は、そのいつ脅威となるかわからないという部分に気づいていながらも、魅了されている。この危うさこそが、中毒性となり、ますます欲望の主が、危険を孕む刺激的な少女を求めることとなる。その危険性は、少女の主体性と関連付けられよう。澁澤は、「知性においても体力においても、男の独占権を脅かしかねない積極的な若いお嬢さんが、ぞくぞく世に現れてきているのは事実でもあろう。」 6 と述べているが、いつ蠢きだすか分からない少女の主体性に脅威を感じていたのではなかろうか。それ故に、頑なに少女に主体性を認めなかったのではないか。本節では、中毒を招く少女の「毒」と、少女の主体性との関連性を探ってゆこう。
写真家の飯沢耕太郎は、1988年刊行の少女に関する論集『少女論』に寄せた論考「写真・少女・コレクション」において、澁澤の『少女コレクション序説』を取り上げ、「少女、とりわけ美しい少女ほど、コレクションの対象としてふさわしいものはないのだ」という、一節に挙げた澁澤の言葉を引用したうえで、以下のように述べている。
しかし実際のところ、少女を「純粋客体」とみなし、オブジェとして蒐集できると考えるのは、男たちの観念や空想のなかだけのことであって、現実の少女たちはやすやすと彼らの欲望に答える(応える?:要確認)ような存在ではない。不思議な魅力に引き寄せられて手を伸ばしても、すんでの所で巧みに身をかわされ指一本触れることができないのが落ちであろう。欲望に火をつけながら、それを成熟させることを許さない、そんな彼女たちのありようが、男たちの「蒐集癖」をより強くエスカレートさせることになるのである。7
飯沢は、現実の少女が持つ、男たちの欲望をするするとかわしてゆくその特性、つまりは身をかわすという主体的行為こそが、男たちの少女を所有したいという欲望をさらに掻き立てるのだと述べている。身をかわされ、触れられないからこそ、「純粋客体」となり得る語らない少女を過剰に求め、人形、写真といったオブジェを収集するのだというのが飯沢の解釈である。ここで飯沢の述べる、男たちのコレクション欲に火をつける少女のありよう、言うなれば少女に性的に眼差しを向ける者にとって程よい主体性は、簡単に手に入らない、逃げられるかもしれないという、一種のスリルを味わわせてくれるスパイス程度の「毒」である。その「毒」には、彼らの身を破壊させはしない程度の中毒性があるのである。
男たちの欲望をするするとかわし、その欲望をさらに掻き立てる、少女の「毒」についてさらに考察を深めるうえで参照したい小説が、アメリカ文学に名を残したウラジーミル・ナボコフの著名な小説『ロリータ』8 である。少女ロリータことドロレス・ヘイズは、主人公である少女性愛者ハンバート・ハンバートの視線を無邪気に弄んでいる。物語は、ハンバートが、小悪魔的なドロレスに翻弄されてゆく様を捉えてゆくのだが、ドロレスの行動は、自らに向けられる欲望の視線を察しながらも「見られる存在」であることを面白がっているようにも読み取れる。

ドロレスの行う、無意識なのか意識的なのか、視線に気づいているのかいないのか曖昧な、性的に挑発的とも取れるその行動こそが、飯沢の述べたところの「男たちの「蒐集癖」をより強くエスカレート」させる、少女の「毒」の持つ中毒性ではなかろうか。眼差す側は、その「毒」にただ翻弄されるしかなく、コレクション欲に火をつけられることとなり、少女の持つ純粋無垢な側面と「毒」を持った側面の両義性に揺り動かされ続けることとなる。この両義性について、さらに詳しく述べると、少女が性的な眼差しに対して純粋無垢であり全くの無意識的なのか、それとも意識的で誘惑するそぶりを見せるのか、ということである。この二つの側面が少女にあることによって、鑑賞者の中に揺れが発生する。中毒性の元となる揺れを引き起こすこの二点について、以下でより詳しく見てゆこう。
まずは、少女は無邪気であり純粋無垢であるが故に、性的眼差しに気づかないという立場である。社会思想家である澤野雅樹は、ドゥルーズ=ガタリの少女に関する記述を独自に解釈した論考「少女――中間的なものへの感受性」において、ドゥルーズ=ガタリの少女に関する記述を独自に解釈した論考「少女――中間的なものへの感受性」において、「少女は無垢であるが故に視線の対象になる。見つめるだけでなく、覗かれ、睨まれ、狙われている。」9と述べている。第二節で紹介した、白瀧幾之介や霜鳥之彦などの描いたひたすらに眼差される少女は、澤野の述べるような、視線に無意識な少女であろう。そこには澁澤や中村によってあぶりだされた「毒」はなく、従来の理想像である純粋無垢な少女の姿がある。
対して、意識的に眼差しを受ける少女については、女性がそもそも見られる存在であるという言説に即して語られる。家族論、ジェンダー論を軸に活動する評論家の小浜逸郎は、『少女論』に収録された論考「主題としての少女」において、少女を従来の「女」の言説になぞらえ、少女がいかに「見られる存在」であるかを力説している。小浜は、「男子がファミコンに熱中している間に女子は「自分たち」に熱中している。要するに彼女たちは、自分の同族およびその対立項としての異族(同世代の男子)をひたすら「気にかける」あり方を通じてのみ自分であろうとする。」 10 のだと述べる。小浜によれば、若い女の子たちは自分の身体に磨きをかけ、「女性としてのエロス的魅力を身に付けることにひたすら執心している」 11 のだという。また、少女の書く文字が男子のそれに対して「うまい」理由について触れ、「字がうまいということは要するにおしゃれに関心を払ってきた時間が長いというのと同じ」 12 であり、それはつまり、「他者のまなざしをうけるものとしての自分をうまく統制して、はい、私はこれです、といって外部に差し出している」 13 のだとも述べる。小浜はそこに「「見られる性」としての女性の本質」 14 を見ている。
この小浜の論は、「見られる性」を「女性の本質」と断言してしまっている点において、近年のフェミニズム研究の知見から反論の余地がある。 15 女性が自らの意思に基づき、見られる存在であることを選び取っている、というように読み取れるこの論は、未だ社会的地位が向上していないがゆえに性的な眼差しを甘んじて受け入れざるを得ないという女性の置かれた現状を正当化する危険性を孕んでいる。以上の問題点を含むものの、見られる存在である少女が、見られる側であることを暗に承諾し、自らを「魅せて」いるという一種の主体的行為を行っているという指摘は重要である。それは、一方的に性的眼差しを向けられるという構造とは異なっている。小浜は、少女たちが視線に対してただ受動的であるのみでなく、したたかに、見られることを逆手にとって自分を魅せているということを示唆しており、このしたたかさはドロレスの行動とも一致する。
「毒」があぶりだされる以前には、視線に意識的な少女はほとんど無視されてきた。しかし、そのしたたかな側面が――たとえ欲望の主に都合の良い解釈であるとしても――明らかになることによって、鑑賞者の欲望を揺らす、「意識的か無意識的か」、「触れそうで触れられない」、「手に入れられそうで届かない」といった、二点間の行き来が誘発されたのである。その揺れは、少女の持つ特性のひとつであり、また、少女表象の「毒」の持つ中毒性となるのである。
以上を踏まえたうえで、さらなる揺れを提示した論があることを付け加えておこう。一節でも引用した論考「夢想する身体 バルテュスの描く少女たち」において倉林は、バルテュスの描く下肢を平気でさらけだす少女に、『ロリータ』のドロレスにも共通する、少女に特有のエロスなるものを見出し、以下のように述べている。
エロスは単に少女を見つめる我々の側にしかないのだろうか?一方的な眼差しを魅きつけ、しかも拒絶しながら、それ自身気づかぬままに無垢さを装っている、というようなエロスがそこに存在するのではないだろうか? 16
無垢とは本来、装うことのできないものである。しかし、倉林はここで、バルテュスの描く少女やドロレスのような、性的視線に意識的である少女たちが、「無垢」を装っていると述べ、そこにエロスなるものを見出しているのである。それを踏まえてみると、先にあげた澤野の論における、「無垢であるが故に視線の対象」となり、「見つめるだけでなく、覗かれ、睨まれ、狙われている」という見方にも疑念が生まれる。その無垢は、主体性を持つ少女によって装われたものである可能性があるのである。
澁澤が見ようとしなかった少女の主体性こそが、鑑賞者の欲望に揺さぶりをかける要因である、「意識的か無意識的か」という疑念を生み出し、中毒性を引き起こす要因となる「毒」なのではなかろうか。
5.危険で安全な「毒」
次節でも取り上げる、美術評論家の相馬俊樹は、「女性像に秘められた毒」と題した論考において、「毒」について「たとえば、苦、病、腐、狂、幻、魔、怪など気配と予感であり、あるいは官能の邪気と濃霧である」 17 と述べる。さらにジョルジュ・バタイユの論を取り入れつつ、「毒」は、「個人の生の安定(均等)を守る日常的秩序の枠組み(防壁)を揺るがし、危険に晒す」 18 と述べ、また、その「毒」の危険に身を委ねなければ、魅惑の核心には触れられないとも述べている。少女の「毒」の危険性の中にはもちろん、社会規範や倫理的問題も含まれるであろう。しかし、少女を性的眼差しで捉え、純粋客体とみなす際についてくる危険は、それだけではない。欲望する男性たちには、「毒」に内在する少女の主体性が彼らを脅かす可能性が常に付きまとっているのである。
先にみてきたとおり、少女の「毒」の中には、見られることを逆手に自ら性的な部分を露わにし、誘惑するファム・ファタールのような側面が含まれている。しかし、破滅へと誘う実際のファム・ファタールの概念と異なるのは、欲望する視線の下における少女が、見られることを意識し始め、性的消費の対象となり始めたばかりの期間を過ごす、〈前女性〉であるという点である。澁澤は少女を「純粋客体」と位置づけた。それは、少女が〈前女性〉であり、自ら言葉を発しない存在であるという、「オナニスト的」な希望的観測に基づいていよう。ファム・ファタール的側面があるとはいえ、成人男性という社会における圧倒的強者からみて少女は未熟で力ない存在である。ゆえに、彼らを破滅に導く可能性は極めて低いのであり、その点において安全な性的対象なのである。欲望する主体によって作られた客体としての少女にしたたかさが描き出されていようとも、それは安全な存在が魅せるしたたかさであり、あくまでもその圧倒的強者の欲望の手中に収まり続けているのである。欲望する眼差しの下における少女は、危険を味わうことができる安全な存在なのではなかろうか。
では、澁澤の少女論における「毒」はどの点にあるだろうか。それはやはり、澁澤独自の「純粋客体」という少女への解釈と関係してくる。澁澤は論の終盤、「物体(オブジェ)」としての少女の極限の形態として、ネクロフィリアと人形愛を挙げ、以下のように述べる。
死んだ者しか愛することのできない者、想像世界においてしか愛の焰を燃やそうとしない者は、現実には愛の対象を必要とせず、対象の幻影だけで事足りるのである。幻影とは、すなわち人形である。人形とは、すなわち私の娘である。人形によって、私の不毛な愛は一つのオリエンテーションを見出し、私は架空の父親に自分を擬することが可能となるわけだが、この父親には、申すまでもなく、社会の禁止の一切が解除されているのである。 19
他者とのコミュニケーションは、他者を物体視しては成り立たない。なぜなら他者は意志を持つ主体であるからである。自己の想像世界に引きこもる「オナニスト的」欲望を持つ主体は、自分の思い通りになる欲望の対象を求めている。思い通りになる対象、つまりは「純粋客体」としての「物体(オブジェ)」を求める彼らにとって、他者の意志、つまり主体性は、邪魔な存在である。澁澤の述べる少女の「純粋客体」性は、死体、人形といった「物体(オブジェ)」への偏愛という究極の部分にまで到達するのである。では、先の引用で述べられた「私の娘」とは何か。
澁澤は、「物体(オブジェ)」としての少女の極限の形態としての人形愛に触れたのち、「少女コレクション序説」を、「人形を愛する者と人形とは同一なのであり、人形愛の情熱は自己愛だったのである。」 20 と締めくくっている。自己の想像世界への閉じこもりは、他者の主体性の否定と自己愛によって成り立つ。少女を「物体(オブジェ)」として投影した欲望の、その正体は男性の自己愛なのだと結論付けているのである。人形という魂のない身体「物体(オブジェ)」は自分の一方的な欲望を一切拒むことなく受け入れ、自己の「想像世界」における欲望の完結を拒絶してはこない。観念上の「私の娘」とは、現実の意思を持ち反発する娘とは異なり、人形と同様に想像世界での閉じこもりを否定してこない。観念上の「私の娘」は、自分の性質を受け継ぎ、自分の手で自分好みに育てることのできる意思のない「純粋客体」なのである。
また、視点を変えれば、それらの「純粋客体」は、閉じこもる自分の「オナニスト的」な欲望を映し出す機能を持っているとも言える。澁澤の述べる少女論における「毒」とは、この部分にあるのではなかろうか。死体、人形、「私の娘」、そして、少女。それらは、閉じこもる欲望の主を、他者との交流からより遠いところまで引き離してしまう。澁澤が述べる少女の現実世界から遠く離れた不気味さは、自己愛を満たすためだけに浮き上がる、魂のない冷たい物体なのであり、その不気味さこそが、澁澤の述べる少女に見出すことができる「毒」ではなかろうか。
少女概念の形成期に描かれた、理想的な少女の姿、少女たちの目標とするべき姿として表象されてきた、無知で純粋無垢な少女という表象には、少なくとも生命をもつものとして、生き生きとした魂なるものが描かれてはいなかったか。また、そののちに性的眼差しを持って描かれた「毒」を持つ少女にも、その魂なるものは描かれていた。中村が描き出した少女の悪意も、『ロリータ』のドロレスの誘惑も、生きる者としての魂が描かれているからこその表出する「毒」である。澁澤の述べる無機質な「物体(オブジェ)」には、それらと同様に少女に対する性的な眼差しを扱いながらも、それらとは異なる自己愛を満たすための、不気味な「毒」を見出すことができる。その不気味な無機質の「毒」によって、欲望を満たそうとする者は、その観念世界において生命を消耗し、現実世界との乖離を深刻化させてしまうのではなかろうか。これまで議論の俎上に載せられることは少なかったが、少女を、言葉を発さない欲望の対象となる「物体(オブジェ)」としてフェティッシュに愛する澁澤の視点は、生きた女性、生きた少女の声や言葉を聞こうとしない閉鎖的な態度であり、フェミニズムの視点から批判されて然るべきである。
ここで、これまで述べてきた「毒」についてまとめよう。川西は、「毒」を少女の一属性であると指摘した。第三節で断った通り、本論ではその川西の規定した「毒」を敷衍する形で展開してきた。そのことによって明らかとなった「毒」は、三つあった。ひとつは、中村が描いたような変形した姿で悪意をむき出しにする少女の「毒」。二つ目は、『ロリータ』におけるドロレスのようなしたたかさを持ち誘惑する、少女の主体性と関連する「毒」。三つ目が、本節で述べた、欲望する者を観念上に閉じ込め、静かに生命力を奪う、無機質で不気味な「物体(オブジェ)」としての「毒」である。
澁澤の論から時代は流れ、澁澤のような少女に対する眼差しだけでは語ることのできない、生きた少女の声が反映された作品が近年には見られる。それらは、ここまで述べてきた「毒」の系譜にあるが、それらとは異なった少女である。そこには、これまで述べてきた、欲望の主をより一層夢中にさせるが脅威とはならない、男性のための主体性とは異なった、少女たちが自らを主張するような主体性が表現されているのである。それは、女性性を敢えて高らかに主張するフェミニズム・アートのように、性的欲望を刺激する、程よいスパイスとしての主体性とは異なった少女性を高らかに主張している。のちにみてゆく通り、少女表象は数十年の時を経て変化してきたのである。では、「毒」はどのように受け継がれ、またどのような変化を遂げてきたのであろうか。次節以降では、現代の少女表象を中心に分析してゆこう。(続)
山田萌果(北海学園大学大学院)
脚注
- 川西由里「美人画と少女画のあいだ」芸術新聞社監修『美人画ボーダレス』芸術新聞社、2017年、49頁。
- 同上。
- 同上。
- 澁澤龍彦『少女コレクション序説』中央公論新社、1985年、12-13頁。
- 同上、13頁。
- 同上、12頁。
- 飯沢耕太郎「少女・写真・コレクション」、『少女論』青弓社、1988年、40頁。
- ウラジーミル・ナボコフ『ロリータ』若島正訳、新潮文庫、2006年。/ Vladimir Nabokov, Lolita, Olympia Press, 1955.
- 澤野雅樹 「少女——中間的なものへの感受性」、『現代思想』2002年8月号、青土社、2002年、231頁。
- 小浜逸郎「主題としての少女」、『少女論』青弓社、1988年、93頁。
- 同上、90頁。
- 同上、98頁。
- 同上。
- 同上。
- 女性がおしゃれをすることは、他者に見られること以外にも、女性たち自身を奮い立たせるためや、女性たち自身が心地よく過ごすためなど、他者の視線だけが動機ではない。女性のおしゃれには多様な動機があり、文字も同様に、美しい字を書くことを安易に見られることを意識しているからだと捉えるのはあまりにも短絡的である。もちろん、女性が、社会に蔓延る女性に対する視線を敏感に感じ取り、常に見られることを意識せざるを得ないという点は事実であろう。しかしそれは、女性の生きづらさのひとつでもあり、小浜の述べるような、女性が「本質的」に見られる存在であり、見られることに対して積極的であるというのは、社会に内在している父権的な視点における理想論である。
- 倉林靖「夢想する身体 バルテュスの描く少女たち」、『少女論』青弓社、1988年、59頁。
- 相馬俊樹「女性像に秘められた毒」芸術新聞社監修『美人画ボーダレス弐』芸術新聞社、2020年、72頁。
- 同上、73頁。
- 澁澤龍彦『少女コレクション序説』、22頁。
- 同上。
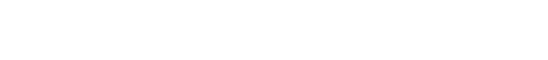

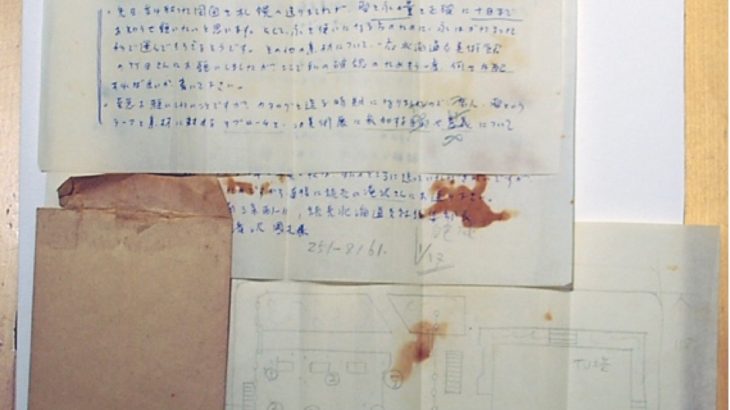


-730x410.jpg)
